トヨタ全店全車販売 国内メーカー提携 コロナ ゴーンショック… クルマ界「あの話題」の前と後
日本の自動車業界を見てみると、新機軸となる新たな何かを始めることは多い。また、突如何かに襲われることもある。それらにより「前とは違う」の姿に変化していることもあるにちがいない。
「それ」によりどう変わったのか? この先の予測も含め、8本のテーマについて探っていく。
ライズ&ハリアーに押されて苦戦気味!? 好調だったRAV4が新車販売で失速している!?
●トピック
・国産メーカー、提携の前と後ではクルマはどう変わったか?
・トヨタのカンパニー制導入。この先も含め、導入後の変化はないのか?
・日産、カルロス・ゴーン体制時とその後で社内変化はあるのか?
・トヨタ全店の全車扱いが実施されて、販売現場で起こった変化とは?
・トヨタがダイハツを完全子会社化。ダイハツのクルマは変わったのか?
・フルモデルチェンジを経て販売が大きく伸びたモデル、逆に低速したモデル
・リーマンショックの前と後業界は「何が」一番変わったのか?
・コロナ蔓延の前と後、クルマ界はどう変わった?
※本稿は2021年2月のものです
文/桃田健史、国沢光宏、渡辺陽一郎、井元康一郎 写真/NISSAN、ベストカー編集部 ほか
初出:『ベストカー』 2021年3月10日号
【画像ギャラリー】本文で出てきた以外にも…フルモデルチェンジで沈んだクルマ&浮上したクルマ
■国産メーカー、提携の前と後ではクルマはどう変わったか?
この先の企業成長のため、国内メーカーや外資と提携するメーカーは多い。その提携の「前と後」ではクルマはどう変化したのか? 今後は? トヨタ、スバル、マツダ、三菱、ホンダについて追ってみた。
* * *
スバルがトヨタから頼まれた。2社の関係の第一歩は、そうしたイメージだ。その象徴はもちろん、2012年に登場した「86/BRZ」である。
豊田章男社長の時代となり「トヨタ車で走りを楽しむこと」を、トヨタ改革の中核に置き、社長自らが評価ドライバーとして開発の前面に出るようになった。
86/BRZ初号機のステアリングを握ったあとに“トヨタ車らしさの要望”をスバルエンジニアに伝えた……、といわれている。
また、豊田社長はSTIに対して強い関心を持ち、東京モーターショーなどでSTI関係者らと楽しそうに会話するシーンを見かけたものだ。
両社の提携後、こうしたトヨタとスバルの、人と人との繋がりが、のちのGRヤリスへと進む道を築いた。
一方、スバルは提携後、トヨタから開発面の厳しいコストと時間の管理など、企業として多くのものを学んだ。
むろん、この先、電動化の共同開発への期待も大きい。
国産メーカー4社、提携後の変化はこれからより鮮明になる!?
●提携後、刺激を受けるトヨタ
では、2017年に資本提携したトヨタとマツダはどうなのか。
マツダもロードスターというキラーコンテンツがあるが、トヨタの関心はそこではなく「一括企画」にある。一括企画とは、車体などを共通化するコモンアーキテクチャーと、フレキシブル(臨機応変)な生産の構想が、実際の開発と生産を動かすという企業としての概念であり、かつ事業戦略である。
トヨタにもTNGAという技術的な基盤はあるが、マツダのように短期間で商品改良を行うことに対する大きな刺激を受けたことは確かだ。
それが、レクサスの「ALWAYS ON」という開発方針に直結している。
一方で、マツダのトヨタに対する最大の関心事は、スバルと同じく電動化対応だ。
ただ、これもスバルとマツダの同じ悩みだが、スバルなら水平対向型、マツダならSKYACTIVと、トヨタ主体のEV(e-TNGA)を、今後どう両立させていくのだろうか?
●「餅は餅屋」の3社
次に、ルノー・日産・三菱だが、2019年からの関係強化で「餅は餅屋」の戦略がはっきりし、商品企画、開発、製造、営業の各社の各部門で、自分たちがやるべきことが見える化された。
三菱にとっては、PHEVの量産効果や、軽の生産技術での特化がプラス効果を生んだ。
今後も、3社で聖域なきドラスティックな組織再編が進む可能性も考えられ、結果的に三菱もしっかりと生き残っていくことになるだろう。
最後にホンダとgm(※)だ。
ホンダ主導で進んできた燃料電池車での連携から、北米向けEVプラットフォーム「アルティウム」採用や、自動運転技術開発企業クルーズとの連携など、次世代技術の中核をgm主導へと大きく軌道修正したホンダ。
ホンダ経営陣は、自前主義からの転換を掲げるが、ホンダ愛の強いエンジニアたちはこれからのホンダをどう考えるのか。
ここがホンダの将来を決める大きなポイント、となるだろう。電動化へとどう舵を切るか、注目したい。
(TEXT/桃田健史)※GMは今年(2021年)から社名を小文字表記に変更
■トヨタのカンパニー制導入。この先も含め、導入後の変化はないのか?
ざっくりいうと、トヨタ社内にいくつかの会社を設けるようなカンパニー制。2016年導入とまだ日が浅いが、変化の兆しは見えないのか!? 国沢さん、わかる部分、あります?
* * *
編集部から電話かかってきて「2016年にトヨタがカンパニー制を導入しましたけれど、導入前と後で変わったことを書いてほしいのですが」。
う~ん! 最初から白旗をあげます。そんなこと外部からわかるワケない。
100歩譲って10年ほど経過した後なら売れゆきなどで評価できるものの、5年ではカンパニー制になってから企画したクルマが出るか出ないか、というタイミング。結果すら出ていない。
とはいえ「書け」と言われたら何かカタチにしなくちゃならない商売なのでトヨタに「まったく見当違い!」と言われることを覚悟で以下。
まずカンパニー制の目的だけれど、各部門で結果を出しなさい、ということだと思う。
なかには「各部門の採算性を追求するため」という人もいるけれど、そんなこと言ったら『先進技術カンパニー』なんか直接的な利益をあげられない。『パワートレーンカンパニー』だって稼げないです。
さらに「カンパニー制導入で変わったように感じるか?」と聞かれたなら、「外部からは今までとの明確な違いは感じません」と答える。
プレジデントと呼ばれるカンパニー長同士の関係も、以前から仲よければそのまんま。悪いとウワサされる人達は相変わらず悪いまんまです。
独自性が伴ったりするかどうかについちゃ、プレジデントの人柄次第。ここまで読むと「なんのために取り入れたんでしょう」と思うかもしれません。
強いて言えば独立性が付きましたね、と感じる。プレジデントの責任分担は従来より明確になった。自分のカンパニー内であれば、独自の判断もできるようだ。
例えばRAV4やハリアー、MIRAIを担当しているミッドサイズカンパニー。相当自由なクルマ作りをしているように思う。
あまり話題にあがらないけれど商用車を中心に作っているCVカンパニーもカンパニー制度が始まってから業績を伸ばしてます。しっかり機能していると思う。
トヨタ「カンパニー制」はこのような中身
(TEXT/国沢光宏)
■日産、カルロス・ゴーン体制時とその後で社内変化はあるのか?
いろんな意味で日産の顔だったカルロス・ゴーン。氏の体制が終わってから2年と数カ月経過。その後の日産に変化はあるか? 商品戦略は変わったのだろうか?
* * *
2018年11月、1999年6月から19年余にわたって続いていた日産のゴーン体制が突如瓦解した。日産という企業、文字通りゴーン思想で動いていたことを考えると、混乱に陥ったことは想像に余る。
とはいえさすがのゴーンも、日産のすべてをコントロールしていたワケじゃありません。
飛行機でいえば、巡航高度で飛んでいる状態。ゴーン体勢末期になると少し気流の悪い空域となってましたが。
加えて自動操縦(オートパイロット)のスイッチも入っているため、ゴーンの指図なくても日産という飛行機は飛んでいられる。
しかし! 飛んではいるものの、それまでの空域選びに判断ミスあったため、状況は徐々に悪化。さらに目的地選びもしなければならなくなっていた。
表向きは混乱していないが、突如機長を失った飛行機と同じようになってしまったワケです。そして次の機長も見えず。
日産グローバル本社
●舵取り役は内田社長だが…
実際、今の日産を誰がコントロールしているのか見えにくい。というか誰なんだろうか?
内田誠社長がすべて決めているかとなれば、そうじゃないように思える。
豊田章男社長と違い、オールラウンダーじゃありませんから。2003年に日商岩井から日産に入ったあとの経歴、主として購入関係。自動車企業の社長としてのパーツをすべて持っているかと聞かれたら難しい。
ルノーとの関係もコントロールしなくちゃならない。
この件、日産の皆さんに聞くと口を揃えて他に適任はいないと言う。「最高じゃないかもしれないが、内田で行くと決めたから前を向いて頑張るしかない」ということです。
幸い、ゴーン体制末期に日産のデザインをすべて決めていた中村史郎さんが2017年に退任。アルベイザさんという才覚あふれた人に代わった。
これから出てくるモデル、軽の電気自動車を除き、すべて売れそう。いい人事だったか?
2017年にデザイン・トップに就いたアルベイザ氏。氏のテイストが現在、浸透中
●日産、案外いい感じかもしれない(!?)
戦略面とルノーとの折衝は、あまり表に出てこないけれど、井原慶子社外取締役がいい仕事をしているようだ。
現在仕込み中の新型車群は、井原さんの意向が大きく反映されていると聞く(e-POWER戦略も井原さんが猛プッシュしている)。
500万円という思い切ったARIYA(アリア)の価格戦略も、星野朝子副社長、井原さんともに強く支持している模様。
ルノーとの折衝も日産ペースで進んでいるという。日産、案外いい感じなのかもしれません。
(TEXT/国沢光宏)
【閑話休題】変化の現われはデザインにも! Vモーショングリルが進化中だ
本文中にもあるが、ゴーン体制末期の2017年4月、デザイン・トップに就いたのが写真上のアルフォンソ・アルベイザ氏。
ここにきて日産車全体のデザインの方向性も滲み出てきており、象徴的なのがVモーショングリル。今年登場のアリア、こうして見ると2013年登場のエクストレイルより進化していることがわかる。
日産 アリア
■トヨタ全店の全車扱いが実施されて、販売現場で起こった変化とは?
トヨタの販売店が全国的に全店で全トヨタ車を扱い始めてもうすぐ1年。販売現場で起こった変化とは?
* * *
2020年5月以降、トヨタのすべての販売店でトヨタの全車を買えるようになった。この変更で生じた最も大きな変化は、トヨタ車同士の競争と販売格差が広がったことだ。
一番顕著なのはアルファードとヴェルファイアの登録台数。
現行型の登場時はヴェルファイアが多く売れたが、マイナーチェンジでフロントマスクを変更するとアルファードが上まわった。
さらに全店が全車を扱うようになり、2020年12月の登録台数はアルファードが前年の1.5倍に増えて、実質的に同じ内容のヴェルファイアは半減している。
登録台数に8倍の差が生じた。以前はヴェルファイアを専門に販売していたネッツトヨタ店からも「最近はアルファードに乗り換えるお客様が増えた」という話が聞かれる。
同様の理由でハリアーも登録台数を伸ばし、以前から全店で販売していたプリウスやアクアは、顧客を奪われて売れゆきを下げた。
ルーミーも1.5倍に伸びたが、姉妹車のタンクは廃止された。
このように販売格差が広がると、人気車は生産が間に合わず納期が遅れる。販売店では「アルファードの納期は3カ月を要しており、ヤリスクロスもハイブリッドは半年以上に達する」という。
また、トヨタの販売会社同士の競争が激しくなった。例えばアルファードやハリアーは、以前はトヨペット店だけが扱ったから、ユーザーは販売系列を選べなかった。
しかし今は全店が扱うため、より自宅に近い店舗でも購入できる。
取り扱い車種が共通になったので、店舗の立地条件を含め、販売会社の実力が従来以上に問われるようになった。
トヨタ店とネッツトヨタ店が隣接する場合など、従来は販売車種が異なるから併存できたが、今後は競争に負けて廃止される店舗も生じる。
「取り扱い車種が一気に増えて商品知識が追いつかない。特に修理を行うメカニックが苦労している」と話す販売店員もいる。販売と修理の両方で手間を要するだろう。
このように全店が全車を扱うようになり、車種の売れゆきから販売店の実績まで、トヨタ同士の競争と格差が進んだ。その結果、車種や店舗数の減少、納期の遅延などユーザーの不利益も生じている。
都内のトヨタ販売店はひと足早く2019年5月から統合されて、店舗外観も新しくなっている
(TEXT/渡辺陽一郎)
■トヨタがダイハツを完全子会社化。ダイハツのクルマは変わったのか?
2016年にダイハツはトヨタの完全子会社となったが、その後、ダイハツとダイハツ車に変化はあったのか?
* * *
2015年のダイハツの小型/普通車登録台数は1年間で1624台だった。ところが2016年には、前年の4倍以上になる6859台に増えている。
販売店では「2016年にダイハツがトヨタの完全子会社になり、4月に新型ブーン、11月にはトールも加わって売れゆきを伸ばした。従来と違って小型車の試乗車も用意され、テレビCMも活発に放映している。ダイハツがトヨタの完全子会社になり、小型車に力を入れるようになった」という。
今ではロッキーも堅調に売れて、2020年のダイハツの小型/普通車登録台数は5万6054台だ。5年前の35倍に達する。
ダイハツの小型車にも変化が生じた。従来はトヨタに供給するOEM車と同じ内容だったが、現在のロッキーはトヨタのライズにはないソフトレザー調シート内装の最上級グレードを設定している。
ダイハツが小型車に力を入れる背景には、近年は軽自動車とリッターカーの自動車税の差が小さくなっているのに加え、今後はトヨタが主導して小型・普通車の販売に力を入れるため。
これらにより将来的に軽自動車の販売低下が懸念され、ダイハツも軽自動車偏重の売り方を抑えている。
(TEXT/渡辺陽一郎)
【閑話休題】ダイハツ社員へ聞いてみた!
トヨタの完全子会社化によってダイハツでの仕事の変化は? ダイハツ広報によると、もともとトヨタグループの一員という位置づけだったので大きな変化はなく、「広報業務も以前からトヨタさんと常にやり取りをしていました。その頻度が増えた面はありますが、ダイハツ車のPRという意味では変わらない形でやっています」とのこと。
■クルマの「前と後」フルモデルチェンジを経て販売が大きく伸びたモデル、逆に低速したモデルの「なぜ」
フルモデルチェンジした後大ヒットするクルマもあれば、「前のほうがよかった」と嘆くクルマも。ナゼそうなった?
* * *
当たり前の話ながら、自動車メーカーは販売台数を増やすためフルモデルチェンジを行う。
なかには新型N-ONEのように「撤退することも攻めることもできない」苦肉の策のモデルチェンジなどあるけれど、基本的に「先代よりたくさん売りたい!」と考える。
されど失敗することだってあります。典型例が現行プリウス。先代プリウス、世界規模で売れまくりました!
日本市場においても1年以上バックオーダーが解消しなかったほど。アメリカや欧州に行くと、いまだにたくさんの先代プリウスをタクシーとして使っているほど。
そして現行モデル、登場直後の2016年の販売台数は約24万8000台と、約16万8000台売った2位のアクアに大差をつけたが、その後、大失速。販売台数は激減! 2020年の販売台数見ると20位に沈んでしまった。
●「カッコ悪いものね……」
なぜ大失敗したか? もう簡単です。歴代すべてのプリウスを買ってきた私も現行モデルは見た瞬間「こら買う気にならん!」と思うほどカッコ悪かったからだ。
プリウス。今はこの顔です。2020年販売台数:6万1500台/ランキング21位(PHV、α含む)
燃費など向上しているものの、あそこまで厳しいスタイルだと腰が引けてしまう。
今回編集部が選んだ「失敗した3モデル」を見ると、すべて先代よりカッコ悪いと思う。ステップワゴンも見た瞬間「シルエットが軽自動車と同じですね」。いいクルマなのに。
ホンダ ステップワゴン。ハイブリッドが高価すぎか。2020年販売台数:3万4441台/ランキング32位
エルグランドは先代が大きく立派に見えるデザインを採用し人気に。けれどモデルチェンジで地味にしちゃった。現行ヴェルファイアが地味路線を選んだ結果、アルファードの10分の1しか売れなくなったのと同じ理由です。
ヴェルファイアからアルファードに移ったのと同じく、エルグランドからアルファードに逃げた。
●デザインの役割が大きい
成功した4モデルはどうだろう?
アルファードの場合、先代は地味なフロントグリルだったが、フルモデルチェンジ&MCでオラオラ的になり、車名からしてオラオラ的なヴェルファイアを地味に。すると! 先述どおり、アルファードの10分の1しか売れず。
トヨタ アルファード。いい感じのオラオラ顔になり今もヒット中。2020年販売台数:9万748台/ランキング7位
販売台数におけるデザインの役割、超大きいです。同じくノンビリしたデザインだったRAV4も、新型でガラリとアウトドアに振ってきた。ハード文句なし! 価格文句なし! 売れない理由を見つけられないほど。
トヨタ RAV4。スタイルも走りも一本筋の通ったSUV。2020年販売台数:5万4848台/ランキング24位
同じくヴィッツ改めヤリスも絶好調! 2016年は10位だった販売台数が5位に。同じくスペーシアもデザインでイメチェンしてます。こちらは2位へ大躍進!
(TEXT/国沢光宏)※紹介した「ランキング」は、登録車と軽自動車をすべてあわせた総合順位です
■リーマンショックの前と後 業界は「何が」一番変わったのか?
2008年に世界経済を揺るがしたリーマンショック。この戦後最大の金融危機の後、日本の自動車業界が一番変わったのは何だったのか?
* * *
2008年に起こったリーマンショックは自動車メーカーの経営にも大きな影響を与えた。
2000年代半ばまで、日本メーカーは基本的に思いついた新商品や新技術をイケイケドンドンで出す傾向が強かった。
モデルチェンジは4年ごと。クルマの中身は同じながらデザインが違うという、いわゆる“兄弟モデル”を出すのもごく当たり前のことであった。
ところがリーマンショックを境に、新型車の数が各社とも激減した。数だけでなく内容的にも遊び心や個性があるようなクルマが減り、ベーシックなクルマが大半を占めるようになった。
リーマンショック時に日本メーカーは一様に経営のための資金が不足し、黒字なのに最悪倒産を迎えるのではないかというほど肝を冷やした。そこで各社、キャッシュを潤沢に持たなければ危ないと考え、経営効率を高めるためにモデル数を減らす方向に一斉に動いたのだ。
その結果、日本メーカーの経営体質は強くなり、今回のコロナ禍を充分に耐えきることができた。だが、ユーザー側としては新商品が減ったことを寂しく感じるのもまた確かであろう。
トヨタも昨年から全店で全車を扱うようになり、ノアなどの今ある兄弟車が統合される予定
(TEXT/井元康一郎)
■コロナ蔓延の前と後、クルマ界はどう変わった?
2020年初頭から全世界を覆い、いまだ出口の見えないコロナショック。その渦中で自動車業界にはどのような変化が起こっているのか?
* * *
コロナ禍で自動車メーカーのストラテジーにも変化が生じる可能性が出てきている。
ひとつは短期的な商品戦略。世界の自動車マーケットはコロナショックにもかかわらず、順調に販売を回復させているが、問題は今後。
世界各国が膨大な財政赤字を抱えたのはリーマンショック以上の爆弾材料で、どの市場でどのようにクルマが売れるかが不透明になってきている。
ポストコロナ時代を生き残るカギは、アメリカ、中国、ヨーロッパ、ASEAN、そして日本など、特定の市場に過度に依存しないこと。仮にひとつのマーケットが不調になったとしても、別のマーケットで補えるような柔軟性を持てるかが勝負となる。
そのために、複数の市場に向けてクルマを作り分ける必然性も出てくるだろう。
コロナショックによるもうひとつの変化は、メーカーが抱くモビリティの展望だ。
2016年にダイムラーがコネクティビティ、自動運転、シェアリング、電動化、この4分野の技術革新を表した「CASE」という概念を提唱して以降、世界の自動車業界はそれを巡って激しい技術競争を繰り広げている。
CASEを通じてメーカーが実現させたいのはMaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)、つまりクルマを個人に売るのではなく、すべての交通手段による移動をひとつのサービスととらえる自動車産業のサービス業化だ。
ところが、コロナショックの後、一時は少し盛り上がりを見せた、自動車サービスの象徴のひとつ、カーシェアの需要が減少に転じるという現象が多発しているという。
感染症への警戒感から不特定多数の人が触るカーシェアを嫌がり、中古でもいいからマイカーへと後戻りするケースがあとを絶たない。
MaaSはもちろん実現させていくべきビジネスだ。
しかし、コロナ禍で自動車メーカーは無人バスや無人タクシーで乗客をA地点からB地点に運ぶというMaaSだけでなく、クルマを個人所有して移動の自由を存分に味わえるタイプの次世代車も大事にしなければならなくなった。
未来のモビリティサービスに向けてトヨタが昨年12月に発表した自動運転EVのeパレット
(TEXT/井元康一郎)
【画像ギャラリー】本文で出てきた以外にも…フルモデルチェンジで沈んだクルマ&浮上したクルマ
こんな記事も読まれています
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
おすすめのニュース
-
-
レスポンス0
-
-
-
レスポンス1
-
Merkmal1
-
-
-
-
愛車管理はマイカーページで!
登録してお得なクーポンを獲得しよう
おすすめのニュース
-
-
ベストカーWeb10
-
-
-
Auto Prove0
-
レスポンス0
-
-
-
-
-
ベストカーWeb8
-
-
-
-
-
-
motorsport.com 日本版0
-
-
motorsport.com 日本版0
-
-
-
motorsport.com 日本版0
-
AUTOCAR JAPAN2
-
ベストカーWeb14
-
-
Webモーターマガジン0
-
-
バイクのニュース0
-
-
業界ニュースアクセスランキング
-
スズキが新型「ジムニーノマド」注文停止でお詫び! 発表4日後に5万台受注!? 一方で「シエラ離れ」起きている?なぜ? 軽ジムニーは1年待ち続く
-
ジムニーノマドがもう買えないなら[新型ランクルFJ]に期待するしかない!? 2025年秋のデビューで300万円台!?
-
[ノア]を実際に買うと500万円!? 新車367万円のクルマがここまで高額になる[パッケージオプション]の正体とは
-
東京‐神奈川の“山越え新ルート”20日ついに開通! 新ジャイアンツ球場に接続 大規模造成で景色激変
-
前のクルマに謎の「ちょうちょマーク」が…一体どういう意味? 知らなきゃ「反則金6000円」の可能性も! 若葉マークだけでない「重要な標識」見たらどうすればいいのか
コメントの多い記事
-
ベンツで「サイゼリヤ」はおかしい? 庶民派ファミレスに高級車… 身分不相応or賢い選択? あなたはどっち派?
-
NEXCO怒りの警告「夏タイヤ車の衝突事故が起きました!」高級SUVが“無惨な状態”に…ネットでは「免許取り消せ」「タイヤ買う金あるだろ」の声も!?
-
[ノア]を実際に買うと500万円!? 新車367万円のクルマがここまで高額になる[パッケージオプション]の正体とは
-
スズキが新型「ジムニーノマド」注文停止でお詫び! 発表4日後に5万台受注!? 一方で「シエラ離れ」起きている?なぜ? 軽ジムニーは1年待ち続く
-
[スープラ]短命すぎない!? デビューからたった6年で生産終了に涙
あなたにおすすめのサービス
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
新車見積りサービス
店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!







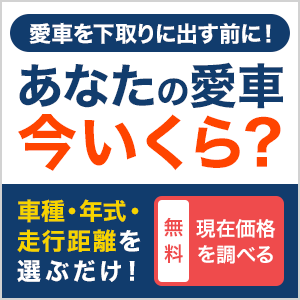
みんなのコメント
直接トヨタに取材申し込むツテは無いのか?