10月9日、今年のノーベル化学賞が吉野彰氏(名城大教授・旭化成名誉フェロー)ら3人に授与することが発表された。受賞理由は「リチウムイオン電池の開発」。
リチウムイオン電池といえば、ハイブリッド車や電動自動車とは切っても切れない技術。自動車メディアとしては、ますます吉野氏に足を向けて寝られない。
【話題の本格派軽スポーツ登場】 コペン GRスポーツ堂々発売!!! 普通のコペンと何が違う?
実は日本の研究競争力、開発競争力はその低下が叫ばれて久しい状況にあるのだが、日本が世界に誇るべき「ならでは」のクルマ、技術、魅力はまだまだたくさんある。
ここでは、そんな「ニッポンのお家芸」と呼ぶにふさわしいクルマや魅力や技術にスポットライトを当ててみたい。
※本稿は2019年9月のものに適宜修正を加えたものです
文:ベストカー編集部/写真:TOYOTA、ベストカー編集部
初出:『ベストカー』 2019年10月10日号
■【祝・ノーベル賞受賞!!!】 日本人が生みの親! 電動車に欠かせない!リチウムイオンバッテリー
(TEXT/編集部)
EVやハイブリッド車など電動車には欠かせないのがリチウムイオンバッテリー。もちろん、携帯電話やパソコンにも使われているのだが、実は日本人が発案したことはあまり知られていない。
リチウムを含有するコバルト酸リチウムを正極とし、負極に炭素材料を使うリチウムイオンバッテリーの基本概念は1985年当時、旭化成に在籍していたエンジニアの吉野彰氏によって現在の構成がほぼ完成されたのだった。翌1986年にはプロトタイプが試験生産されている。
その後、1991年にソニー・エナジー・テック社(現ソニーエナジー・デバイス社)により、リチウムイオンバッテリーは世界初の商品化にこぎつけた。
写真はトヨタの燃料電池バス「SORA」。ハイブリッド車も燃料電池自動車も、リチウムイオン電池の存在があってこそだ
1993年には旭化成と東芝による合弁会社からも商品化され、翌’94年には三洋電機からも黒鉛炭素質を負極材料に使ったリチウムイオンバッテリーが商品化された。
この功績により、吉野氏は昨年、国際科学技術財団から日本国際賞を授与され、今年に入って欧州特許庁から欧州発明家賞(非欧州部門)を受賞、また10月9日にはノーベル化学賞を受賞した。
本当におめでとうございます!!! そしてありがとうございます!!!
■これぞ日本のファミリーカー!ミニバンの充実度
(TEXT/永田恵一)
乗用車をベースに3列シートを持ついわゆるミニバン。
日本で商用車を乗用車化して3列シートを持つハイエース&キャラバン、タウンエース&バネットが「1BOXカー」と呼ばれていた1980年代前半に、アメリカでクライスラーのダッジキャラバンを先駆車に始まったジャンルである。
1990年代に入り、日本車もアメリカ輸出を目論んだエスティマやMPVからミニバン作りを開始。1990年代中盤以降ラージクラスのオデッセイやエルグランド、ミドルクラスではイプサム、コンパクトクラスでもカローラスパシオなどが登場し、徐々に市民権を得ていった。
その後もステップワゴンやストリーム、モビリオ、アルファードなどモデルは増え続け、現在日本ではコンパクトクラスのシエンタとフリード、ミドルクラスのヴォクシー3兄弟、セレナ、ステップワゴンというスライドドアを持つ5ナンバーサイズのミニバンはファミリーカーのスタンダードになっている。
本格的なオフロード走行までこなしてしまう高い悪路走破性を持ったミニバン、三菱デリカD:5も日本車ならでは!
輸入車はというと、1990年代後半から欧州車もベンツVクラス、VWシャランのほか、3列シートではないがボディサイズのわりにユッタリ乗れるルノーセニックやシトロエンクサラピカソでミニバン市場に参入。
各々よさはあったものの、使い勝手や総合力は特にミニバンの需要が多い日本では日本車に及ばず。現在も欧州ではミニバンはそれほど目立たないジャンルだ。
それに対し、現在日本のミニバンはついにレクサスからアルファードベースのLMが登場し、VIPカーの新しい形を提案。ミニバンも軽自動車と並ぶ世界に誇れる日本車の「特産品」に成長した。
■“ガラパゴス”だっていいじゃないか! 軽自動車規格
(TEXT/永田恵一)
「ガラ軽」と揶揄する層もいまだにごく一部ではいるようだが、それはとんでもない間違いだ。
何よりも全長3400mm×全幅1480mm、排気量は660ccというかぎられた規格のなかで4人が乗れ、高速道路を100km/h、120km/hで走れて、それなりの衝突安全性を確保したクルマが100万円以下から成立しているということ自体が凄すぎる。
ガラ軽と呼ばれようが、軽自動車は日本人が誇るべきクルマ。しかも背の高いモデルだけじゃなく、SUVにスポーツカーなど、バリエーションも多い
海外メーカーを見ても、2000年代初めに当時のダイムラークライスラーがピンチに陥っていた三菱自動車と資本提携を結んだ理由のひとつは「軽自動車、小型車の技術が欲しかったから」と言われているのはよくわかる。
また、軽自動車的な「10万ルピーカー(当時のレートで約20万円)」として2009年に登場したインドのタタのナノは、衝突安全性やクォリティなど問題のオンパレードだった。
現在もナノはフルモデルチェンジされて販売されているが、価格は中級グレードで約33万ルピー(日本円で約50万円)まで値上がりしている。そのため総合的、長期的に見たらナノ同様にAMTで約80万円のアルトバンのほうがずっと安く、軽自動車の凄さがより際立つ。
個々のクルマを見ても素晴らしい。まず100万円程度で自動ブレーキ付きで4人が乗れるアルト&ミライースにはじまり、スーパーハイトワゴンなら大型セダンより後席の広い足元と頭上空間を確保しているうえに、ACCは装備され、N-BOXならクルマの出来自体がコンパクトカーも真っ青だ。
また、主力となるモデル以外を見ても、ハスラーやキャストアクティバといったクロスオーバーは序の口で、大人4人とその荷物がバッチリ積める軽1BOXをはじめ、実際にないことではない過積載に耐える軽トラック、世界最小クロカンのジムニー、S660とコペンという趣味性の高いクルマまで揃う。
そんなクルマたちに安い維持費で乗れる国は日本しかなく、軽自動車は世界に誇れるジャンルと断言できる。
■取り回し抜群! 5ナンバー車
(TEXT/編集部)
1960年9月に道路運送車両法で定められた小型自動車規格がいわゆる5ナンバー車であり、全長4700mm以下、全幅1700mm以下、全高2000mm以下の排気量2000ccが該当する。
国産車もグローバルでは車幅がどんどんワイドになっているが、自動車評論家の渡辺陽一郎氏は次のように語る。
「このボディサイズをもとに日本国内の道路インフラは作られているから妥当性がある。狭い日本で道路の幅員を考えるとこれが限界のようにも思う。
国産メーカーにはこのサイズでのしっかりとしたクルマ作りをやってほしいと熱望しているんだけど……」
全幅1700mm以内の現行型プレミオ/アリオンは由緒正しい5ナンバー車の模範。2007年デビューと古くてもいいモノはいいのだ
■実燃費は他を寄せ付けない!ハイブリッド車の性能
なんといってもニッポンのお家芸を持った国産車といえば、ハイブリッド車が浮かんでくる方がほとんどではないだろうか。
下の一覧にまとめているように、トヨタを中心にコンパクトカー、セダン、SUV、ミニバン、ワゴン、軽といったように多種多様なカテゴリーにハイブリッド車、もしくはプラグインハイブリッド車が設定される。
一方、輸入車ではBMWやポルシェ、レンジローバー、ボルボなどがパワー系ユニットとしてプラグインハイブリッド車を設定しているものの、明らかにその性格は日本のプラグインハイブリッド車とは違う。
世界に誇れるハイブリッド車大国のニッポン。なかでも現在の状況を作り出したのは紛れもなくプリウス。現行型で4代目になるが、その功績は偉大
なぜ日本はここまでの“ハイブリッド王国”になったのか。自動車評論家の鈴木直也氏に聞いてみた。
* * *
ベストカーでもおなじみの燃費テストを実施すると、ハイブリッド車の実燃費はほかのパワーユニットを圧倒する。それはもうトヨタが22年も前に先陣を切って、ハイブリッド車の道を切り拓いてきた功績が何よりも大きい。
1997年にトヨタが初代プリウスを出した時って、周囲はリスキーだし、コスト割れ必至とみていた。実際、初代プリウスの最初期型なんて頻繁に亀マークは出たし、欠陥車と言われてもしかたないレベルだった。
でも、結果はコストが下がっていった2代目プリウスから爆発的に売れ始め、3代目で盤石となり、現在に至っている。それはなぜか。
もちろん、ハイブリッド車は都市部で平均速度が低速になり、信号が多い日本の道路状況に特性が合っていたこともあるのだけど、ボクは日本人の国民性が深く結びついていると考えている。
レクサスES(左)にインサイトなど、国産車ではセダンタイプもハイブリッド車のラインナップが豊富に揃っている
だって初代プリウスなんか、燃費だけを考えると購入にかかる費用を回収できないのは明白だったワケで、それでも約4万人もの日本人アーリーアダプターが最初期型を買ったのだから、新しモノ好きの日本人の国民性ありきで偉かったと思うし、これぞニッポンのお家芸だと思う。
この時に初代プリウスを購入した人のおかげで利益が上がって、それが次期型モデルの開発費に回り、マーケットが確立されていった。
今やトヨタのハイブリッド技術は基本的な特許も切れ、他社への無償供与も今春から打ち出している。THSについて技術的ノウハウやサプライヤーまですべて公開されているのにもかかわらず、フォロワーが出てこない。
それはアクアのように180万円くらいでハイブリッド車を販売して利益を出すことがいかに難しいか、トヨタと同じことをするのがいかに難しいかということの証明。
トヨタとしては「やれるもんならやってみろ」ということだと思うけど、どこも追随してこないのが現状。
■コスパの高さなら任せとけ!信頼性&経済性
続いては信頼性と経済性。いわゆるコストパフォーマンスの高さもここに含まれてくる。以前に比べれば日本車の新車価格は相対的に高くなり、今や輸入車との差もかつてほどではない。
しかし、購入してからのことを考えると、信頼性と経済性は重要なのは間違いない。
そこでクルマのコストパフォーマンスに一家言持つ渡辺陽一郎氏に聞いてみた。
* * *
日本の自動車ユーザーというのは、根本的に商品が故障することを嫌うことが背景にある。例えば、食への安全性について日本は実に厳しいけど、同じことがクルマにも求められているのだと思う。
その背景にはクルマに対する文化の違いもあるのだと個人的には思う。米国や欧州は戦前からすでにクルマが根付いていたのに対し、日本でモータリゼーションが急速に発達したのは高度経済成長期の’60年代に入ってからだから。
その後、1970年代のオイルショックを迎え、日本車は「安い」「壊れない」「燃費がいい」という3つのセールスポイントをウリに輸出されるようになり海外でも評価されるようになった。
とはいえ、愛車のメンテナンスに対するディーラー網の発達や安心感などは日本特有のもの。やはり安心感は違ってくる。
皆と同じ安心感、つまり「付和雷同」というのが日本車のコスパの源にはあるのかもしれない。
省燃費走行をゲーム感覚で行えるメーター表示。こんなところにも高い経済性を気軽に感じられる配慮が日本車の「粋」なのだ!
■痒いところに手が届く! 至れり尽くせりの快適装備
(TEXT/永田恵一)
ニッポンの誇るLクラスミニバン、アルファード/ヴェルファイア。2列目シートに一度座ってしまえばもう病みつきになること間違いなし。この快適さはどんな輸入車にだって引けを取るものではない
●カーナビ
日本車は「日本の都市部の道は非常にわかりにくい」という背景もあり、GPSができた約30年前からカーナビに力を入れていた。
当初のものは確かに50万円級の価格に見合わないものだったが、20年ほど前から実用性の向上と低価格が進み、今では当たり前の存在だ。
一方、輸入車はカーナビが付き始めたのが20年ほど前と遅く、かつ操作性にもクセがあった時期が長く、ここ数年でようやく日本車に追いついてきたというのが実情。
やはり日本人特有の几帳面さを発揮しながら、長年やってきたアドバンテージは大きい。
●自動ドア
タクシーが自動ドアなのは世界的に日本くらいなのと同様に、日本車は軽スーパーハイトワゴンやミニバンで自動ドアは当たり前の装備だ。これは日本人らしいおもてなしとお年寄りなどへの優しさの象徴だ。
一方、輸入車はというと現在日本で買えるもので自動ドアが付くのはVWシャランとベンツVクラスくらいしか浮かばない。
そもそもスライドドア車がないという事情も大きいにせよ、スライドドア車がないこと自体が使い勝手に対する国民性の大きな違いなのではないだろうか。
●後席の豪華装備
日本車は軽スーパーハイトワゴンでも後席用のモニターが付き、高級車になればマッサージ機能や電動調整など、おもてなしのオンパレードだ。
輸入車にこの手の装備が付き始めたのはここ15年ほどといったところだが、このあたりは車内を部屋のようにも考える日本車と、車内はあくまでも移動空間と考える輸入車の思想の違いと言える。
●AT
ATはアメリカと日本を中心に発展した。これはイージードライブに加え、日本は渋滞が激しいため、ATの需要が多いという背景もある。
一方、欧州車のATといえば需要が少ないのもあり、オマケ的な時代も長かった。
30年ほど前は3速ATやトラブルも珍しくなく、ラテンのクルマも含め日本車に近くなってきたのはここ数年である。
その進歩には日本のサプライヤーの貢献も多大だ。
■これも日本が独走! 燃料電池車
(TEXT/編集部)
CO2を排出しない燃料電池車(FCV)。
現在、日本には一般ユーザーが買えるMIRAIとフリート販売のみのクラリティフューエルセルの2台だが、市販されているだけでも日本は凄い!
自動車評論家の鈴木直也氏は「次世代のハイブリッド車としてFCVには個人的に期待している。
日本は集約国家だから環境的に合致するし、水素ステーションなどインフラの整備が整えば一気にブレイクスルーする可能性を秘めていると思う。
ピーク時の負荷を上げる発電所を増設するよりも、貯蔵が利く水素立国を目指すべきだよね」
2015年、ベストカー編集部に納車されたMIRAI。現在も活躍中です!
【番外コラム】輸入車が密かに採用する日本製の部品
ボルボは現在、ほとんどのモデルでトランスミッションにアイシン・エィ・ダブリュ製の8速ATを採用している
日本のサプライヤーが優秀なのは今さら言うまでもないのだが、ATの世界市場でナンバーワンのシェアを誇っているのがアイシン・エィ・ダブリュ。
BMWやボルボ、ジャガー、フォード、PSA、GMなどに採用されており、2004年のポルシェ911(997型)には同社製6速MT(※当時はアイシンAI)が採用されて話題になった。
また、電動パワステで世界シェア1位のジェイテクトは先代AクラスやBMWミニにも採用されているほか、VWはコイルばねをニッパツ、熱交換用コンデンサーをケーヒン、車体用ゴムを鬼怒川ゴム工業、ワイヤーハーネスを住友電気工業など日本製部品を続々と採用している。
◎ベストカーwebの『LINE@』がはじまりました!
(タッチ・クリックすると、スマホの方はLINEアプリが開きます)
こんな記事も読まれています
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
おすすめのニュース
-
乗りものニュース0
-
-
ベストカーWeb0
-
LE VOLANT CARSMEET WEB0
-
-
Auto Prove0
-
-
-
AUTOSPORT web0
-
AUTOCAR JAPAN1
愛車管理はマイカーページで!
登録してお得なクーポンを獲得しよう
おすすめのニュース
-
-
ベストカーWeb4
-
Auto Messe Web0
-
WEB CARTOP3
-
LE VOLANT CARSMEET WEB0
-
-
-
AUTOSPORT web0
-
AUTOSPORT web0
-
AUTOSPORT web0
-
-
-
AUTOCAR JAPAN1
-
AUTOSPORT web0
-
AUTOSPORT web0
-
-
AUTOSPORT web0
-
AUTOCAR JAPAN1
-
レスポンス0
-
Auto Messe Web8
-
日刊自動車新聞0
-
AUTOSPORT web0
-
AUTOSPORT web0
-
AUTOSPORT web0
-
AUTOSPORT web2
-
-
-
-
-
業界ニュースアクセスランキング
-
関西~中部 完全分断の「予防的通行止め」に不満爆発!? ネット上で「やり過ぎ」「国道まで止めるなよ」「迷惑」「無能な行政」の声も…国が危惧する未曾有の「大規模滞留」の悪夢とは
-
瞬く間に受注5万台強 大人気すぎて発表5日で受注停止! スズキ新型「ジムニーノマド」に対する販売店への反響とは
-
約99万円! トヨタ新“軽セダン“「ピクシス エポック」に反響多数! 全長3.4m級ボディで4人乗れる「超便利マシン」に「満足」の声! 安全性向上&寒さ対策UPの「新モデル」が話題に
-
ガソリン減税、2025年中は困難か 「国民をなめている…」「税金を上げるのは早いのに、下げるのはなぜ遅い?」の声も! 暫定税率(25.1円)に代わる財源確保が課題だと言うが
-
「名神・北陸道」夕方から大雪通行止めへ 新名神も“見込み”発表 “名阪ルート全滅”か
コメントの多い記事
-
新車250万円! “イチバン安い”ホンダ「フリード」に反響多数! ライバル「シエンタ」最安モデル比「40万円以上」に「実際買うなら装備付きがイイ」「価格差は気になる」と賛否両論!?
-
ガソリン減税、2025年中は困難か 「国民をなめている…」「税金を上げるのは早いのに、下げるのはなぜ遅い?」の声も! 暫定税率(25.1円)に代わる財源確保が課題だと言うが
-
荷主より厄介? 「荷受け担当者」の“上から目線”にドライバー不満爆発! 「忙しいから早くしろ」 現場の見えない圧力を考える
-
ガソリン“高値県”の長野で価格カルテル、公取委が商業組合に立ち入り検査[新聞ウォッチ]
-
「普通」であることの脅威。BYD「シール」に乗ったらコスパ最強で日本メーカーの将来が心配になった【JAIA】
あなたにおすすめのサービス
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
新車見積りサービス
店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!







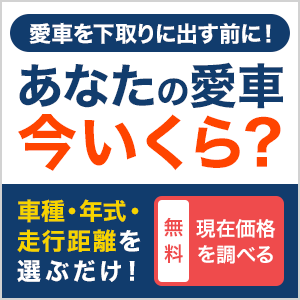
みんなのコメント
この記事にはまだコメントがありません。
この記事に対するあなたの意見や感想を投稿しませんか?