タクシーに「ハリアー」「アルファード」!? セダン車が減り「変わり種タクシー」がOKになった理由とは
■ほんの数年前までタクシーといえば「セダン」タイプが当たり前だった
日本全国津々浦々走るタクシーといえば、かつては3BOX型の古典的な「セダン」タイプのクルマが常識でした。
ところが最近では、背の高い新型タクシー専用車のほか、SUVやミニバン、ハイトワゴンもタクシーで用いられるようになりました。
ではなぜ、タクシーにさまざまなクルマが用いられるようになったのでしょうか。
【画像】都内周辺で見かけた「変わり種タクシー」を写真で見る(77枚)
日本におけるタクシーの歴史は古く、その始まりは1912年。戦後の1950年代に入り純国産車が登場するまでは、輸入車(と、そのノックダウン生産車)がタクシーの主力で、とくに日野が生産したルノー「4CV」は代表例のひとつでした。
1960年代にマイカー時代が到来し、クルマのボディバリエーションが増加しても、タクシーの車種はセダンが基本。
メーカーは、トヨタ「クラウン」や日産「セドリック」を中心に、法人顧客向けのタクシー特化モデルを開発していきました。
1990年代までは、トヨタ「コロナ」や日産「ブルーバード」、さらに三菱「ギャラン」、マツダ「ルーチェ」「カペラ」などをベースにしたタクシー用車両も存在しました。
1990年代は、タクシーの歴史に転換点を与えたクルマが数多くデビューしています。
まずは1993年、日産が小型タクシー専用の「クルー」を発売。続いて1995年には、トヨタがタクシー専用に開発した「コンフォート」および「クラウン コンフォート」、そしてほぼタクシー専用車といってよい「クラウン セダン」を登場させています。
このほか日産はセドリック(Y31型でタクシー用の「セドリック営業車」)の生産を継続。しばらくは、このメンバーが日本のタクシーのメイン車種でした。
しかしクルーは2009年、セドリックは2014年に、そしてコンフォート/クラウン コンフォートは2018年で生産を終えてしまいました。
2022年10月現在では、セダン型のタクシー専用車はもう新車で買うことはできません。
■「ミニバン」を営業車に使用する個人タクシードライバーに話を聞いてみた!
ところが2015年頃を境に、タクシー用のクルマに大きな変化が現れました。
ハッチバック型のトヨタ「プリウス」や「アクア」、トヨタ「ノア」「アルファード」などのミニバンのほか、日産「リーフ」などのEVも法人タクシーとして走るようになったのです。
また2017年10月には、背が高いスライドドアタイプのタクシー専用車、トヨタ「JPN TAXI(ジャパンタクシー)」も登場し、法人タクシーを中心に急速な普及を遂げています。
一方、個人タクシーでは基準緩和前からタクシー専用車のほかに、差別化として高級セダンが用いられることが多かったのですが、緩和以降は、さらに車種選択の自由度が加速。
東京都心では、トヨタ「ハリアー」や「RAV4」、日産「エクストレイル」、ホンダ「ヴェゼル」、BMW「X5」などのSUVや、ミニバンではトヨタ「ヴェルファイア」、日産「セレナ」、ホンダ「オデッセイ」、三菱「デリカD:5」といった幅広い車種を見ることができます。
東京都港区エリアを中心に、23区内で営業するデリカD:5の個人タクシーを営業する野村さんは次のように話します。
「コロナ禍でお客さんが減るなか、それまで使っていたセダン車をスルーされることが何度もあり、今後生き残れないと感じたことがワゴン車に変えるきっかけでした。
ディーゼルターボ車で燃費が良いこと、パートタイム4WDで雨雪時に安定していること、JPN TAXIに乗るより“得した”と思ってもらえること、さらに新型デリカD:5は誰もタクシーとして使っていないようなので、繁華街などで客待ち営業時に目立って選ばれると考えたことなどが挙げられます」
また野村さんはプライベートではキャンピングトレーラーをけん引するアウトドア派で、けん引も得意なデリカD:5は公私ともに大活躍しているそう。
野村さんは「コロナ禍真っ只中の2020年5月に導入しましたが、現在では元の売り上げ以上に回復しています」とし、ミニバンを選択してよかったといいます。
■「ミニバン」「SUV」タクシー普及のきっかけは「規制緩和」だった
このように多様な車種選択を可能としたのが、2015年6月12日に国土交通省が公布・施行した「タクシー車両の基準緩和(タクシーなど乗車定員10人以下の旅客自動車運送事業用自動車に係る以下の基準を廃止)」です。
というのも、それまでは、タクシーに使用するクルマには、以下のような基準が与えられていたのです。
—–
1.座席の寸法に関する基準
2.通路の幅と高さに関する基準
3.乗降口の大きさ、構造等に関する基準
4.緩衝装置及び座席が旅客に与える振動、前方の座席との間隙等に関する基準
—–
これらの細かな基準により、従来は車内の広さ・リアドアの大きさなどがネックとなり、タクシーの車両選択幅が狭くなっていました。
基準が緩和されたことで、前述の車種だけでなくトヨタ「シエンタ」やホンダ「フリード」などのコンパクトミニバン、トヨタ「ルーミー」などの小型ハイトワゴンも、法人タクシーとして活躍するようになりました。
特にミニバンでは、万が一の際に3列目シートから脱出する際、2列目になんらかの通路を確保するという基準があったため、タクシーに架装する際に困難が伴ったのですが、基準緩和後は、市販状態の2列目シートを使用できるようになりました。
これにより、電動スライドドアの利便性を備え、広い室内を誇るミニバンは、タクシーに用いられる機会が大幅に増加しています。
■タフで長持ちな「タクシー専用車」の優位性が失われてきた!?
ではなぜ、基準が廃止されたのでしょうか。
国土交通省の発表によれば「近年、車両の安全性の向上や運行面の安全対策が進んでいること、自家用自動車を用いて旅客を運送する自家用有償運送においても車両の安全上の問題が無いこと、その多くは国際的にも日本特有の規制であること」とあります。
この内容についての具体的な事例を、タクシーメーターやドライブレコーダー・LED表示器の販売・取り付けを行うフタバシステム株式会社の松田 隆氏に聞いてみました。
「まず、クルマ全体の性能が向上したことがあげられます。
かつてクルマ全体の性能が低く装備も少なかった時代では、旅客を乗せて走るタクシー用のクルマは、独自の設計が施され、安全性が高く作られていました。
例えば、1970年代では後席ヘッドレストを持たないクルマが多いなか、タクシーはきちんと備えていました。
現在ではどんなクルマでも安全性は十分に確保されているので、一般車との差がなくなり、タクシー専用車を作り分ける必要がなくなったのです。
そのほか、トヨタを除くと各メーカーともタクシー専用車を開発するメリットが薄くなったこと、タクシー専用セダンの生産自体も終了していること、セダンを選びたくても車種が減少していることなどもあげられます」
さらに松田氏に「ミニバンのタクシーは乗降性に優れているが、地上高の高いSUVではメリットがあるのかどうか?」という素朴な疑問も尋ねてみました。
「正直なところ、タクシーとしての乗降性はあまりよくありません。大きく足をあげないと、乗車が難しいからです。
しかしSUVは車内が広く積載性も高く、操縦性が良いというメリットもあります。
SUVを使う個人タクシーオーナーは、実用性や運転の楽しさという好みで、SUVを選んでいる場合が多いのではないでしょうか」
街の景色を彩るタクシー。今後も変わり種の車両がまだまだたくさん登場するかもしれません。
こんな記事も読まれています
この記事に出てきたクルマ
全国の日産 クルー中古車一覧 (4件)
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
おすすめのニュース
-
レスポンス0
-
-
-
-
-
WEBヤングマシン0
-
-
-
ベストカーWeb1
-
Auto Messe Web6
愛車管理はマイカーページで!
登録してお得なクーポンを獲得しよう
おすすめのニュース
-
-
-
-
-
ベストカーWeb27
-
-
-
-
-
Auto Prove3
-
Auto Prove0
-
-
-
-
-
ベストカーWeb26
-
-
バイクのニュース3
-
乗りものニュース14
-
motorsport.com 日本版1
-
レスポンス14
-
カー・アンド・ドライバー3
-
-
乗りものニュース21
-
-
WEBヤングマシン0
-
-
-
ベストカーWeb0
-
WEB CARTOP8
業界ニュースアクセスランキング
-
日英伊の次世代戦闘機←南アジアの大国「仲間に入れて!」ロシア製戦闘機いっぱい持つ国の思惑とは?
-
格闘家の皇治選手、高級外車を乗り捨て!? 当て逃げ容疑で書類送検! 本人謝罪も批判相次ぐ
-
海自の艦艇に搭載された「未来の大砲」を激写!SFの世界が現実に!? 戦闘を一変させる革新的な兵器
-
満タン後「継ぎ足し給油」は「絶対NG」! 禁止の理由は? 「今までやってた」「知らなかった…」の声も!? “習慣的”にやりがちな「危険すぎる行為」 どんなリスクがあるのか
-
「100年乗っても大丈夫!」なぜB-52はこれほど長寿機に? 納得の理由とは もうすで70年も現役!
あなたにおすすめのサービス
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
新車見積りサービス
店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!







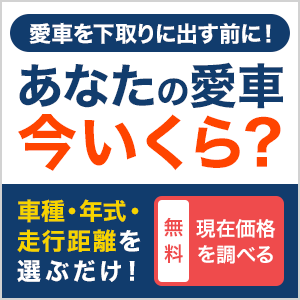
みんなのコメント