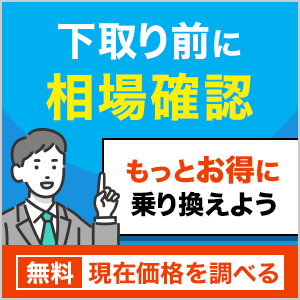- carview!
- 新車カタログ
- ランチア(LANCIA)
- テーマ
- みんなの質問(解決済み)
- 久しぶりの質問です。 詳しい方がいらっしゃ...
ランチア テーマ のみんなの質問
もーもーさん
2023.10.24 21:05
- 回答数:
- 5
- 閲覧数:
- 156
久しぶりの質問です。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
先日、職場の車好きな先輩と車のエンジンについて話しをしました。
「今のガソリンエンジンは2035年までに生産を終わらせるって言ってたね〜」から始まり、今後、ハイブリッドがさらに進化してよりEVに近づくのか、エンジンの発電アシストなしでも超長距離走行ができるバッテリーを積んだEVが主流となるのか、それとも、燃料電池車がメーカー努力や国の支援でもっと安くなって広く普及するのか・・・等々。
「今の無段階シフトだと、おれはマニュアル好きだから、車を運転する楽しみが無くなるな〜」と言う先輩に「いやいや、水素エンジンがあるじゃないですか」と私が言うと「お〜水素エンジンか。あれは今どうなってるの?」というので調べてみると、トヨタを筆頭に開発が進められていて、進化し続けていることを知り、とてもワクワクしています。
というのも、私は学生の頃···もう35年も前の話しですが、その頃から水素エンジンには興味がありました。
そんな中、「自動車工学概論」という授業で「〇〇年後に石油資源の枯渇問題が起きた場合、あなたが考える『自動車のあるべき姿』は」というテーマで小論文を書くという課題があったんです。その頃は二酸化炭素よりも石油資源枯渇のほうが将来的に起こりうる問題として取り上げられていたんです。時代を感じますね。
その時私が出した論文は「水素エンジン」をテーマにしたものでした。
①今のガソリンエンジンを改良して、水素を燃料として動くエンジンを作る。
②燃料となる水素は、タンクに蓄えた水をエンジンルーム内に設けた電解室で分解・生成したものを使用する。
③燃焼して生成された水蒸気は排気管を通って冷却室で液化してタンクに戻して再利用 → 石油資源枯渇問題に対応できるだけでなく、半永久的に燃料補給が不要となる・・・っていう内容です。
クラス42人中、ほとんどが電気自動車と答えている中で、水素エンジンと答えたのは私を含めて3人だけだったんですが、「タンクの水をその場で電気分解して燃料とする。さらに生成した水を再利用する」っていうアイデアが教授にはウケたみたいで、クラスで「大賞」をとり、学校の新聞に載せてもらったのを憶えています。
かなり前置きが長くなりましたが、ここで質問です。
実際のところ、
①水素の供給方法として、上記はどうなんでしょう? 難しいのかな?
②燃焼した後の水を回収して再利用することも難しいのでしょうか?
③それとも、とっくに考えついている方法で、すでにテストされて、成果がないと没になったのでしょうか?
教えていただけたら嬉しいです。
うっしぃ
ベストアンサーに選ばれた回答
Takaさん
2023.10.27 12:02
水素エンジンは水素を燃焼させてエネルギーAを取り出し車の走行に活用する。
その際に燃えカスとして水蒸気を排出する。
水蒸気を水にして電気分解して水素を生成する。
このときエネルギーBが必要。
エンジンで使用した水素と同量の水素を電気分解して生成するとすると、
効率100%と仮定しても A=B なのです。
だからエンジンで取り出したエネルギーを走行に使ってしまうと電気分解に回せないのです。
少しだけBに回しても、元の水素の量を生成できないのです。
もし出来たとして永久に回せれば「永久機関」になりますが、永久機関は出来ないのです。
質問者からのお礼コメント
2023.10.27 14:22
皆さん、ご回答ありがとうございました。
エネルギー保存則とエネルギー変換効率で考えたら、実現できるわけないですよね。今さらながら、目から鱗でした。
その他の回答 (4件)
-
tak********さん
2023.10.25 02:46
質問に対する回答ではないので恐縮ですが、石油はそもそも枯渇しないかもしれません。
近年の実験では、惑星の内部に大量に存在する星間有機物を加熱したところ、化学組成がほぼ同じ石油状の物質が生成されることがわかっています(下部資料①)。旧ソ連では石油の無機起源説を支持する論文がたくさんあり、深度採掘によってこういった説が裏付けられています(下部資料②)。これらの事実をさらに証明するように、近年の日本でも、高温高圧下の地中に水や二酸化炭素を注入して石油を増産できることが実証されています(下部資料③)。実際の油井においても、紀元前から採掘の記録があるカスピ海沿岸のバクー油田(現アゼルバイジャン付近)では、1960年頃に枯渇したと思われた油田から、再度、石油が染み出し、活況となっている例があります。したがって、化石燃料という用語やピークオイル説、有機起源説は、おそらく資本家が広めたプロパガンダであろうと思われます(下部資料④)。
おそらく、蛇口をひねればいくらでも湧いてくるわけではないものの、生成速度を上回る採掘をしなければ、ほぼ永久に枯渇することはないのかもしれません。石油掘削技術におけるシェール革命などといったものも、一向に枯渇することがない埋蔵量という嘘を更に補完するために後付けで考案された、大きな嘘ではないかと思われます。こういった調査の結果は、石油に関連した従来の有機起源説を覆し、一国どころか世界のエネルギー政策・地政学の大転換を促すものであるため、もっと議論が進んで然るべきだと思いますが、そういった動きがないのは理解に苦しみます。
横やり申し訳ありません、参考までに。
①星間有機物が地球の水の起源に
北海道大学、JAMSTEC、東京大学大学院・理学部理学研究科、岡山大学、九州大学ほか、共同研究
プレスリリース 2020/05/12
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id724.html
②石油の無機起源説に関する最近の進展
石油技術協会誌 第80巻、第4号、平成27年7月、275-282項
https://www.jstage.jst.go.jp/article/japt/80/4/80_275/_pdf
③炭酸ガス(CO2)圧入攻法
二酸化炭素排出抑制に貢献し、石油回収率を高める「炭酸ガス(CO2)圧入攻法」
https://archive.md/HZW2K
④化石燃料の真実〜THE ORIGINS OF OIL
https://www.bitchute.com/video/XyUTVddqYID7/
-
sti********さん
2023.10.24 21:44
①水素の液化温度は-253度ですからね~
気軽に運搬して、今のガソリンスタンドみたいに気軽に貯蔵出来ません!
現在はトラックに積んだ移動式水素ステーションや水素基地から近い所に水素ステーションがある位で、今のガソリンスタンドみたいに民間で-253度に保てる貯蔵タンク設備を設置するのはお金が掛かります。
②水を電気分解するのに電気エネルギー消費するのでリサイクル効率が悪いです。
③そもそもそれが可能なら、液化水素タンクを積む必要性がなくなります。
-
tie********さん
2023.10.24 21:36
バッテリーで蓄えた電力で水素を作ると言う所のエネルギー効率が悪すぎて実用化出来ないでしょうね
バッテリがあるならそのままEVとして走らせた方が良い
バッテリーで作る水素で走る距離より
バッテリーの電力をそのままモーター回して走った方が長く走れますね
ですから意味が無い
これって水タンクの水をモーターポンプでくみ上げて水車を回して水車に着いた発電機でバッテリーを充電して
そのバッテリーでモーターポンプを回すみたいな話で
これが出来たら永久機関です
エネルギー変換のロスの分だけどんどんバッテリーが減っていくので無理な話
-
dai********さん
2023.10.24 21:35
工学にはくわしくないですが、
最初に電気分解するのに電気が必要、
電気分解しながら走行して再循環させる。
可能でしょうが、大規模な装置になり小型乗用車に搭載できる
大きさになるには相当な時間がかかるか無理だと思います。
また、重量と体積が増えればそれだけエネルギーが必要となり
本末転倒になる事も。
「自動車」カテゴリとデータを共有しています。
あわせて知りたい
-
EVの普及 私の地元から100kmほど離れた村にいくとEVが多い。 たぶん、近所にガソリンスタンドがないから。 。 田舎はガソリンスタンドがない、戸建が多いから自宅庭に置けて充電が出来る。 つま
2024.10.24
解決済み- 回答数:
- 15
- 閲覧数:
- 154
ベストアンサー:面白いテーマですね 私はテスラを所有していますのでEVに理解あると思っています 基本的に内燃車とEVのエネルギーの充填方法が違う事を理解しないと頑固に充電時間によるEV批判は無くならないと考えます 短時間に満タンにする事が正義みたいに思う人と自宅で毎朝満タンが便利だと思う人の間には結構思想的に隔たりがありますね これはEVの自宅充電は未知なので理解されていないと思います また自宅近辺のシ...
-
2024.10.24
解決済み- 回答数:
- 2
- 閲覧数:
- 19
- 画像あり
ベストアンサー:Kia K8 GL3 2021年2月17日、韓国で発表(販売は同年4月8日)。従来販売されていたK7の後継車種として登場。最新のCIを与えられた最初の車種でもある。 エクステリアは従来からのアイデンティティである「タイガーノーズグリル」に加え、「自然」にインスパイアされたキアの最新デザイン哲学である「OPPOSITES UNITED」に基づいてデザインされている[1]。また、車名の数字か...
-
卒論について。 経営学部です。何もテーマが見つからないので、適当に書きやすそうなテーマを選びました。「自動車メーカーの売上の差が生じる理由」というテーマです。売上やシェアは国内でトヨタが圧倒的な...
2024.10.16
回答受付終了- 回答数:
- 1
- 閲覧数:
- 51
-
- 中古車本体価格
-
198.0 万円 〜 350.0 万円
-
- 新車価格(税込)
-
413.0 万円 〜 838.0 万円
テーマを見た人はこんな車と比較しています
ランチア テーマ についてもっと詳しく
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。
ログイン
ランチア テーマのみんなの質問ランキング
-
ボルボは中国製ですか? 中国企業に買収されましたけど、資本が中華なだけで日本に来てるボルボ車は中国製ではないといわれてますよね。 でも新しい型のボルボですとリアガラスのところに「made in...
2012.1.13
解決済み- 回答数:
- 3
- 閲覧数:
- 47,960
-
社会人が自動車学校。どれくらいで免許がとれますか? アラサー女性です。自動車免許を持っていないのですが とったほうがいいかなと思うようになりました。 毎日フルタイムで働いているので、あいてるの...
2014.4.4
解決済み- 回答数:
- 4
- 閲覧数:
- 22,956
-
皆さんわざわざ普通免許を取得したのに、なぜAT車を買おうとするのでしょうか? 私は、今年免許を取得しましたが、せっかく苦労して普通免許を取得したので (正直、最初の頃は、限定に鞍替えしようとしま...
2014.8.31
解決済み- 回答数:
- 34
- 閲覧数:
- 559
-
運転が下手すぎて辛いです。 私は今自動車学校に通っています。まだ第1段階の2回目なのですが、ほんとに下手でもう少しで補習になりそうでした。 親には補習は絶対だめと言われています。私も補習になりた...
2022.2.4
解決済み- 回答数:
- 28
- 閲覧数:
- 3,669
-
主人ががレクサスを買おうとしているのをどうしても阻止したいです。 うちは古くからのお屋敷で、庭園があり、お義母さんは和服で過ごすような家です。 主人は車好きで、色々と車を買うんですが、テーマは和...
2024.9.9
回答受付終了- 回答数:
- 19
- 閲覧数:
- 564
あなたにおすすめのサービス
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!