新型車のオートライト義務化から1年! オートライトのメリットとデメリットとは
2016年10月に、国土交通省の保安基準の改正によって、オートライトシステム(以下オートライト)装着の義務化が発表され、新型車のオートライト義務化が2020年4月1日から始まった。
早くも新型車のオートライト義務化から1年が経つが、都内を走っていると特に西日で前が見づらくなる薄暮れ時に対向車のライトが眩しいと感じることが多くなった気がする。
燃費基準達成車と低排出ガス車のステッカーなぜ廃止? クルマに貼るステッカーはどんなものがあるのか?
最近ではコペンやアルファードなどが一部改良でオートライト義務化対応をするなど、2021年10月から始まる継続生産車の義務化への動きもみられる。
オートライトの機能は、周囲の明るさに合わせてライトの点灯/消灯を自動的に行ってくれるが、ここで改めてオートライトのメリット、デメリットについてモータージャーナリストの岩尾信哉氏が解説する。
文/岩尾信哉
写真/ベストカーweb編集部 トヨタ ダイハツ
【画像ギャラリー】LED化やオートハイビーム……最近のクルマにみるヘッドライトの進化
近づく全新車のオートライト義務化
新型車は2020年4月以降、継続生産車では2021年10月からオートライトが義務化される
ダイハツは2021年4月7日、コペンに一部改良を実施し、全車にオートライトを標準装備した
内閣府の調査によれば薄暮時は昼間と比べて、自動車と歩行者による事故率が4倍も上回るとされ、こうした背景から2016年10月から「道路運送車両の保安基準」を一部改定して、新車販売される車両の「前照灯の自動点灯機能」、すなわちオートライトが義務付けされることになり、あわせて日中点灯し続けるデイタイムランニングランプの装着も認可されることになった。
新型車は2020年4月以降、継続生産車(5ナンバー、3ナンバー)は2021年10月から搭載が義務化され、定員11人以上の乗用車(バス)や車両総重量3.5トン超のトラックについては、新型車が2021年4月、継続生産車が2023年10月となっている。
従来から日本では独自の立場で、夕暮れから夜間にかけての安全性向上のためにオートライトの義務化が検討されてきた経緯があり、合わせてデイタイムランニングランプは昼間の他車や歩行者などからの視認性向上を理由に解禁されたことになる。
LEDランプの採用などによってヘッドライトが多機能化するなかで、この保安基準の変更について改めて整理してみよう。ちなみに、保安基準変更のポイントである「オートライトの義務化」は、正確には「すれ違い用前照灯の自動点灯に関する基準の導入」ということになる。
内容をまとめて紹介すると、「すれ違い用前照灯(ロービーム)について、以下の要件に従って、周囲の明るさ(照度)に応じ、自動的に点灯及び消灯する機能を有さなければならないこととします」とあり、「自動点灯に係る機能については、「手動による解除ができないものでなければならない」ということだ。
これまでは基準がなくオートライトの設定ひとつをとってもメーカー間に違いがあった。できるだけ早く点灯する早期点灯派の日産、BMW、メルセデスベンツ。一方、トヨタ、ホンダ、マツダ、三菱の4社はドライバーの感覚にあわせて多くのドライバーが暗いと感じるタイミングにあわせて点灯
オートライトとして要求される機能としては、ドライバーは常にヘッドライトを点灯して走行しつつ、条件として設定されている周囲の明るさが1000ルクス未満になると自動で点灯することだ。
なお1000ルクスを下回る時間帯とは、屋外では日没とともに周囲が暗くなり、無灯火の車両がブレーキを踏むとブレーキランプが目につき始めるタイミングといえる。
誤解してはいけないのは、2021年10月に完全にオートライト機能が義務化されるのは、あくまで継続生産車の新車に対してであり、販売済みの車両にはこれまで通り、警察庁などが昼間でのヘッドライトの点灯を推奨している。
加えて、輸入車に見られるデイタイムランニングランプは、日中も暗い北欧などを含むEU域で2011年以降に採用および義務化された経緯があり(夜間は使用しないという前提)、デイタイムランニングランプとしての機能の設定がすでに進んでいるので、ヘッドライトがオートライト機能を備えていなくても、デイタイムランニングランプを昼間の点灯機能として使うなど、各ブランドで対応している。
機能で変わる呼称
写真はホンダ車のウィンカーレバー。「AUTO」のポジションに合わせると、自動で前照灯の点消灯が行われ、現在の国産車は同様の仕組みを用いているオートライトがほとんどだ
ここからはそれぞれのヘッドライト(前照灯)の機能を改めて解説しておこう。確認しておくべきなのは、ハイビームが通常使用する「走行前照灯」、ロービームが「すれ違い時前照灯」と定義されていることだ。
●デイタイムランニングランプ(昼間走行灯:DRL)
自動車メーカーによっては、デイタイムランニングランプ、デイタイムランニングライト、デイライトなどと呼び名が定まっていないのは、先の保安基準の変更で装着が認められるまでは、日本メーカーではアクセサリー類として扱われるなど、機能が正確に認知されていなかった要因もあるのだろう。
保安基準では「昼間に車両“前方”からの視認性を向上させるもの」とされ、フロント部分に装着される。テールランプやナンバー灯など、リア部分の灯火類は同時に点灯せず、メーターやナビ画面など室内の光量も“昼間設定”が維持される。
DRLを装着した車両では、昼間に走行中では、ライトスイッチをAUTOに設定することで、昼間はDRLが点灯、日没やトンネルなどにより暗くなるとヘッドライトが自動的に点灯といった作動となる。
●車幅灯(フロントポジションランプ)
車両のフロント左右両側に備わる灯火類として、夜間に自車位置を周囲に認知させるために車幅を示す機能目的で点灯する。DRLと異なり、意図的にオン/オフを切り替えられる。
●スモールランプ
車両に保安装備として設定されている幾つかの灯火類を組み合わせて点灯させる機能。実は保安基準には未記載というのが面白く、一般的にスモールランプのスイッチをオンにすると、車幅灯とともに尾灯(テールランプ:夜間に車両の存在を後方に示すための灯火器)なども点灯するので、こうした灯火類の総称ともいえる。これも任意でオン/オフの切り替えが可能であり、点灯時にはモニター画面やメーターなどの表示も夜間用に調光される。
スイッチング機能の各メーカーの対応
写真は新型VWゴルフのもの。欧州車は、ライトのオフスイッチがなく、手動で消灯できない車種も多いため、「ライトの切り方がわからない」と戸惑うユーザーも
2021年10月からの継続生産車へのオートライト機能義務化に関して、日本メーカーの対応の動きとしては、価格が抑えられたベースグレードへのオートライトの設定が進むことが予想されるなど、安全性向上のきっかけとしては喜ばしい。
たとえば最近の個別車種への各日本メーカーの対応を見ると、トヨタパッソ(ダイハツブーン)は去る4月1日にトヨタが“コンライト”、ライト自動点灯・消灯システム、すなわちオートライトを全車標準装備するなど、継続生産車への対応が進んでいるようだ。
いっぽうで、日産の場合は、軽自動車のルークスと三菱eKスペース/eKスペースクロスの3モデル(2020年3月発売)に採用されているが、見た目にはオフ機能があって4段階のものがあっても、走り出せば自動点灯するパターンとされている。
続く2020年6月に発売されたコンパクトSUVのキックスでは上(奥)から○(消灯)、スモール、ライトオン、AUTOが設定となるなど、見た目の統一は図られていないようだ。ちなみに、2020年4月までに新車発表を済ませていれば、2021年10月の継続生産車への対応時期まで時間が稼げるということでもありそうだ。
続いてオートライト義務化への対応を数多くの車種を抱えるトヨタで見ていくとしよう。トヨタではオートライトという表記はなく、ポジションとしての「AUTO」で説明している。
トヨタカムリのオートマチックハイビームの使い方(2020年8月時点での取扱説明書)
ちなみに取扱説明書の文章では、DRLについては一部変更の前後で共通ながら「日中での走行時、自車が他の運転者から見やすくなるように、ハイブリッドシステム始動後、パーキングブレーキを解除して、ランプスイッチをAUTOにすると、LEDデイライトが自動で点灯します。(車幅灯より明るく点灯します。)」とある。
2021年2月の一部改良時、カムリの取扱説明書
いっぽう、2021年2月の一部改良では点灯状態での周囲の明暗の違いでDRLとヘッドライト(表記はランプ)の作動の違いを明記している。
ヤリスの新型車への対応としては(2020年2月発売)、ランプスイッチの機能の説明で「消灯のしかた」項目が設定されている
ヤリスの取扱説明書
ヤリスのウインカーレバー
いくつか他社の設定を確認しておくと、ホンダは統一が図られているようで、ホンダe(2020年10月発売)など、新車の自動点灯義務化に対応したライトスイッチは上からOFF、スモール、AUTOとなり、デフォルトとしてAUTOの位置に戻る。スズキハスラー(2020年1月発売)ではライトオン、AUTO、スモール/オフの3段階設定などとなっている。
オートライトのメリットとデメリット
オートライトの機能を含めた使いやすさを考えてみると、ハイビーム、ロービーム、DRLなどの使い分けに関しては、オートライト機能によって単純化されるのは点け忘れ防止などの点ではメリットといえるが、使い勝手のうえでは微妙なデメリットが生まれている。
事故が起きやすい時間帯といわれている、日没前後の夕暮れ時などで安全面での効果は車両の周囲ではあるはずだが、オートライトではいわゆる「思いやり消灯」がしにくいというのがデメリットといえる。
なによりLEDランプの普及でヘッドライトがまぶしく感じる機会が多くなったのは間違いなく、LED仕様のヘッドライトは昼間では対向車はもとより、自車の前方車両の室内ミラーに映ると反射光が気になってしまうケースが増えてしまった。
ドライバーと歩行者、昼間と夜間、それぞれで認知度が高まったことはよいととしても、消灯に要する時間に差があるなど、各メーカーで操作や作動の設定(マナーというべきか)などを、機能面を煮詰めていく余地がまだあるはずだ。
【画像ギャラリー】LED化やオートハイビーム……最近のクルマにみるヘッドライトの進化
こんな記事も読まれています
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
おすすめのニュース
-
AUTOSPORT web0
-
乗りものニュース1
-
-
AUTOSPORT web0
-
-
-
-
Merkmal2
-
THE EV TIMES22
-
AUTOCAR JAPAN0
愛車管理はマイカーページで!
登録してお得なクーポンを獲得しよう
おすすめのニュース
-
AUTOCAR JAPAN0
-
AUTOSPORT web1
-
-
-
motorsport.com 日本版0
-
motorsport.com 日本版0
-
AUTOCAR JAPAN0
-
AUTOCAR JAPAN0
-
-
-
-
motorsport.com 日本版0
-
AUTOSPORT web0
-
ベストカーWeb0
-
-
-
-
-
-
motorsport.com 日本版1
-
-
-
motorsport.com 日本版2
-
AUTOSPORT web0
-
-
乗りものニュース3
-
AUTOSPORT web0
-
-
motorsport.com 日本版1
-
業界ニュースアクセスランキング
-
「世界で一番嫌い」 マツコ・デラックスはなぜ「二子玉川」を拒絶するのか? 理想化された街に漂う“らしさ”の呪縛、再開発と多様性の葛藤を考える
-
「車中泊トラブル」なぜ後を絶たない…!? 「ご遠慮ください」案内を無視する人も… 背景にはキャンプと「混同」も? 現状はどうなっている?
-
来年から「クルマの税金」が変わる!? 今年も納税時期迫るが…今後は負担減るの? 自動車諸税、ついに抜本改革なるか 「環境性能と公平性」を軸に
-
軽自動車を買おう! でも「ターボ」って必要ですか? 街乗りは「安いノンターボ車」で良くないですか? だけど「パワー」は欲しい… 「新生活の軽選び」で考えるべきこととは
-
本当かよ!? 空自F-2後継の新戦闘機計画「GCAP」にオーストラリアも参加←現地の専門家に聞いてみた
コメントの多い記事
-
「世界で一番嫌い」 マツコ・デラックスはなぜ「二子玉川」を拒絶するのか? 理想化された街に漂う“らしさ”の呪縛、再開発と多様性の葛藤を考える
-
中国にはBYD以外にも多数のEVメーカーが存在! BYDの成功で日本に押し寄せることはある?
-
来年から「クルマの税金」が変わる!? 今年も納税時期迫るが…今後は負担減るの? 自動車諸税、ついに抜本改革なるか 「環境性能と公平性」を軸に
-
昭和の自動車教習所、なぜ教官は「ヤンキー」風だったのか? しかも指導は「鬼教官」スタイル! 今じゃありえない? その裏に隠された激動史を辿る
-
給油時に「空気圧高くしますか?」素直に従うべき? ガソスタ定番セリフの「意図」とは 本当に「空気圧高め」する必要はあるのか
あなたにおすすめのサービス
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
新車見積りサービス
店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!







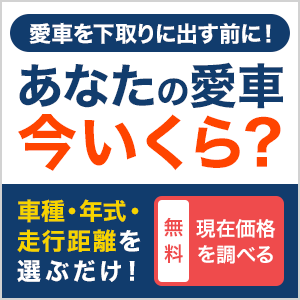
みんなのコメント
完全に日が暮れているのに無灯火の車、対向車が来ても前に車が居てもハイビーム。
話しにならない。
技術が進歩して便利になるとドライバーの質が下がるのはなんとかならないものか?