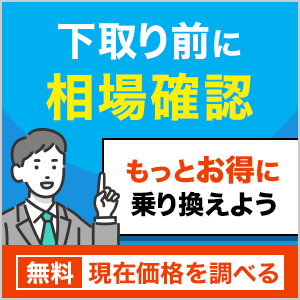- carview!
- 新車カタログ
- スバル(SUBARU)
- スバル360
- みんなの質問(解決済み)
- 昔のスバル360のサスペンションは何故ふわふ...
スバル スバル360 のみんなの質問
知恵袋ユーザーさん
2023.5.13 16:29
- 回答数:
- 5
- 閲覧数:
- 54
昔のスバル360のサスペンションは何故ふわふわだったんですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
知恵袋ユーザーさん
2023.5.13 17:37
スバル360の懸架装置は前後ともトレーリングアームに横置きトーションバーとセンターコイルスプリングを組み合わせた、きわめて軽量・省スペースでサスペンションストロークの大きな4輪独立懸架構造である。
ポルシェタイプのリアサスペンションはスイングアクスル式に分類される。
自動車用トーションバーは、当時の日本に製造しているメーカーがなく、富士重工は大手ばねメーカーの日本発条に新たに開発・製造を要請した。
当初の試作品は削り出し加工で作られ、1台分4本が合計4万円にもなる法外さで、車全体の予定価格の1割近くに達した。
しかもメーカーの経験不足もあり、歩留まり良く製品を作れず、試験中に破損することもしばしばであった。
その後、品質面で改善が進められ、また鍛造での製作が可能になって量産体制が整ったことで、発売時点の価格は4本で数千円レベルに引き下げられた。
このトーションバーと連結されて車輪を支えるトレーリングアームも、軽量化と強度確保という相反する課題のため破損続出に悩まされ、高価だが強度の高いクローム・モリブデン鋼を材質に使うことで解決している。
サスペンション方式に前後ともトレーリングアームを採用した背景には、やはり横置きトーションバー・トレーリングアームレイアウトのフォルクスワーゲン・ビートルの影響もかいま見ることができるが、特にフロントサスペンションのコンパクト化という点では普通小型車サイズのビートルに比して格別に徹底されたものがあった(ビートルはトーションバーを二段としたポルシェ式のダブル・トレーリングアームだが、スバルはより簡潔なシングル・トレーリングアームである)。
これは後述のとおり、フロントシートのレッグスペース確保に絶大な効果を発揮した。
超軽量車の開発における問題点の一つは、積空差が著しく大きいことである。運転者1名のみの場合と、4人フル乗車の場合とで、車両の総重量には150 kg以上の差が生じ、空車重量350 kgを計画している自動車には大変な重量差である。
このような条件で、フル乗車時でも最低限のロード・クリアランスを保障し、サスペンションストロークも確保しながら操縦性と乗り心地を常に良好とすることには、非常な困難があった。
対策として当初考えられたのは、トーションバーの他に補助スプリングとして車体前後中央にエンジン動力で油圧を得て作動する補助スプリングを装備することだった。
シトロエンが同時期に実用化していたハイドロニューマチックシステムに近い発想であったが、試験では油圧スプリングユニットのオイル漏れを解決できず、油圧ポンプについても搭載スペース難やこれを駆動するだけのエンジン出力余裕の難など多くの制約があり、コストや開発期間も厳しかったことから、結局実用化は諦められた。
代案として、油圧スプリングを装備予定だった中央位置に補助のコイルスプリング1基を装備することになった。
トーションバーに一定以上の大きな荷重がかかれば基部に接続するこのセンタースプリングが働き、ダンピング効果が生じるわけである。これによって実用上の基本的問題はほぼ解決された。
スイングアクスル式サスペンションでは避けて通れない問題として、リアのジャッキアップ現象があるが、後にスバルでも横転事故の事例が多発するようになった。当初、前後輪それぞれにリンクされていたセンタースプリングは、横転対策としてリアサスペンションの剛性を確保するため、後部の接続を止め、後輪はトーションバーのみの支持に変更された。
同時に後輪用トーションバーは径を太くし、対ロール抗性が高められた。
またダンパーについては、当初コストの制約から原始的なフリクションダンパーを用いざるを得なかった。
これでは定量的なダンパーとしての効果には不満もあり、後に油圧ダンパーの価格低下でそちらに移行した。
当時の日本の自動車業界では、小型車の場合、乗り心地と悪路への耐久性・踏破性はおよそ相反するものと考えられていただけに、悪路をフワフワといなして快適に走行できるスバル・360のサスペンションは感嘆をもって迎えられ、愛好者の間では「スバル・クッション」と称された。
もっともスバルの場合、やはりタイヤの小ささ故にロードクリアランスの限界はあり、スプリングが最も圧縮される4人定員乗車時に悪路の深いわだちにさしかかると、時としてそのままでは乗り越えきれない事例も生じた。
この場合、対処は至って単純で、ドライバー以外の1人か2人をいったん路傍に下車させるだけである。
即座にスプリングが伸びて車高が上がる。
そして「お荷物」の下車要員たちは、道の行く手でわだちが浅くなるところまで、スバルの後を歩いていくのだった。
1960年代、モータリゼーション黎明期の田舎道や山道で時折見られた、牧歌的情景である。
その他の回答 (4件)
-
がんばれニッポン!さん
2023.5.13 17:39
そのふわふわは「スバル・クッション」として有名でした。
当時の業界で小型車の場合に
乗り心地と悪路への耐久性・踏破性は
およそ相反するものと考えられていました。
また1960年前後の道路事情ではふわふわじゃないと辛かったと思います。
ただやっぱりふわふわ過ぎたのでしょう、当初はコストの制約からフリクションダンパーを用いざるを得なかったのだと思います。
これでは定量的なダンパーとしての効果には不満もあり
後に油圧ダンパーの価格低下でそちらに移行した様です。
面白い話が有ります
スバル360のタイヤの小ささからロードクリアランスの限界があり
4人乗りで轍に差し掛かると乗り越えられなかったそうです
その際は同乗者は降りてスプリングを伸ばして車の後ろを歩いていたそうです
-
cat*********さん
2023.5.13 17:02
その当時の道路状況に有ったチューニングだったのかと思います。
舗装率は低く路面の凹凸が多かった事から、現在のような速度は出せない事から柔らかいバネが適していたのだと思います。
-
ptm********さん
2023.5.13 16:37
サス=ばね、で、ショックアブソーバーの概念がまだ時代的に
余り無かったのかと思います。
-
sil********さん
2023.5.13 16:31
当時の自動車技術が未熟で、小型車のサスペンションに適した技術がまだ開発されてなかったためです。
また、スバル360は軽量で、サスペンション設計も簡素化されていたため、振動吸収性能が不足していたことも影響してます。
「自動車」カテゴリとデータを共有しています。
あわせて知りたい
-
「スバル360」同年代、その前後の車オーナーの方に質問ですが、スバル360で採用されてる「合わせホイール」(チューブ‶イン”タイヤ)でタイヤ交換したときに「ホイールバランス」作業はできましたか? 「合
2024.11.22
回答受付中- 回答数:
- 4
- 閲覧数:
- 46
-
工具に詳しい人教えてください。 画像はスバル360のホイール です。見えている 半球状のボルトの頭を 抑え付けて反対側のナットを 緩めたいのですが ロッキングプライヤーが いいのでしょうか? も...
2024.11.21
解決済み- 回答数:
- 1
- 閲覧数:
- 27
- 画像あり
ベストアンサー:合わせホイールのボルトはスチール棚を組む時の組立用ボルトみたいにボルト頭の下が四角になっていてボルト頭を押さえなくてもナットは緩むかと。押さえないと緩まない場合はバイスプライヤーですね。カーブタイプあごの標準式バイスプライヤーでいいのではないかと思いますよ。
-
- 中古車本体価格
-
78.0 万円 〜 256.0 万円
-
- 新車価格(税込)
-
-
スバル360を見た人はこんな車と比較しています
スバル スバル360 についてもっと詳しく
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。
ログイン
スバル スバル360のみんなの質問ランキング
-
軽自動車を改造して、ワーゲン風にしてる人って、恥ずかしくありませんか? 私は、本物のワーゲンバスに乗っていますが、すれ違いざま手を振られたり、しつこい人は、ついてきたりします。勘弁してください。
2015.3.17
解決済み- 回答数:
- 7
- 閲覧数:
- 42,421
-
最近360cc時代の軽自動車(2スト)に興味があるのですが、実際のところ使い勝手はどうなんでしょう? あくまで超小排気量の旧車なので、相応のものであることは想像がつきますが… ・実際に高速道路で...
2011.11.13
解決済み- 回答数:
- 2
- 閲覧数:
- 16,380
-
スバル(富士重工)はもうオリジナルの軽自動車を出さないのでしょうか? 本気を出しすぎて赤字で生産中止とも聞きますがなんか悲しいです。もう一度、4気筒+SCで速い軽、乗り心地のいい軽を作ってほしい...
2013.9.22
解決済み- 回答数:
- 11
- 閲覧数:
- 15,791
-
旧車の中で117クーペHM(1600ccDOHC)ってどうしてこんなに安いのでしょうか? 質問内容はタイトルの文章に要約されているのですが、それにしても117クーペHMは安いです。 なんせ200...
2012.2.5
解決済み- 回答数:
- 5
- 閲覧数:
- 10,341
-
4人乗りの出来て現在購入可能な一番小さなクルマは何でしょうか。 嫁の弟が初めてクルマを買うにあたり、あまり見かけないタイプの小さなクルマが欲しいとの事です。 私自身スポーツタイプなら詳しいのです...
2011.5.25
解決済み- 回答数:
- 7
- 閲覧数:
- 8,668
-
日本の車検制度って変じゃないですか? スバル360時代ならともかく、なぜ今の軽自動車がここまで性能もよくなって故障も滅多 日本の車検制度って変じゃないですか? 2年に一回車検に出さなければならな...
2018.4.6
解決済み- 回答数:
- 22
- 閲覧数:
- 1,246
-
良く「部品がなくなると、もう乗ることができない維持できない」といいますがそんなことって実際にあるのですか。たとえば極上GT750とか極上ハスラー400の部品が出なかったらスクラップ屋に売るんで...
2017.7.31
解決済み- 回答数:
- 22
- 閲覧数:
- 651
-
軽自動車を馬鹿にするような質問や書き込みをたくさん見受けます。 こういう書き込みをする方たちの精神状態や考えを考察したいと思い、また皆様の考えも伺いたいと思いまして質問を立ち上げました。 まず軽...
2019.5.31
解決済み- 回答数:
- 21
- 閲覧数:
- 284
-
爺です。車が趣味で数台所有しておりますが、 そろそろ終活をしたいと考え2台に絞りたいです、 皆さんならどれを残しますか? マセラティボーラ、 BMWZ3、 240Z、 S600、フィガロ、 5...
2022.3.23
解決済み- 回答数:
- 19
- 閲覧数:
- 743
あなたにおすすめのサービス
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!