なぜ、旧いクルマのデザインは秀逸なのか?[part6:スーパーカー世代を魅了したリトラクタブル・ヘッドライト]
スーパーカー世代を経験した人であれば誰もが「リトラクタブル・ヘッドライト」に憧れたのではなかろうか?
男の子のハートをわしづかみにするギミックとしてもっとも愛されたアイコンだ。現在では生産されなくなってしまったリトラクタブル・ヘッドライト。
一時期は自転車にも採用されるほどの一大ムーブメントを起こし、当時は「スーパーカーライト」という言葉までもが世間に浸透していた。
なぜ、リトラクタブル・ヘッドライトは生産されなくなったのか?
これには複数の理由が考えられるが、最終的に「対人事故の際に突起物として危険と判断された」ことが大きいのかもしれない。つまり安全性の問題だ。
もちろん、他にも重量やヘッドライトを開いたときの空気抵抗、部品点数が多いことによるコスト、光軸がズレるなど複数の問題が絡んでいるようだ。結果として、時代の流れとともに国内では2002年のマツダ・RX-7、2005年にシボレー・コルベットを最後に量産車の生産が終わってしまった。
過去の産物にしておくにはもったいないギミック
スーパーカーブーム真っ只中の時代において「リトラクタブル・ヘッドライト(通称:リトラ)」と「ガルウィング」という2つのキーワードは、当時のクルマ好きの子どもたちにとってマストアイテムであった。
リトラクタブル・ヘッドライトについては、筆者は田舎出身ゆえ、父親にスーパーカーショーに連れて行ってもらうまではテレビでしか見たことのなかった。そのため、実際にヘッドライトが開くところを見たときは我を忘れるほどに興奮したものだ。
特に「ランボルギーニ・カウンタック」は、リトラクタブル・ヘッドライト&シザードア(カウンタックがシザードアということを知るのは、もう少し大人になってからなのだが)という両方のギミックを備えていたのだ。そのデザインはもちろんのこと、男の子のハートをわしづかみにする要素が満載であり、誰もが憧れる存在であったことはいうまでもない。
スーパーカーブーム真っ只中に、サバンナRX-7(SA22C)が発売されたときには、本当に興奮した。
「ついに日本車でもスーパーカーが買える時代が来た!」
おそらく、多くの日本人がトヨタ2000GTは高嶺の花であることを認識していたのか、そう簡単に買えるクルマではないということはわかっていたのだろう。
サバンナRX-7はヘッドライトが開くというだけで、学校でもこの話題で持ちきりだったほどだ。
当時は「リトラクタブル・ヘッドライト」にしか目がいっていなかったのか、子ども心にはロータリーエンジンの存在は頭の片隅にもなかったようだ。
近所のお兄さんがRX-7を購入した際には嬉しくて毎日のように「ライト開けて!」と遊びに行っていた記憶がある。今思えば、RX-7を購入したお兄さんも、ウザいという感情よりも「ヘッドライトを開ける」ことを見せることが嬉しかったのかもしれない。ニコニコしながらいつもライトを開けてくれていたことを鮮明に覚えている。
その後、筆者はこのときのままの感覚で大人になり、20歳くらいの頃だったか、マツダからユーノス・ロードスターが販売されたときはディーラーまでいって見積もりを出してもらった。
当時、フィアットX1/9を中古で安く購入するか、ローンを組んでロードスターを買うか悩んだものである。
結局、何を血迷ったか、ガルウイングに惹かれてトヨタ セラを3年ローンで購入した。
走りたい年頃だったこともあり、3日くらいで飽きてしまった。半年後に売ったときにはローンの支払いだけが残ったという苦い思い出もある(笑)。
世界各国のクルマに採用された、さまざまな種類のヘッドライト
リトラクタブル・ヘッドライトに限らず、当時は色々なヘッドライトが存在した。
やはりスーパーカー・ブームの際に人気だったのがランボルギーニ・ミウラ。ポップアップ式と呼ばれているが、これはライトが見える状態で収納されていて、点灯時に起き上がる仕組みである。
ポルシェ928などにも採用されているが、ミウラの場合はレンズのカットを利用しているのか、起き上がっても斜めの状態である。これも空気抵抗を考えてのことなのであろうか。
アルファ ロメオ・モントリオールは、上部にあるブラインドが点灯時にヘッドライト下側スペースに「シャカ」っと音を立てて格納される変わった仕組みである。しかも圧縮エア式であるため、左右の開閉タイミングが微妙にズレるのも、逆にカッコいいギミックだと感じてしまうのは筆者だけではないはず。
なんと1963年の時点で英国車にも採用されていたロータス・エランのリトラクラブル・ヘッドライト。インテークマニホールドのバキューム(負圧)を使って駆動させる仕組みである。当然であるが、バキュームホースからエアーが漏れるとライトの開閉ができなくなることもあるようだ。
スーパーカーブーム到来以前から国内でリトラクタブル・ヘッドライトを採用していたのが、トヨタ2000GTだ。1967年に採用されていたわけだから、いかに2000GTが当時の最先端の存在だったのかがわかる。
面白いのは開閉速度だ。個体差があるかもしれないが、実際に計ってみたところ、全閉状態から全開状態まで9秒も掛かっていた。とにかくゆっくりと開いていく動作が、カッコいいというより可愛いとの表現もできるかもしれない。
オペル1900GTのリトラクタブル・ヘッドライトは、文字どおり「ギミック」だ。ステアリングの下にある大きめのスティックを手動で回転させると「くるりん」と横に180度回転するのだ。実際にやってみてわかったことだが、カウンタックなどのミニカーのボディー下側にあるヘッドライト開閉スイッチで開けるようなギミックであった。
余談ではあるが「プアマンズ・コルベット」と呼ばれることもあるが、当時は2000GTと同じくらいの金額だったのだ。ちなみにC4コルベットはヘッドライトが縦に180度回転するが、もちろん手動ではない(写真はC3)。
初代カマロには電動の横スライド式ヘッドライトカバーが存在した(当時マーキュリー、リンカーンなど他にもアメ車にはヘッドライトカバーが存在する)。これはリアルタイムで見たことがあったが、意味もわからずワクワクするギミックだった。
英国車のリトラクタブル・ヘッドライトで個人的に非常に印象深いのがアストン・マーチン・ラゴンダだ。実際に目の前で見るとエッジがここまで強調されたデザインには圧倒されるが、ここにリトラクタブルを採用することにも驚愕である。内装のボタン類はタッチパネルがメインになっていて、オーナー曰く「バブル時期のラブホ」みたいで気に入っているとのことだった(笑)。
リトラクタブル・ヘッドライトのようなギミックは絶滅するのか?
現代のクルマのギミックと言えば、電気自動車や自動運転など、見た目とは関係のない方向に進んでいるように思える。
と同時に、速く・安全に走ることを目的としたギミックも日進月歩で進化している。
しかし、男の子のハートをわしづかみにするギミックは、その種とは異なる「もっと単純なもの」なのだ。
高価なスーパーカーは別として、筆者のような庶民にも手の届く価格帯でワクワクするようなギミックが搭載されるクルマが今後発売されることは難しいのかもしれない…。
しかし年齢を重ねてもなお、もしかしたら幼少期のとき以上に「リトラクタブル・ヘッドライト」や「ガルウィング」のようなギミックに憧れを抱く人は意外と多いのではないだろか?そう思えてならないのだ。
なぜ、旧いクルマのデザインは秀逸なのか?過去の記事はこちら
なぜ、旧いクルマのデザインは秀逸なのか?[part1:ヘッドライト編]
なぜ、旧いクルマのデザインは秀逸なのか?[part2:テールデザイン編]
なぜ、旧いクルマのデザインは秀逸なのか?[part3:クーペ編]
なぜ、旧いクルマのデザインは秀逸なのか?[part4:ディーノ206GTと246GTの違いとは?]
なぜ、旧いクルマのデザインは秀逸なのか?[part5:大人になって改めて気づく…。小さなクルマの魅力とは?]
[ライター・撮影/ユダ会長]
こんな記事も読まれています
この記事に出てきたクルマ
全国のマツダ RX-7中古車一覧 (58件)
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
おすすめのニュース
-
-
ベストカーWeb0
-
-
motorsport.com 日本版0
-
-
-
-
-
AUTOSPORT web0
-
WEB CARTOP2
愛車管理はマイカーページで!
登録してお得なクーポンを獲得しよう
おすすめのニュース
-
-
Auto Prove0
-
-
-
motorsport.com 日本版1
-
-
GQ JAPAN1
-
AUTOSPORT web2
-
-
-
-
-
-
ベストカーWeb3
-
GQ JAPAN0
-
motorsport.com 日本版0
-
-
-
-
-
-
AUTOSPORT web0
-
-
-
-
AUTOSPORT web2
-
Webモーターマガジン3
-
ベストカーWeb1
-
カー・アンド・ドライバー4
-
業界ニュースアクセスランキング
-
NEXCOが大激怒「告発も考えます!」 「4年で21回も“不正通行”」した超・悪質事業者を名指しで発表! ルール“完全無視”で「規格外車両」を何度も運行 是正指導を公表
-
中露の「巨大な怪鳥」と空自機が睨み合い!? 沖縄を通り越して“四国沖まで”共同飛行 防衛省が画像を公開
-
アメリカや中国よりも早い?「無人戦闘機」が“高性能対空ミサイル”を発射し目標を撃墜 いよいよ創作物のような話に
-
“軽自動車”よりも安い! 日産「“ニセ”GT-R」登場!? “格安の140万円”&なんか「小さいボディ」採用! 2.5L「V6」×MT搭載の「R35!?」独国サイトに登場
-
また!? アメリカ肝いりの新型艦計画「やめます」「代わりは急いで造れるものを」 鍵は日本にあるのでは?
コメントの多い記事
-
ついに「リッター25円安」が実現!? ガソリン価格が「大きく下がる」理由とは… 51年続いた「暫定税率」廃止のウラ側
-
約8割の人が知らないってヤバいぞ! スタッドレスタイヤは「残溝1.6mm」の前に「プラットフォーム」が露出したら雪道走行はダメ!!
-
韓国に惨敗! 交通行政の限界が生んだ「1万台の差」――日本の横断歩道は本当に安全か
-
中露の「巨大な怪鳥」と空自機が睨み合い!? 沖縄を通り越して“四国沖まで”共同飛行 防衛省が画像を公開
-
大雪の「国道17号」で立ち往生発生に怒りの声“殺到”!? 「免許返納しろ!」「迷惑でしかない」 呼びかけ無視の「ノーマルタイヤ車」が坂登れず… 国道事務所が警鐘 新潟・湯沢
あなたにおすすめのサービス
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
新車見積りサービス
店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!







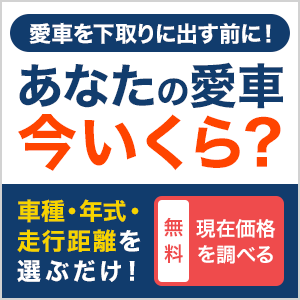
みんなのコメント
フェラーリテスタロッサ、F40、ポルシェ928、アストンマーチンラゴンダどれも個性的で、華がありました!