「軽も世界進出できるかも?」“飛び道具”だったプリウス…世界へ旅立ったクルマ 4選+α
2022年7月、待望の新型クラウンがお披露目された。いまの時代に合わせた4つのバリエーション、そして世界約40カ国・地域でのグローバル展開の発表には驚きを隠せなかった。
そして、これまでにもさまざまなクルマたちが日本から世界へ旅立った。いっぽう、世界へ進出してほしいと思うクルマもあるだろう。
「軽も世界進出できるかも?」“飛び道具”だったプリウス…世界へ旅立ったクルマ 4選+α
そこで今回は、「日本から旅立ち、世界に大きな影響を残したクルマ」と「これから進出してほしいクルマ」を筆者が厳選し、その魅力を解説していく。
文/桃田健史
写真/TOYOTA、NISSAN、MITSUBISHI、HONDA、DAIHATSU、SUZUKI
日本から世界に向けて大きく羽ばたいたクルマの代表格は?
“ほぼ日本専用車”だったトヨタ「クラウン」が、クロスオーバーを筆頭に4車系でのグローバルカーとして生まれ変わったことが、日本を含めて世界で大きな話題となっている。
そうしたなか、改めて日本市場とグローバル市場を見比べてみると、これまで日本から世界に向けて大きく羽ばたいていったクルマたちがいろいろいて、さらにこれから世界に向けて挑戦するべきクルマも存在するように思える。
こうしたクルマたちを、筆者の私見でピックアップしてみた。
世界初の量産ハイブリッド乗用車として、1997年に発売された初代プリウス
世界に向けて大きく羽ばたいたクルマの筆頭は、やはりトヨタ「プリウス」だろう。1990年代後半から2000年代初頭、初代プリウスの時代には、自動車産業の中心的存在であるドイツやアメリカのメーカー関係者からは「ハイブリッドは、トヨタの”飛び道具”であり、グローバルで広く普及する技術でなく、すぐ終わる」という声を筆者は数多く聞いてきた。
ところが、2代目がアメリカで発売されると、カリフォルニア州南部のハリウッドスターなどのセレブや、同州北部の学識者らの間で、環境問題に対する意識の高まりから、大排気量の大型SUVではなくハイブリッド車を乗ることを推奨するといった社会運動が起こる。
また、アメリカではガソリン小売価格が上昇すると、それに比例してハイブリッド車など低燃費車の販売台数が伸びるという、一般ユーザーのクルマ利用に対する市場の流れが明確となり、プリウスはアメリカで市民権を得ていく。
こうしたアメリカでのハイブリッド車に対する意識変化が、欧州などグローバルに広まっていったといえるだろう。
環境への対応で、グローバルに大きな影響を与えた日本車といえば、ホンダ「シビック」も忘れてはならない大きな存在だ。
1970年代のアメリカは、排気ガス規制のマスキー法の施行や、オイルショックによるガソリン価格の急騰などで、第二次世界大戦後から長らく続いてきた大排気量・大型ボディ・豪華絢爛(ごうかけんらん)な内外装デザインといったアメ車のトレンドが事実上の終焉を迎えた。
そこに登場したのが、ホンダの初代「シビック」。副燃焼室によりエンジン燃焼を効率化させたCVCCだった。いまでは多くのメーカーがさまざまな手法で、希薄燃料の技術を量産化しているが、70年代当時には燃焼室内の空気とガソリンの混合気体の動きを可視化する技術は極めて難しかった。
筆者はCVCC開発の理論を考案した人から直接、その苦労話を聞いたことがある。現在は、車体全体の空力の基本となる流体力学をエンジン内部構造に取り入れたという点で、初代シビックはまさに、エポックメイキングだった。
そうした初代の強烈なインパクトによって、シビックという1モデルだけではなく、ホンダ四輪事業全体に対する「先進性」というブランドイメージが根付いたといえるだろう。
アメリカ市場で大ヒットの初代Z マツダのロータリー車は欧州から
スポーツカーとしてはリーズナブルであったことが支持され、北米を中心に大ヒットとなったS30型フェアレディZ
同じく、70年代のアメリカで大きく羽ばたいた日本車といえば、日産「フェアレディZ」がある。
直近では、その初代S30を彷彿するデザインや、懐の深い走り味を感じ取れるRZ34が世に出ているが、RZ34販売総数の7割~8割がアメリカ向けになるという認識を、日産は持っている。
それは、初代S30が70年代当時、アメリカ人にとっていかに大きなインパクトがあったかという証明でもあろう。
先に初代シビックの説明で触れたように、70年代のアメリカ市場全体が大きな転換期となるなかで、単純に燃費が良いというだけではなく、誰もが気軽に楽しめるスポーツカーとして、当時のアメ車や欧州車と比べて価格もリーズナブルだったS30は爆発的なヒットとなった。
このように、日本から見て海外市場とは、多くのメーカーにとって当時の世界最大市場であるアメリカを強く意識しており、グローバルに見て小型大衆車の領域で事業基盤を築いていった日本車の活躍の舞台は、主にアメリカだったといえる。
いっぽうで、技術の原点を欧州に持ち、欧州での量産車の普及促進から、アメリカ市場へと活躍の場を広げていったのが、マツダのロータリー車だ。
1961年、当時の東洋工業(現在のマツダ)はドイツのNSU社とバンケル社とロータリーエンジンの技術提携を正式発表した。
当時、ローターリーエンジンは”夢のエンジン”と称されたが、量産化までには克服すべきさまざまな技術的なハードルがあった。
晴れて、1967年に「ロータリースポーツ」が発売され、1968年には「フェミリアロータリークーペ」が登場する。
当時の東洋工業は、ロータリーエンジンの認知度を広めるため、コスモスポーツでドイツにて開催されたマラソン・デ・ラ・ルート84時間レースに参戦したり、ファミリアロータリークーぺでスパ・フランコルシャン24時間レースに挑戦した。その後、「RX-7」でアメリカのデイトナ24時間レース、そして70年代からさまざまなチーム形態で挑戦し続けてきたルマン24時間レースではついに1991年、「787B」による総合優勝を成し遂げる。
直近で、ロータリーエンジンはEV(電気自動車)のレンジエクステンダー向けの発電機として活躍の場を持つ。
海外へ進出して活躍が期待できる日本車とは?
このほかにも、世界に向けた挑戦を繰り広げてきた日本車は数多い。近年の日本車は、グローバル展開を基本として、国や地域での社会実情や市場性を俯瞰して開発されるため、広義において、日本発での世界に挑戦という括りでの話にはなりにくいように思う。
また、日系各メーカーは、来るEV化時代を念頭にモデルライナップの集約化も進めており、日本市場専用車がほとんどなくなってきているのが実情だ。
そうしたなかで、日本市場専用車の筆頭はやはり、軽自動車であろう。日本市場に特化した車両規定ゆえに、日本の匠の技を集約した、世界でもまれなマイクロカー文化を実現している。
そんな軽自動車を日本の道路事情に近い欧州や東南アジアなどで展開してはどうか、という話はずいぶん前から自動車産業界で話題に出てくる。
実際のところ、軽をそのままではなく、現地化する必要があるという判断から、スズキはインドで、またダイハツは東南アジアで、軽でも使えるプラットフォームを活用するなど、実質的な軽自動車技術の海外展開をしているといえるだろう。
今後、本格的な電動化、そしてEV化を迎える日本車がどのようにグローバルで挑戦するのか、その動向を期待こめて見守っていきたい。
こんな記事も読まれています
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
おすすめのニュース
-
バイクのニュース0
-
AutoBild Japan0
-
-
-
AUTOSPORT web0
-
-
-
-
-
WEBヤングマシン3
愛車管理はマイカーページで!
登録してお得なクーポンを獲得しよう
おすすめのニュース
-
-
AUTOSPORT web0
-
WEB CARTOP3
-
motorsport.com 日本版1
-
-
-
カー・アンド・ドライバー0
-
motorsport.com 日本版0
-
AUTOCAR JAPAN1
-
-
-
motorsport.com 日本版0
-
乗りものニュース2
-
AUTOSPORT web0
-
-
-
-
-
AUTOCAR JAPAN0
-
-
-
Auto Messe Web0
-
Webモーターマガジン0
-
-
-
motorsport.com 日本版0
-
-
-
-
コメントの多い記事
-
日産新型「エルグランド」初公開! 元祖高級ミニバン大刷新で“打倒アルファード”なるか!? 先進的な箱型デザイン&1.5リッターの「スゴいe-POWER」搭載し26年度発売へ!
-
BYD「軽EV」参入、日本どうなる?「150万円以下」「航続距離250km超」は実現? ガラパゴス市場の破壊者となるか? 日産・三菱はどうなる
-
自衛艦と中国軍艦がにらみ合い? 空母「山東」が宮古島南方に出現! 巨大ミサイル艦とともに日本近海をウロウロ
-
「ごみ出しに1万5000円」 町内会の退会者に命じられた利用料! 福井地裁の判決が突きつけた“地域崩壊”の危機とは
-
【中国】レクサス新型「ES」世界初公開! パワトレで異なる「斬新ツルツル顔」&“LEXUSロゴ”光る「一文字ライト」! 全面刷新された「FFセダン」外装デザインの進化とは?
あなたにおすすめのサービス
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
新車見積りサービス
店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!







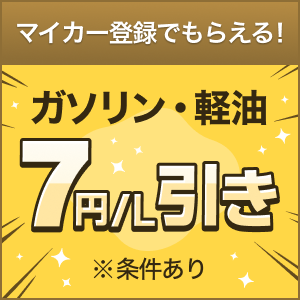
みんなのコメント