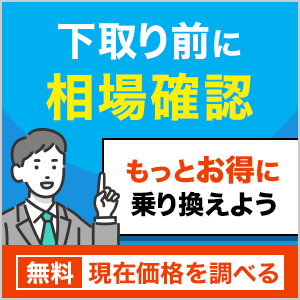- carview!
- 新車カタログ
- メルセデス・ベンツ(MERCEDES-BENZ)
- Mクラス
- みんなの質問(解決済み)
- 近年は環境問題等により、ディーゼルエンジンが...
メルセデス・ベンツ Mクラス のみんなの質問
sl2********さん
2011.11.24 18:19
- 回答数:
- 4
- 閲覧数:
- 670
近年は環境問題等により、ディーゼルエンジンが変化というか進化したかと思います。
以前の実家では20年位前のディーゼル車を乗っていて、オレもよく利用しました。
その頃と現在のディーゼルエンジンは、「どこがどのようになったのか」や「メリット・デメリット」等(価格・性能・メンテナンスなど)、色々知りたくなったので、詳しい方よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
鳥さん
2011.11.24 18:43
クリーンディーゼル搭載車(MB Eクラス、Mクラス、日産 エクストレイル、三菱 パジェロ、マツダ CX-5等)のレビューを見るのが手っ取り早いかと。
エンジンだけの違いではなく(もちろんエンジンそのものの改良も大きいですけど)、車全体の改良点も多いのでエンジン単体ではどうなのか分かりませんが、大まかに言って
・黒煙を吐き出さない
・静粛性が増した
・振動が減った
・回転数がスムーズに上がる
など、ガソリン車的な部分が強くなったようです。
マツダのCX-5(未発売)を除いては、高価な後処理装置で排ガス処理をしている関係上、極めて高価となるのが相場です。
日本車で言えば、ガソリンの同クラス車と比べて50万円以上高価になるのが普通です。(オプションや標準装備の違いもあるが)
メンテナンスはガソリン車的になってきてはいますが、エンジンオイルの管理や使用量は敷居がまだ高いようです。
メルセデスのBLUETECは尿素(アドブルー)処理ですが、2万kmに一回の補充で済むので、実質メンテナンスフリーに近いかと。
日産やトヨタ等の触媒処理は、触媒がダメになることもあるとかないとか。
マツダのSkyactiv-Dはそれらの後処理装置が必要ないということですが、まだ表舞台に出てきていないので何とも言えないところです。
質問者からのお礼コメント
2011.11.29 13:35
一番最初に回答くださったこの方にBAを差し上げます。他のお二方もありがとうございました。
その他の回答 (3件)
-
e60********さん
2011.11.25 19:07
●ディーゼルエンジンの20年間の進歩とは?
排ガス規制への対応の20年間でした
20年前と比較すると,現在のポスト新長期規制(2009年)は
PM(細かいスス)= 2.5%
NOx(窒素酸化物)= 5%
非常に排ガス規制が厳しくなり,現在の規制値は,ほぼ直噴ガソリン並です
直噴ガソリン:PM=0.005g/km,NOx=0.05g/km
ディーゼル:PM=0.005g/km(同じ),NOx=0.08g/km(少し高い)
●規制対応のために何をやっているのか?
PM低減 = より完全な燃焼 → 燃料の微細化+予混合化
NOx低減 = より低温の燃焼 → EGR増加+大量過給
●完全な燃焼とは?
以前のディーゼルエンジンは副室式でした。これは燃焼室の表面積が大きく冷却損失が多いため,燃費がよくありませんでした。ただ副室から主室へ燃焼がゆっくり移行するため,筒内圧力ピークが低くなり,騒音・振動では有利でした。
燃費改善のため直噴が選択されました。問題は直噴後の短時間で十分,燃焼できるかどうかです
★燃料粒径の微細化 … 酸素分子との接触確率を増やすことと → PMは,大きな燃料粒径の中心部にある燃料が酸素と接触しないため,未燃の炭化物として発生。コモンレールにより燃料圧力を高圧にできれば,より微細な燃料粒径になります
★予混合化 … ガソリンエンジンのように空気と燃料を十分混合できれば,酸素との接触確率を改善できます。このためには燃焼時間を長くとる必要があります
→ 課題:燃焼時間を長くすること
●NOx低減とは?
NOxは,高温と十分な酸素濃度がある条件で生成されます。このため酸素濃度を下げれば,NOx量は低減できます。しかしこの方法ではPMが増えます。このため燃焼温度を下げる方法を選択します
★高EGR … 排ガスを再度,燃焼室に戻すことをEGR(=Exhaust Gas Recirculation)といいます。EGRには,CO2(二酸化炭素)が多く含まれます。CO2は,三原子分子のため,二原子分子の酸素や窒素より比熱が28%くらい大きくなります。比熱が大きいほど,同じ熱量に対して温度上昇は小さくなりますので,EGRが多いほど,燃焼温度が低下します。これにより2000K(ケルビン)以下になるようにEGRをたくさんいれます(30%くらい)。ところがCO2は消炎作用があり,燃焼を妨害しPMを増やします。
★高過給 … ターボ・チャージャのような過給機を使い,無理矢理,燃焼室に空気(新気=外気:酸素を21%含む)を入れます。すると燃焼室内の酸素濃度が高くなり,酸素との接触確率が増えて,PMが減ります。このため最近のディーゼルエンジンはどんどん過給量が増えています
つまり過給はダウンサイジングのためではなく,PM低減のためであり,そのオマケとして,高出力化によるダウンサイジングが可能になっています。というのは,出力アップなら,ダウンサイジングするより,排気量を上げた方が,はるかにコストが安いからです
以上のようないろいろな取り組みにより,現在のディーゼルエンジンは,クリーンな排ガスと高い出力特性,そして優れた燃費を達成しています。たとえば
トルク = 同排気量のガソリンエンジンの1.5~2倍 (最大トルク発生回転数が1200~1800rpmと低いので,実用域で運転しやすい)
燃費 = ガソリンエンジンより25~30%改善 (上記 高トルクを達成した上で)
★過給レスポンス … ガソリンエンジンは吸入空気量で出力調整をしますが,ディーゼルでは燃料噴射量で調整します。このため加速時,増量された燃料に見合う空気量が必要になります。
→ 課題:高レスポンス過給
●残る課題は?
残る課題は「燃焼時間の確保」と「高レスポンス過給」ということになります。これを解決したのが,マツダのSKYACTIV-Dです。NOx触媒がないので,従来より20万円くらい安くなります
●どうやって燃焼時間を長くするのか?
一般のディーゼルは上死点の直後に燃料を噴く(コモンレールのメイン噴射)と急激な筒内圧力上昇のため振動・騒音が悪くなります。このためやや遅らせて燃料を噴きます(その典型は日産のMK燃焼)。MK燃焼では,振動・騒音は改善できますが,時間損失(=筒内圧力をトルクへ変換する効率で,上死点後,15度くらいに圧力ピークが来ると良い)が悪くなり,燃費が悪化します
圧縮比を下げると,上死点直後に燃料噴射しても急激な圧力上昇がないので,ゆっくり燃えます。こうして燃焼時間を長くできました
●圧縮比をどうして下げられないのか?
始動時の自発火ができないからです。先日(11月21日)のディーゼル・セミナーでのマツダの寺沢様の説明によると,「SKY-Dの開発=確実な始動」だったそうです。このためにグロープラグの改善+内部EGR(排気弁の可変動弁)+2ステージターボ(再始動時)+リッチ混合気+プリ燃焼(=メイン燃焼の前の小燃焼)で対応したそうです。
●高レスポンス過給は?
ターボを2段階にし,低回転域から過給しました。今後は,LPL-EGR(低圧EGR=過給量を維持)にするそうです
ご参考になれば幸いです。
-
k_f********さん
2011.11.25 00:00
字数制限に引っ掛かりましたので、こちらに続けます。
燃焼室内の圧力とピストンの行程位置でグラフを描いた物は、指圧線図と呼ばれます。
神が作った理想エンジンを基準として考えた場合に、そこからどれだけ圧力の上昇が遅れたかを「時間損」と呼びますが、ガソリンが揮発した混合気に電気火花で点火するガソリンエンジンは、爆発とも称せられる位に燃焼速度が早い事が判ると思います。
一方、着火した後も燃料の噴射が続く拡散燃焼を行うディーゼルは、時間損が大きい事が解ります。
吸入した酸素を使い切る程には、黒煙とNOxが同時に急増してしまって燃料を増やせないので、理論空燃比を使って酸素を使い切れるガソリンに較べると、必ず3割方、排気量を多くせねばならない宿命を持つディーゼル。(λ=1.3)
高圧縮、大衝撃に耐えねば成らないので丈夫に作らねばならないディーゼル。拡散燃焼なので回転馬力を稼げないディーゼル。
小型軽量大出力が求められる乗用車向けには、時間損も大きく、小型に成らない、排ガス浄化も容積を食う、と本質的に向いていないエンジンなのです。
おまけに、余剰酸素を常に排出するが故に、その排ガス対策も完全に消化し切れていない。
ですから、小型車向けにはディーゼルの良い所を採り入れて大改良を施したガソリンエンジン(スロットル弁廃止、高過給化)を使い、大型車向けに注力して行くのが、今後のディーゼルエンジンの正しい在り方なのです。
<追加>
もう少し追加しておきます。
NOx抑制には、燃焼温度を下げる排ガス再吸入(EGR)が良く聞きます。が、軽油に硫黄分が含まれているので亜硫酸ガスが発生し、これをEGRすると潤滑油があっさり酸化されて腐蝕摩耗するので、中々採用出来ませんでした。硫黄分は高圧ポンプや噴射ノズルの摩耗を防止する役割も担っていた為に、無しに出来なかったのです。
しかし8都県市の条例制定でDPFの採用が不可避に成ったので、硫酸被毒 → 無効化を避ける為に、サルファフリー軽油の流通が始まりました。これを契機に、尿素SCR等も採用出来る見通しが立って来たのです。
現在はEGR無しには排ガス浄化は語れませんので、エンジン油も相応にアルカリ価が高い物が不可欠に成っているのです。
噴射の高圧化は、相応に補機類製作費を押し上げます。ノズル等の精密な機器は、これ又高価につきます。加えて、耐久性についても未だ未だ未知数の所が有ります。
とても狭い、袋小路の奥を深堀りしている様な技術開発、と表現しても良いかもしれません。
-
k_f********さん
2011.11.24 23:59
sl2002swさんへ
20年かぁ。こんな書き方でどうかなぁ。。。
ディーゼルエンジンは、圧縮して高温に成った空気の中に燃料を吹き込んで燃焼させますよね。中々綺麗に燃焼させられなかった為に、副室と呼ばれる小部屋を設けて、そこで先ず着火させ、火焔を燃焼室内に放射する様に、燃焼室が作られていたのです。
大別すると、ベンツだけがやったプレナムチャンバー式と、世界中の大多数が使ったリカード(渦流)式が在って、ほぼこの二つで決め打ちでした。
余談ですけど、今でも大排気量のガスエンジンでは、大面積の燃焼室一杯の希薄混合気に一気に着火する為に、電気火花より着火力の強い軽油を使った副室(パイロット着火)式が生き残っています。
http://www.mhi.co.jp/technology/review/pdf/404/404246.pdf
許容出来る位に完成度が高まって、大いに広まった。
「さて、次の課題は」と成ると、高過ぎる圧縮比を下げたい、と成って来ます。又は、副室が在る為に大き過ぎる燃焼室表面積を小さくして、冷却損を低減したい、と。
副室が有って冷え過ぎる為に、圧縮比を22〜23と大きく設定せねば成りませんでしたから、これを少しでも下げたかったのです。
えっ? 圧縮比は大きい方が効率が良く成るんじゃなかったの??
実はそうじゃ無いんですね。
圧縮比、つまり燃焼で作った高圧のガスをどれだけ膨張させるかで、熱効率は決まって来ます。燃焼最高温度と圧力が同じとしたら、同じ膨張比のエンジンならディーゼルでもガソリンでも相違は生じない事に成ります。よね? 膨張させるだけですから。
理論的には大きく膨張させる程、仕事に変換されるので効率が上がる。
しかし、膨張比を大きく設定しようとするに従ってロングストローク傾向に成り、ピストンとシリンダーの摩擦量が増えて来てしまいます。から、ある所で頭打ちに成り、以後は逆に摩擦損が増大するので下がって行ってしまいます。ピークを描くのは、膨張比14と計算されて来たのです。
22〜23じゃあ高過ぎる。おまけに表面積も過大で冷却損が大きい。から、副室無しに綺麗に燃やせる様に、という直噴がトライされ、実用化されたのです。
表面積が減りますし、圧縮比も下げられる分、過給を大々的に使って行けるという効果も望めたので、直噴が実用化され、圧縮比も16.5程度迄下がって来たのでした。
次なるトライは?
噴射圧を高圧化して、瞬時に噴射を終わらせてしまおう、という研究が筑波の新ACEで行われました。
燃料を噴射する際、着火し始めた火焔の中を後続の燃料が通過するので、燃え易い水素だけが先に奪われ、残った炭素が互いに手を繋ぎ合う様にして巨大化するので黒煙が発生する、と考えられたからです。
高圧にして噴射時間を短縮すれば、着火しても火焔が大々的に成長する前に噴射を終わらせられる。しかも、燃焼室外縁部に到達した燃料から先に燃えてくれるので、中心部の火焔が酸素不足に成らずに済む、と目論んだのですが、エンジンが壊れそうな位にディーゼルノックが高まってしまった事に加えて、NOx生成量がハチャメチャに増えてしまったので、直接的な実用化は断念されたのでした。
そして、都知事による電撃的な規制強化によって尻を叩かれた結果、コモンレール式に代表される、高圧且つ精密な噴射が出来る構造・機構で、つまり一気に噴射するのでは無く、
http://www.isuzu.co.jp/technology/d_databook/tech/tech_02.html
の様な多段噴射を行う事で、NOx急増と黒煙規制を乗り切る様に成って来たのでした。
でも、これだけでは全然不足なんですね。
コモンレールが登場する遥か以前から、過給によって空気過剰運転にすれば、黒煙発生を抑制出来るのみならず、インタークーラーを使って吸気温を下げれば、NOx生成量が大幅に抑えられる事が判っていました。ので、欧州ではトラックで小排気量化とTurbo過給が普及して行ったのですが、日本では異常に多い信号でのStop&Go環境なので、自然吸気大排気量ディーゼルが温存され、黒煙が目に付き易い状況と成っていたのです。
現在、ほぼ全ての大型車はTurbo過給に成っていますが、低回転域で過給圧が高まらない事、よって排ガスが汚い事、その領域では低トルクで発進性が悪い事、変速機が多段化せざるろ得ない事等は、相変わらず問題点とされているのです。
小型のディーゼルについても同様で、やっとマツダがSKYACTIVE-Dで圧縮比14達成を宣言した様に、未だ未だ低圧縮比化や更なる過給圧の上昇、そして排ガス対策等、困難な課題を抱えている状態です。
<字数制限>
「自動車」カテゴリとデータを共有しています。
あわせて知りたい
-
車の買い替えっていつでしょうか 私は二児の父です 14万㌔のボクシー70(H24)に乗っていますが、不具合はありません 燃費の10前後と良くはないですが、大きな不満もありません 家族が増える関...
2025.2.5
解決済み- 回答数:
- 16
- 閲覧数:
- 163
ベストアンサー:自分の場合は、その時で買い替えタイミングが違いました。 前々の時は60型ノアを13年で45万km乗り、車検費用が交換部品など合わせて50万くらいになったので、とりあえず中古の軽を20万くらいで購入しました。 その後に中古の30型ヴェルファイアを増車して、9年10万kmになった時に40型ヴェルファイアが抽選などなく購入できるとなり、急遽乗り換えしました。30型ヴェルファイアが中古購入時の半額程...
-
2013年式 BENZ ML350 アメリカ仕様 カーナビについて質問です。 カーナビの表示が アメリカとカナダしかでません、地域設定の画面でもアメリカとカナダの二カ所しか選択枠がありません日本...
2025.1.26
回答受付終了- 回答数:
- 1
- 閲覧数:
- 14
-
- 中古車本体価格
-
79.0 万円 〜 318.0 万円
-
- 新車価格(税込)
-
797.0 万円 〜 829.0 万円
Mクラスを見た人はこんな車と比較しています
メルセデス・ベンツ Mクラス についてもっと詳しく
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。
ログイン
メルセデス・ベンツ Mクラスのみんなの質問ランキング
-
ニコニコレンタカーで5人乗りのレンタカーかりて長野県のスキー場にいくならなにをかりますか? 最近、雪山にFFスタッドレス+チェーンで行って、単独事故しました。険しい急なの雪山はいがいとすいすいい...
2013.1.3
解決済み- 回答数:
- 5
- 閲覧数:
- 16,717
-
大型1種免許を試験場(1発試験)で取得された方、取得時の回数等を教えて下さい。 職場で大型免許の取得を考えています。 私自身は免許改正前に大型を試験場で取得したので、現在の状況をご存知の方に教...
2010.6.20
解決済み- 回答数:
- 3
- 閲覧数:
- 12,761
-
中型観光バスをキャンピングカー登録するため、座席などを外しまくって、さらに家具などをドサドサと置きまくっても大丈夫なんですか? 聞いたところによると、ハイデッカーのバスは重量配分を細かく計算して...
2011.5.13
解決済み- 回答数:
- 2
- 閲覧数:
- 9,943
-
セダンの全長5mクラスは左折するときに煽るのは、仕方ないですか? かつて、普通免許取得するのに、30メートル前には左に寄り巻き込み確認をして… もちろん、曲がった先の対向車がはみ出していたり、...
2023.3.26
解決済み- 回答数:
- 24
- 閲覧数:
- 1,003
-
車の買い替えっていつでしょうか 私は二児の父です 14万㌔のボクシー70(H24)に乗っていますが、不具合はありません 燃費の10前後と良くはないですが、大きな不満もありません 家族が増える関...
2025.2.5
解決済み- 回答数:
- 16
- 閲覧数:
- 163
-
フリードから新型ノアへの買い替えについて 現在フリードに家族5人で乗っています。 子どもは10歳、8歳、5歳の3人です。ベンチシート型で、2列目に3人が乗っています。子どもがこれから成長するにあ...
2023.12.28
解決済み- 回答数:
- 13
- 閲覧数:
- 4,617
あなたにおすすめのサービス
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!