クルマ界のサザンか松任谷由実か!? 偉大なるマンネリを貫く「健康長寿」なクルマたち
自動車が量産化されるようになって100年以上が経過しているが、その間に数え切れないほどの車種が誕生し、そして消えていった。そんななか、絶えることなくシリーズを存続している“健康長寿”のクルマがある。なぜそれらのクルマは長寿を保っていられるのか? 今回は寿命の長さを誇る6種類の国産車をピックアップし、愛され続けるその理由を探っていきたい。
文/長谷川 敦、写真/スズキ、トヨタ、日産、Favcars.com、ホンダ、マツダ、三菱自動車
クルマ界のサザンか松任谷由実か!? 偉大なるマンネリを貫く「健康長寿」なクルマたち
誕生から56年、大衆車の王者はまだまだ進化する 「トヨタ カローラ」
現行型12代目カローラ。シリーズ初の3ナンバーモデルとなったが、エッジを絞ったデザインのためか、サイズアップされた印象をあまり感じさせない
日本が高度経済成長期にあった1966年、トヨタは新たな大衆向けモデルの「カローラ」を発売した。それまで実用一辺倒だった大衆車に、スポーティなテイストを盛り込んだカローラの開発コンセプトは「80点主義+α」。この時代に急速に整備されつつあった日本国内の高速道路事情にも適した初代カローラは、累計生産台数100万台を突破し、狙いどおり大衆に愛されるクルマになった。
ほぼ4年サイクルでのモデルチェンジを繰り返したカローラは、1983年登場の5代目でシリーズ初のFF方式を採用。コストやスペース効率に優れるFFは、カローラにとっても最適な駆動方式であり、同車のFF化は国内でのFF普及を一気に加速させた。
日本国内がバブル景気に沸いた1990年代前半にはカローラも高級路線へと舵を切った。そしてバブルが弾けるとシンプルなコンパクトセダンへと回帰。このように、時代が求める姿へと自在に変化するカローラの柔軟性が、シリーズを存続させる大きな要因になっていることがわかる。
2019年に登場した現行型12代目カローラは「曲がりたいところで曲がり、止まりたいところで止まる」という、クルマの基本とも言えるコンセプトで開発され、シリーズ初の3ナンバーモデルとなった。これもまた時代の要求に応えた姿なのは間違いない。
現トヨタ社長の豊田章男氏が、社会人になって最初に自分のお金で買ったクルマがカローラだったそうだ。トヨタのトップに立つ人物にとっても思い入れの強いカローラは、今後も時代に寄り添って生き続けていくだろう。
日産の伝統を受け継ぐ地平線 「日産 スカイライン」
日産 スカイラインの現行モデル(2019年)。3.0リッターV6ターボエンジンモデルもラインナップされ、最上級グレードの400Rはなんと400psを叩き出す
2022年に誕生から65年となった飛びきりのご長寿モデルが日産のスカイライン。初代モデルの登場は1957年だが、製造販売は日産ではなくプリンス自動車が行っていた。そしてプリンス自動車は1966年に日産と合併することになり、ここから日産 スカイラインとして販売が継続されることになった。
初代スカイラインはプリンスセダンの後継となるプレミアムカーで、ド・ディオン式リアサスペンションや2スピードワイパーなど、国産車初の機構も盛り込まれていた。後年にはよりスポーツ色を強めたクーペモデルも作られ、これがスカイラインのイメージを形作っていくようになる。
日産と合併後の1969年、当時の技術を集めた2000GT-Rが生み出される。レースにも投入されたGT-Rは、強力なライバルだった外国車を打ち負かし、やがて常勝モデルとなって国内レースに君臨した。
それからはモデルチェンジを繰り返し、CMキャッチコピーや外観デザインに合わせて「ハコスカ」や「ケンメリ」、「鉄仮面」などの愛称を得ている。通常ラインナップに加えて走りを重視したGT-Rにも数多くの名車が生まれた。特に1989年にリリースされた8代目R32型GT-Rは、シリーズ初の4WDが採用され、レースだけでなく公道でもその速さを披露してみせた。
2007年からはGT-Rが独立した別車種となり、スカイライン本流は独自路線で進むことになったが、高級志向が強まり、近年のモデルはかつてのスカイラインからかなりイメージの異なるものとなっている。
現行のスカイラインは2013年発売の13代目。2019年にはビッグマイナーチェンジが実施されたものの、登場からすでに9年が経過し、そろそろフルモデルチェンジ版の登場も期待されている。14代目スカイラインは果たしてどんな姿となるのか?
大衆車からの脱却で堂々の長寿モデルに 「ホンダ シビック」
現行型ホンダ シビック。従来型同様のガソリンエンジンモデルに加えてハイブリッドのe:HEVも登場。ボディバリエーションは4ドアと5ドアハッチバック
2022年に生誕50周年を迎えたのがホンダのシビック。同社の乗用車では最も長い期間同一名称で販売されているモデルであり、現在は11代目がその名を継承している。
車名の「CIVIC」は「市民」を意味する言葉であり、元々は大衆向けのコンパクトカーとして1972年にデビュー。FF方式の車体に当時の厳しい排気ガス規制をクリアしたCVCCエンジンを搭載し、クルマにとっては逆風のはずの1973年のオイルショックをも味方につけ、世界各国で大ヒットモデルになった。
初代モデルの成功を受けて登場した2代目も堅調な売り上げをみせ、以降シビックはホンダの4輪車を代表するモデルの地位を確立していくことになる。
そんなシビックの転機となったのが2005年。同年に登場した8代目シビックは、それまでのコンパクトカー路線から脱却して3ナンバーサイズに拡大された。この頃のホンダ製コンパクトカーはフィットがメインになっていて、シビックは3ナンバー化によって車格を上げることになった。
シビックを語るうえで欠かせないのが「タイプR」だ。ホンダが自社製チューンドモデルに与える名称のタイプRはシビックにも存在し、最初は5代目シビックのチューンドバージョンで1997年に登場した。シビック タイプRはその後も複数のモデルが作られ、いずれも高い人気を獲得している。
最新11代目シビックは2021年にリリースされた。翌2022年にはシビックシリーズ初のハイブリッドモデルとなるe:HEVも登場するなど、時代の要請に応じたバリエーションを展開するのはシビックならでは。
かつては誰でも手が届く大衆向けコンパクトカーとして、そして現代では個性的なミドルクラスセダンとして多くの人から愛され続けるシビック。50歳となった今でも老成することなく、常に若々しいエネルギーを感じさせてくれる。
続けることが人気の証 「マツダ ロードスター」
マツダ ロードスター。写真は現行の4代目モデルで登場は2016年。シリーズのイメージを受け継ぎながらも、先代からの大胆な変更によって洗練された仕上がりに
数多くの魅力的なモデルが誕生しながらも、流行の影響を受けやすいせいか、長く続くシリーズがあまりないのがライトウェイトスポーツカー。実用性よりも楽しさを重視したモデルは、メーカーに余裕がないとすぐにシリーズが打ち切られてしまうことが多い。
だが、マツダのロードスターは、発売以来30年以上が経過した現在でもシリーズが存続し、今や国産ライトウェイトスポーツの牙城を守る唯一の存在となっている。
ロードスターの誕生は1989年。当時のマツダは販売店の5チャンネル化戦略を進めていて、ロードスターもマツダではなくユーノス店の初弾となる「ユーノス ロードスター」の名称で販売された。ちなみにロードスターとは2人乗りオープンカーを指す英語で、各メーカーからもロードスターモデルがリリースされている。
ユーノス ロードスターは、折からのバブル景気も後押しになって発売直後から高い人気を獲得した。日本国内だけではなく海外からも評価され、発売翌年には全世界で10万台のセールスを記録している。
その後はマツダの販売形態変更に伴ってユーノスブランドからマツダ ロードスターになるものの、シリーズの製造販売は続けられ、現在では2016年登場の4代目モデルが世界の道路を走り回っている。
初代の販売からすでに33年が経過し、その間にクルマのトレンドも移り変わっている。特にエコが重要視される現代では、楽しむために乗るスポーツカーにとって肩身の狭い状況と言える。しかし、マツダ ロードスターはライトウェイトオープンスポーツというコンセプトを守り、多くの人に運転する喜びを与え続けている。
もはや“そこにいる”のが当たり前? 「スズキ アルト」
初代は1979年に登場したスズキ アルト。写真のモデルは2021年に発売された9代目モデル。外観デザインは先代をベースにより丸さを強調したものとなった
「アルト47万円」というフレーズが耳に残っているベテランドライバーも多いはず。これは1979年に発売された鈴木の軽自動車「アルト」のCMに使われたコピーで、もちろんアルトの価格を知らせるもの。当時の軽自動車が60万円台で販売されていたことを考えるとかなり安いと言える。
さらにこの47万円が全国統一価格だったことにも注目が集まった。この頃の自動車販売価格は地域によって差があるのが普通だったため、アルトはどこで買っても同じ金額を支払うだけでいいのがユーザーへのアピールになった。
現在でもシリーズが存続し、スズキ製軽乗用車の代名詞的存在になっているアルトだが、実は当初は商用車として販売されている。これは当時の商用車には物品税がかからなかったのが理由で、実質的に日常使用できるにもかかわらず、節税が可能でさらに販売価格も低く、クオリティも高かったアルトが成功しないわけはなかった。
以降のアルトは順調に売り上げ実績を残し、さらには派生車種も誕生させていくが、なかでも1987年登場のアルトワークスは、3気筒DOHCインタークーラーターボエンジンを搭載するパワフルさをウリにした過激なモデルだった。
最新のアルトは2021年登場の9代目。この世代からマイルドハイブリッド採用モデルをラインナップするなど、時流に乗った戦略にも抜かりはない。
もはや風景のひとつと言ってもいいほど自然に街中に溶け込んでいるアルトは、誕生から40年を超えてもまだまだ元気だ。
カテゴリーを変えて受け継がれる伝統の車名 「三菱 デリカ」
三菱 デリカD:5。デリカスペースギアの後継車種で、現行三菱 デリカのフラグシップ的存在。デリカにはD:2&D:3も存在するが、三菱の自社製造はこのD:5のみ
デリバリー(運搬・配達)を行うカー(車)――それが三菱「デリカ」という車名の由来。この名称から想像できるとおり、初代のデリカは、デリカトラック(1968年)、デリカバン(1969年)の2タイプの商用車で登場し、以降はこの2タイプのラインナップを展開した。
1979年には2代目デリカをベースにした乗用モデルのデリカスターワゴンがリリースされ、デリカの名は日常用途のクルマにも用いられるようになった。さらに1994年にデリカスペースギアも発売となり、乗用デリカも一気にポピュラーな存在に駆け上がっていった。
デリカバン&トラックは、1999年から他社製OEM供給モデルになり、本流としてのデリカは2019年にその歴史を終えることになった。だが、2011年より三菱では国内向けミニバンの名称をすべてデリカに統一する戦略を開始。その結果、現在ではデリカD:5、デリカD:3、デリカD:2の3車種が現役で活躍している。
デリカの名称は2023年に生誕55年を迎える。車格やカテゴリーは変化しても、この名称だけは変わらず生き続けているのだ。
技術の進歩に伴う変化の大きい自動車業界において、同一シリーズが長期間継続しているのは稀有な例だ。それだけに現存の“長寿モデル”が今後も健康的に続いていくことを期待したい。
こんな記事も読まれています
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
おすすめのニュース
-
-
-
-
-
GQ JAPAN0
-
-
-
-
-
ベストカーWeb48
愛車管理はマイカーページで!
登録してお得なクーポンを獲得しよう
おすすめのニュース
-
-
-
GQ JAPAN1
-
-
-
-
motorsport.com 日本版2
-
GQ JAPAN2
-
GQ JAPAN3
-
motorsport.com 日本版2
-
-
-
バイクのニュース3
-
-
-
-
GQ JAPAN0
-
motorsport.com 日本版0
-
-
-
-
AUTOCAR JAPAN0
-
ベストカーWeb23
-
-
motorsport.com 日本版0
-
-
-
AUTOCAR JAPAN2
-
-
ベストカーWeb9
業界ニュースアクセスランキング
-
海自の艦艇に搭載された「未来の大砲」を激写!SFの世界が現実に!? 戦闘を一変させる革新的な兵器
-
NEXCOも国も激怒!?「告発します」 3倍超過の「72トン」で国道走行…全国で多発する違法な「重量オーバー」に厳重対応も
-
トヨタ斬新「スライドドアSUV」が凄い! 全長4.3m“ちょうどいいサイズ”×カクカクボディがカッコいい! 2リッターハイブリッド4WDの“コンセプトカー”「Tjクルーザー」とは
-
お金持ちは損をしない!? なぜ経営者は新車のベンツではなく3年10カ月の中古車を選ぶのか? その心は?
-
高齢女性が「踏み間違い」で暴走!? 「歩行者7人」を巻き込む“大事故”に… 「免許返納すべき」「またこんな事故!」の声も? 減らない高齢者事故で「免許制度」を問う社会問題に
コメントの多い記事
-
フィットが1年間でたったの6万台しか売れてない!? かつての勢いはどこへ?
-
まさかの500万円切りってマジ!? BYDシーライオン7が高級SUV市場をひっくり返しそうな件!
-
高齢女性が「踏み間違い」で暴走!? 「歩行者7人」を巻き込む“大事故”に… 「免許返納すべき」「またこんな事故!」の声も? 減らない高齢者事故で「免許制度」を問う社会問題に
-
国の「ガソリン補助金」、17日から0円に! “支給なし”は制度導入後で初! しばらくは「レギュラー185円」継続か… 今後は「補助金復活」の可能性も素直に喜べないワケ
-
NEXCOも国も激怒!?「告発します」 3倍超過の「72トン」で国道走行…全国で多発する違法な「重量オーバー」に厳重対応も
あなたにおすすめのサービス
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
新車見積りサービス
店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!







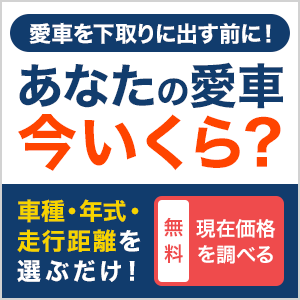
みんなのコメント
サザンとユーミンに謝れよ