【ハイブリッドの先駆者たち】前編 ファミリーカーからスーパーカーまで 黎明期のハイブリッド再検証
100km/Lを目指して
text:Richard Lane(リチャード・レーン)
photo:Olgun Kordal(オルガン・コーダル)
2002年4月のある朝、フェルディナント・ピエヒはウォルフスブルグからハンブルグへクルマを走らせていた。この頃、彼はそのエリアで数多くの仕事をこなす日々を送っていたのだ。230km弱の道のりは、冷たい雨が降る天候のなかを行く、フラットキャップにチェックのスカーフという古めかしい服装に身を包んだ彼のドライブは密度の濃いものだった。
彼はラジオを聞くこともなかったが、そもそもそんなものはついていなかった。エンジン出力はほんの9ps弱しかないから、無駄なオーバーテイクはしない。アウトバーンの流れに合わせて速度を上げ下げしながら、ピエヒは3時間かけて、本社から重要な株主向けのイベントに向かっていた。ある面では、そこに特別なことはなにもなかった。
もちろん、そのドライバーが引退を目前にした65歳の経営者だというのは、ありふれた話ではない。ピエヒは自社の企業理念と同じく、すばらしくもしばしば冷淡さを見せる、フォルクスワーゲンの取締役会会長だった。イベントというのは、この野心的な会社の42回目となる年次株主総会だ。
出発してから5つ星ホテルのフィア・ヤーレスツァイテンに到着するまで、彼の乗ってきたクルマに積まれた、トースターくらいの大きさしかない299ccのディーゼルエンジンが消費したのは、たった2.1Lの軽油のみ。燃費にして、112km/Lほどだ。
この頃、ピエヒがなにより重要視していたのは、1Lの壁というやつだ。そしてそれは、その後10年にわたり、フォルクスワーゲンに不条理なほど多額の出費を強いることになる。
合法的に公道を走らせながら、リッター100kmという経済性をいかにして成立させるか、難題は山積みだった。言い換えるなら、1リッターカー・コンセプトに用いた戦闘機のようなタンデムシートも、車重290kgを実現する薄っぺらな造りも、巨大なソーセージの皮にリコリスキャンディーを無理やり詰め込んだような不恰好なデザインも使わずに、当時としてはまったく非現実的な燃費をどうやって実現するのか、ということだ。
その答えとなるXL1が、アンヴェールされるまでには9年かかった。発表の場が産油国のカタールというのは、なんとも皮肉な選択だったが。そしてそのクルマは、あの春の朝にピエヒが走らせた黒いソーセージのようなテストカーに劣らぬ驚きを、今見ても覚える。このXL1を送り出したフォルクスワーゲンは必然的に、燃費争いにおける最終兵器の発射ボタンを押すことになったともいえる。
エコカー界のスーパーカー
XL1は、方向性こそ違うが、常識はずれの技術の塊という点でいえば、ブガッティ・ヴェイロンの従兄弟みたいなクルマだ。どちらもピエヒの監督下で開発され、スーパーカー的な理論を異なるかたちで使ったのである。2014年まで生産され、最終的な価格は9万8515ポンド(約1379万円)。大衆車というには、あまりにもワイルドだ。
モノコックはフルカーボンFRPで、マグネシウム合金のホイールを履き、ブレーキディスクはカーボンセラミック、エキゾーストはチタニウム。手動で開閉するランボルギーニ・カウンタックのようなウインドウはポリカーボネートで、スパルコ製のシートはシェルがカーボンFRP。パワーアシストなしのステアリングと、専用のマグネシウムケースに収まったDCTを装備し、アンダーフロアはフラット。エンジンはリアミドシップに搭載し、デリケートなスタビライザーもカーボンFRPを用いている。
スーパーカーだとしても、間違いなくハードコアな部類に入る。そして、なにより小さい。車幅はルノー・ルーテシアより狭く、車高はアリエル・アトムのエアボックスより低い。細長いレバーで開くガルウイングドアもスーパーカー的で、やはりピエヒが手に入れたランボルギーニを思わせる。もっとも、その管理はフォルクスワーゲンではなく、アウディの管轄とされたが。
パワートレインは、800ccの2気筒ディーゼルターボに小さな電気モーターを加え、約50kmのEV走行が可能。結果、111km/Lを誇るハイパーなハイブリッドができあがった。
ピエヒが農夫のような格好で、宇宙船みたいなプロトタイプを走らせていた頃、トヨタとホンダは次の段階へ進もうとしていた。両者とも、すでに市場での燃費争いを本格化しており、トヨタが世界初の量産ガソリンハイブリッドをデビューさせていたことはご存知の通り。いっぽうのホンダはわずかに遅れて、ハイブリッドに空力性能と軽量化を組み合わせた際の有効性を示してみせた。
ハイブリッド時代のパイオニア
1994年に始動した初代プリウスの開発は、タフさを極めた。真の21世紀のクルマを送り出そうという決意を固めたトヨタの首脳陣が、当時のカローラに対して倍の燃費性能達成を厳命したのだ。エンジニアリング的に全く未知の要素というわけではないものの、ゴールはなかなか見えなかった。
「通常の乗用車開発では、経験豊富な年配スタッフがあまりにも熱心で、助言しづらく、若いエンジニアは新しいことをできませんでした」と、プリウスの開発責任者だった内山田竹志氏は、2015年の日経アジアの取材に答えている。「ところがハイブリッドに関しては、誰もどうしていいかわからなかったので、干渉もできませんでした。重圧は大きかったですが、士気も高まりましたよ」。
彼らが創り出したのは、電気モーターをふたつ使ったシステムだ。メインとなるのは駆動用モーターで、減速時にはジェネレーターとして機能し、エネルギー回生を行う。もうひとつは、エンジン駆動力を電力に変換するジェネレーターで、CVT機能の制御と、それを介してエンジンをクランキングするスターターも兼ねる。
それらのフローを整えるのはプラネタリーギアで構成される動力分割機構で、これがエンジン回転数を制御するCVTとしても機能する。この複雑怪奇さを考えると、エンジンカバーに記されたハイブリッドシステムの文字を、楽しげで無邪気さすら感じる字体としたのは、マーケティング部門の腕利きのお手柄といえるだろう。
その作業の広範囲ぶりは、理解し難いほどだ。内山田氏は先に引用したインタビューの中で、開発当初はニッケル水素バッテリーの出力が必要とされる数値の半分にしか達しなかったと打ち明けている。しかも、欠陥率は許容レベルの100倍だったという。
1995年に、トヨタはプリウスの発売を1年延期し、1997年とすることを決定する。このタイミングでスケジュール変更が必要な事態というのは、悪いジョークだといっていい。この頃、エンジニアたちが完成させていたのは1台のプロトタイプのみで、しかも49日間も動かなかったらしい。
その風向きが変わったのは50日目のことで、その走行距離はたったの500mだったものの、状況は確実に前進を始めた。「21世紀に間に合いました。」というのは単なるキャッチコピーではない。血と汗のにじんだ本音だったのだ。
エコとスポーツの好バランス
最後はホンダの小さなハイブリッド、インサイトだ。ちょうどXL1とプリウスの中間といったところ、というのは、価格ではなくコンセプトの話。もしXL1を考慮に入れなければ、これはもっと目を引くクルマになるだろう。少なくとも、プリウスよりは見飽きないデザインだ。
インサイトには特徴的なリアスパッツをはじめ、空飛ぶ円盤を思わせる14インチのアルミホイールやエレガントなカムテールを形成するガラスのテールゲート、薄く口を開けたグリルなど、ルックスに見どころが多い。そして、それらすべてが相まって、0.25という優れたCd値を達成している。
もちろん、この点についてはXL1が0.18という驚異的な数値を叩き出していることに言及しないわけにはいかない。これは、現行の量産車においてトップであるメルセデスEQSの0.19をも凌いでいる。しかも空力は、あの巨大なEVより、XL1のような小さいクルマでそれを成し遂げるほうが難易度は高い。
ホンダが産んだ効率命の2シーターに乗っていると、ガラスハウスからの眺めが好きになってくるはずだ。そのおかげでキャビンには開放感がもたらされ、XL1の室内より心地よく過ごせる。しかもリアが絞り込まれたボディワークにより、ホイールハウス周りはスポーティなブリスターフェンダーのように見える。
目に見えないところにも魅力はある。アルミボディのインサイトは燃費スペシャルかもしれないが、たった995ccの3気筒とはいえ、6000rpm回るVTECエンジンを搭載。IMAと呼ばれるハイブリッドシステムは、6cm厚の電気モーターをエンジンと専用の5速MT(もしくはCVT)との間、すなわち通常ならフライホイールが備わる位置に組み込んでいる。
プリウスやXL1と違うのは、3.5kg-mのモーターだけでの走行はできないことだ。電力はあくまでアシストで、低回転域でもっとも効率的に機能する。その効果は、驚くほど高回転型の超小型ターボをつけたようだ。
このパワートレインの先進的な部分は、電気モーターだけじゃない。エンジンの吸気マニフォールドとバルブカバーなどは、樹脂素材を採用して軽量化。マグネシウムのオイルパンは、重量を削減しながら、薄肉スリーブ構造で小型化したブロックを補強するという副産物も得られた。当時、1.0Lユニットとしては世界最軽量だと謳っている。
燃焼室内では、混合気に一般的なエンジンより強いスワールを発生させ、リーンバーン運転を実現。29.4km/Lの公称燃費は、これよりパワーの低い当時のフォード・フィエスタに積まれた1.3Lのじつに倍だった。
最高速度は180km/h止まりだったが、ギア比からは283km/hに達する計算。1100kgのフィエスタよりかなり軽い835kgのウェイトと優れた空力性能もあって、コンディションが整っていれば、40Lタンクのフル給油で1050km近く走れることになる。ロンドンからベルリンまでノンストップで走り切れる、ということだ。
しかもキャビンのホスピタリティは完備され、1999年当時の最新装備はフルに備わる。これに乗っていたならば、ピエヒの長距離ドライブはもっと快適だったことだろう。
こんな記事も読まれています
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
おすすめのニュース
-
Auto Messe Web0
-
WEB CARTOP1
-
Webモーターマガジン0
-
THE EV TIMES1
-
LEVOLANT0
-
motorsport.com 日本版0
-
AUTOCAR JAPAN0
-
AUTOCAR JAPAN0
-
-
motorsport.com 日本版0
愛車管理はマイカーページで!
登録してお得なクーポンを獲得しよう
おすすめのニュース
-
AUTOSPORT web0
-
レスポンス2
-
-
AUTOCAR JAPAN0
-
乗りものニュース0
-
motorsport.com 日本版0
-
-
-
AUTOCAR JAPAN0
-
AUTOSPORT web1
-
ベストカーWeb23
-
-
-
-
motorsport.com 日本版1
-
AUTOSPORT web1
-
-
-
-
AUTOSPORT web2
-
-
乗りものニュース1
-
motorsport.com 日本版2
-
motorsport.com 日本版1
-
-
motorsport.com 日本版8
-
AUTOSPORT web0
-
-
-
AUTOCAR JAPAN2
コメントの多い記事
-
日産新社長は開発部門出身!! 日産が生まれ変わるために「すぐやるべきこと」とは?
-
ついに公正取引委員会がトヨタモビリティ東京に対し独禁法違反にあたる えげつない「抱き合わせ販売」をやめるよう警告!! ユーザーの怒りが通じた!!!
-
「WR-V」一部改良に賛否。好意的な声の一方「値上げでは」との批判も…なぜここまで評価が分かれるのか?
-
「車中泊トラブル」なぜ後を絶たない…!? 「ご遠慮ください」案内を無視する人も… 背景にはキャンプと「混同」も? 現状はどうなっている?
-
どんだけ金食い虫なんだよ! 自衛隊に配備目前「F-35戦闘機のコスト」調べてみた 納税者なら知っておくべき?
あなたにおすすめのサービス
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
新車見積りサービス
店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!







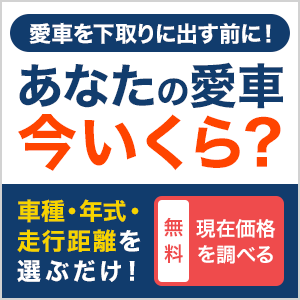
みんなのコメント