170馬力と圧巻デザインの衝撃! 初代ソアラの真実と知られざる秘話
「伝説の名車」と呼ばれるクルマがある。時の流れとともに、その真の姿は徐々に曖昧になり、靄(もや)がかかって実像が見えにくくなる。ゆえに伝説は、より伝説と化していく。
そんな伝説の名車の真実と、現在のありようを明らかにしていくのが、この連載の目的だ。ベテラン自動車評論家の清水草一が、往時の体験を振り返りながら、その魅力を語る。
【車名当てクイズ】この名車、迷車、珍車、ご存じですか? 第60回
文/清水草一
写真/トヨタ、ベストカー編集部
[gallink]
■知る人ぞ知る「145馬力の壁」
初代ソアラは1981年にデビュー。フロントグリルに「グリフォン」のエンブレムが装着されていた(写真は後期型)
初代ソアラ。それは、日本車にとって、ひとつの大きな革命だった。今の感覚では理解が難しいと思うが、当時(1980年代初頭)の日本の自動車業界には、見えない壁があった。それは、「145馬力の壁」である。つい近年まで、国産車には「280馬力自主規制」というものが存在したが、145馬力の壁はそんな明確なものではなく、どのメーカーもそれを超えようとしないだけの、不思議な壁だった。
当時の国産車は、2.8Lの大排気量でも、2.0Lターボでも、最高出力は最大で145馬力。それを超えているのはセンチュリー(3.4Lで170馬力)とプレジデント(4.4Lで200馬力)のV8だけ。どちらも基本的にはハイヤー用で、一般人とは無関係だ。
かつてはトヨタ2000GTやスカイラインGT-R(ハコスカ&ケンメリ)が、2.0L直6DOHCで150~160馬力を絞り出していたが、1970年代前半の排ガス規制強化で消滅を余儀なくされ、国産車には145馬力を超えるスペックのクルマが消えていた。1980年に自動車免許を取った私は、「国産車は145馬力が上限で、それ以上は許されないのだろう」と思い込んでいたほどだ。
そんな時代に、突如その壁をぶっ壊す存在が現れた。それが初代ソアラ(1981年2月発売)である。
「ツインカム6 2.8L 170馬力」
その数字は、雷のように私を打った。「こんなクルマを出してもいいのか!?」と思った。当時の日本は、クルマだけでなく、あらゆる分野がさまざまな“きまりごと(学歴や終身雇用など)“でがんじがらめで、それを破ることはまずあり得ない社会だったから、この掟破りは衝撃だった。
■清潔感あふれる美麗スタイリング
前期型はフェンダーミラーを装着。1981年の日本カー・オブ・ザ・イヤーを獲得している
しかも初代ソアラは、当時の国産車では考えられないほど、スタイリッシュで美しいボディを持っていた。ウエストラインは清潔感あふれる水平基調。フロントウィンドウ、リヤウインドウ、そしてセンターピラーの傾斜は、空中で幾何学的に交差し黄金律を描く。
きわめつけはタイヤの張り出しだ。195/70HR14という贅沢な(当時の感覚です)サイズのタイヤは、前後フェンダーほぼギリギリ。いわゆるツライチに近かった。
当時の国産車の多くは、車体幅に対してトレッド幅が狭く、タイヤがフェンダーの奥に引っ込んでいて、見栄えが非常に悪かった。名車の誉れ高い初代フェアレディZも、ノーマルだとタイヤが奥に引っ込んでいて驚くほどショボい。そんななか、大地を力強く踏ん張るワイドトレッド(前1440mm/後1450mm)で登場した初代ソアラは、それだけでガイシャに見えたくらいである。
初代ソアラから遅れること約半年で登場した2代目セリカXXは、ソアラと同じエンジンを積んでいたが、シャシーベースはセリカ。トレッドもセリカのままだったので(前1430mm/後1390mm)、後輪がフェンダーの内側に引っ込んでいた。断然ソアラの勝ちであった。
こんなにパワフルで、こんなに美しい国産車が登場するなんて信じられない……。ソアラの出現は、当時19歳の青年だった自分にとって、アグネス・ラム(70年代後半に日本を席巻したハワイ出身のグラビアアイドル)の出現と同じくらい衝撃的だった。アグネス・ラムは、当時の日本人の想像を絶する巨乳だったが、ソアラの170馬力のパワーと美しいプロポーションも、日本人の想像を超えていたのである。
■父が購入した初代ソアラはフェラーリ以上?
当時のソアラのCMキャッチコピーは「未体験ゾーン」。スペックと見た目だけで、その言葉は十二分に真実だった。価格は、2800GT(4速AT)で275万円! 今ではフルオプションの軽でもこれくらいの価格になるが、当時は「ものすごく贅沢なお値段」だった。
(ソアラ、すげぇ……。ソアラに乗れたら死んでもいい)
本気でそう思ったものである。個人的な話で恐縮だが、私の場合、それが実現した。父がクルマを買い替えるにあたり、ソアラを強く推したところ、なぜか本当に買ったのだ。それはもう夢のようなクルマだった。有り余るパワー、カッコよすぎるデザイン、光り輝くスーパーホワイト、ゴージャスな室内。世界初のデジタルメーターは未来そのものだった。
20歳の青年だった自分には、「とにかくスゲエ!」ということ以外わからなかったが、自動車評論家の先生が、ドイツ・アウトバーンでスピードリミッターが解除されたソアラに乗り、「デジタルメーターが200km/hを超えた」と語ったのには本当に興奮した。200km/h! それはあの頃の日本人にとって、UFO並みの速度だったのである。
ソアラに対する周囲の反応もすごかった。1980年代、若者のクルマ熱はすさまじく、男子はもちろんのこと、女子もカッコいいクルマに激しく憧れていた。父にソアラを借りて所属サークルの練習に乗り付けると、女子大生たちが「乗せて乗せて~!」と群がった。仕方なく(?)女子4人をソアラに満載し、そこらを一周したほどだ。あんなことは初代ソアラでしか経験していない。フェラーリでも。フェラーリは2名しか乗れないが。
■日本人にとってのゼイタクとは?
写真は1986年に発売された2台目ソアラ。キープコンセプトでの進化を果たす
その後ソアラは、「ハイソカーブームの火付け役」などと呼ばれたが、当時はまだハイソカーという言葉はなかった。そこには、「ハイソサエティぶっているクルマ」と微妙に見下す意味が含まれているが、当時ソアラを見下すような風潮はゼロで、国民を挙げて熱狂していたのである。あえて言えば、初代ソアラは、日本人にとって、「ゼイタクの未体験ゾーン」だった。初代ソアラがバブル経済の入り口で、ここから日本は約10年間、ゼイタクの未体験ゾーンへと突入したのである。
初代ソアラは本来、トヨタブランド高級化の尖兵であり、貿易摩擦で輸出台数が制限されつつあった状況で、利益を出すために開発されたが、結局輸出されることはなく、国内専用モデルで終わった。私が後にショックを受けたのは、欧米では初代ソアラが事前調査段階で「売れない」と判断されたらしい……という事実だった。特にデザインに関しては、まったく理解されなかったという。あんなにカッコいいのに!?
欧米人の感覚では、セリカやセリカXXならスポーツカーとしてアリだが、豪華なパーソナルクーペとしては、初代ソアラはサイズ(5ナンバー)やデザインのボリューム面で役不足だったようだ。その後ソアラは北米進出のため、3代目(1991年発売)でヌメッとした幅広デザインに変身。国内では不評で販売は振るわなかったが、北米ではレクサスSCとしてブランド力アップに貢献した。
初代ソアラの清潔感あふれるクリーンなクーペルックは、日本人の美意識の結晶だったが、そこまでだったと言うべきなのかもしれない。
[gallink]
こんな記事も読まれています
この記事に出てきたクルマ
全国のトヨタ ソアラ中古車一覧 (160件)
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
おすすめのニュース
-
AUTOSPORT web0
-
-
-
ベストカーWeb0
-
Auto Messe Web1
-
-
-
AUTOSPORT web0
-
motorsport.com 日本版0
-
AUTOSPORT web0
愛車管理はマイカーページで!
登録してお得なクーポンを獲得しよう
おすすめのニュース
-
-
motorsport.com 日本版0
-
乗りものニュース0
-
AUTOSPORT web0
-
-
AUTOCAR JAPAN0
-
ベストカーWeb2
-
motorsport.com 日本版0
-
-
AUTOSPORT web0
-
motorsport.com 日本版0
-
AUTOCAR JAPAN0
-
-
-
-
ベストカーWeb3
-
WEB CARTOP1
-
-
-
AUTOSPORT web6
-
-
Auto Messe Web0
-
-
AUTOSPORT web0
-
-
AUTOCAR JAPAN0
-
AUTOCAR JAPAN0
-
-
-
motorsport.com 日本版1
業界ニュースアクセスランキング
-
海上自衛隊が未来の兵器「レールガン」の鮮明な画像を公開! 1隻だけ存在する“激レア艦”に搭載
-
JAFブチギレ!? 「もう限界です!」 ガソリン「暫定税率」“一刻も早い”撤廃を! 目的を失った「当分の間税率」はクルマユーザー“ほぼ全員”が反対意見! SNS投稿で訴え
-
トヨタが中国で激安BEV発売!! 約220万円ってマジか!! 勝ち目はあるか? 日本への逆輸入は……??
-
ダイハツの「タフすぎ“斬新”軽トラ」がスゴかった! 全長3.4mボディに5速MT搭載! 「“カクカク”デザイン」で地上高350mm超えの「マッドマスターC」コンセプトとは
-
高速代が安くなるのに…「ETC 2.0」なぜ普及せず? 「普通のETC」より“良いこと”たくさん! それでもメリットを感じない人が多い意外な理由とは?
あなたにおすすめのサービス
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
新車見積りサービス
店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!







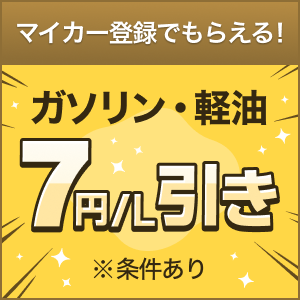
みんなのコメント
ただし金なかったので1カム1GのVX
友人たちにはツインカムじゃねーの!?のバカにされまくりましたが
思い出いっぱい作れたしいい車でした