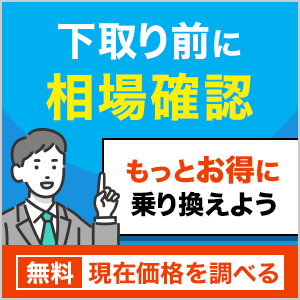- carview!
- 新車カタログ
- BMWアルピナ(BMWALPINA)
- B5
- みんなの質問(解決済み)
- リジットアクスルとトーションビームの違い
BMWアルピナ B5 のみんなの質問
nhb********さん
2012.4.24 03:17
- 回答数:
- 3
- 閲覧数:
- 9,939
リジットアクスルとトーションビームの違い
リジットアクスルとトーションビームってどうちがうんですか?
調べても違いがイマイチわかりません。
ベストアンサーに選ばれた回答
k_f********さん
2012.4.24 03:49
nhbc_scpさんへ
欧州製小型車の後輪に良く見られるトレーリングアームの構造はご存知でしょうか?
リジッドはその名の通りで、左右のタイヤが一本の軸の両端に固定された形です。これに対してトーションビーム式は、トレーリングアームと同様に左右独立な物の、キャンバーの位置決めは左右関連させた物、と考えれば良いでしょう。その為に、左右を繋ぐビームは、捻れを許容する構造・剛さに成っています。
パイプ形状にせずU字形に開口しているのはその為です。
優劣の比較は・・・中々難しいですね。
<追加>
>トーション・ビーム式は,トーアウトになりにくい
この様な不思議な回答が付いていましたので、追加します。
ロール、つまり横gによってトーアウト傾向が出るか出ないかは、設計次第です。実際、トーションビーム構造であっても、ビームを先ずサブフレームに取り付け、そのサブフレームと車体の接合部に大きなブッシュを設け、そのブッシュの動きを制御する事(ゴムの特定方向肉抜きやストッパー金属配置等)で、サスストロークに伴うトーアウトが生じない様な工夫が、実用化への鍵でした。
車体を横方向から透視すれば、トレーリングアームとトーションビームでは、変わり無く、横からの押されに対してトーアウトが生じる事が解る筈です。から、一度サブフレームに付け、その車体への取付スパンを前後に長く設定し、後ろbushは硬くして、横gで前側が押し込まれてトーインに成る・・・様に作られたのです。(今はもっと沢山バリエーションが出てますし、パナールロッド or ラテラルリンク
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E5%BC%8F%E3%82%B5%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
を使う物も増えて来た)
リジット式では、リンクの配置によってその傾向を調整する事が、昔のRX-7(SC22)の時代に広告にも使われていました。(5リンク)
・ ・ ・
その昔、ランチャ フルビアという、とても良く出来たFF車が在りました。あの、ローバーminiが一世を風靡していた時期でしたが、あちらとは違って落ち着いた操縦性は、世界の模範たる仕上がりでした。
その後軸は、リジット。(時代が時代ですから)
但し、懸架していた板バネの前後長は非常に長く、トー剛性の確保と同時に、ストロークに伴うジオメトリー変化を抑えた、大変秀逸な物でした。ストローク自体も長く取れていましたし。(これが大事。FFでもリバウンドストロークを使い切った途端にスピン挙動に入る)
今の基準で考えると、板バネの層間摩擦による振動の伝達は排除すべき物ですし、リジット構造によって、片輪のみ乗り上げの際の、両方へ衝撃が伝わる事も排除すべき用件です。設置スペースも広い。
今に再現するにはどうしたら良いか? タイヤも大幅に進歩して、走行ペースも大いに上がった今、どの様な構造にすべきか。
その、メーカーが量産で、FF車の後軸構造として考えた場合に、トーションビームが一つの最適解であった、と言う事なのです。
質問者からのお礼コメント
2012.5.1 00:12
みなさん回答ありがとうございます!
理解したような気がします^^;
BAは最初に回答されたk_fzr1000さんにさせていただきます<(_ _)>
その他の回答 (2件)
-
tie********さん
2012.4.30 20:18
リジッドアクスルは大分類で
リジッドアクスルの一種としてトーションビームがあります
リジッドアクスル式として他には5リンク式、リーフリジッド式などがあります
大分類としては車軸(リジッド)懸架式と独立懸架式に分類できます
-
e60********さん
2012.4.24 08:55
●リジッドアクスル と トーション・ビーム式の違いは?
リジッドアクスル = 左右輪をつなぐ「アクスル(車軸)」があります。このため右輪があるキャンバ角(後方からみてのタイヤの傾き)になると,左輪はその逆のキャンバ角になります。また右輪がバウンド(タイヤが車体に近づく方向の上下動)になると,左輪もバウンドになります。
トーション・ビーム式 = 左右輪をつなぐ「弾性体(=トーション・ビーム=ねじれるはり)」があります。これによりリジッドアクスルほどではないのですが,左右のキャンバ角や上下動の動きが規制されます。
●リジッドアクスルのメリットは?
左右輪をほぼ完全な剛体でつないでいるため,オフロードのように車輪に大きな入力があるときでも,タイヤをしっかり支えることができます。このためトラックやオフロード車にしばしば使われます。乗用車でも30年くらい前までは使われていましたが,最近はほとんど使われていません。
●トーション・ビーム式とは?
ここでは,いわゆる独立懸架と比較してみましょう。
独立懸架とは,左右輪が別の上下動をできるサスペンションという意味です。上下動が別々にできると,道路の凹凸が左右で異なっていても対応できます。ところが最近のFF駆動車は,独立懸架よりトーション・ビーム式が使われています。どうしてでしょうか?
●独立懸架の問題点とは?
左右で異なる上下動ができる独立懸架より,左右で関連した動きをするトーション・ビーム式が使われるのはどうしてでしょうか?
20年くらい前までは,後輪の独立懸架としてセミ・トレーリング式がよく使われていました。左右上下動を分離できるのは良いのですが,旋回時,タイヤにかかる力で,左右輪を上から見ると,「ガニ股」になるのです。これを「トー・アウト」といいます。旋回の外輪が旋回の外側を向くため,車体後方が外側に動くことになり,旋回が安定しなくなります。
この問題があるため,セミ・トレーリング式の独立懸架を使うより,「半独立懸架」のトーション・ビーム式が望ましいということになりました。
●トーション・ビーム式のメリットは?
トーション・ビーム式は,左右の上下動で関連をもつデメリットがあるものの,下記のメリットがあります。
・トー・アウトになりにくい … 旋回が安定
・部品点数が少ない … コストが安い
・サスペンションの上部のスペースが広い … 燃料タンクなどのスペース確保が容易
これらのメリットがあるため,現在のFF駆動車の大半がトーション・ビーム式を使っています。
●欧州車は?
日本では,ヴェルファイアのような大型のミニバンまでリヤ・サスペンションにトーション・ビーム式を使っています。しかし欧州では,VWゴルフやBMWミニのようにトーション・ビーム式ではなく,ダブルウィッシュボーン式をベースにしたマルチリンク式を採用した車種もあります。
ちなみに,FF駆動車にトーション・ビーム式を広めたのは,初代のVWゴルフです。
●まとめると
リジッドアクスルにくらべてトーション・ビーム式は,上下動の追随が良くなり,タイヤの接地性が良いので,安定した走行が実現します。また古いタイプの独立懸架にくらべてトーション・ビーム式は,トーアウトになりにくいので,旋回時,安定した走行が可能になります。これにより最上の独立懸架より特性は悪いものの,コストメリットや部品点数が少ないことで,いろいろなメリットが出てきます。
簡単ですが,ご参考になれば幸いです。
「自動車」カテゴリとデータを共有しています。
あわせて知りたい
-
整備士の方々に質問です。ボルボ XC60 B5 エンジンのドライブベルト交換サイクルは何万kmで、交換の際にはどこをどうやってテンションを緩めて交換しますか? また、テンショナーは同時交換ですか? 特
2024.11.17
回答受付終了- 回答数:
- 1
- 閲覧数:
- 40
-
ボルボ XC40 XC60 XC90などの b4 B5 B6エンジンのISGMベルトの交換方法は? ユーチューブなどのリンクでも良いです。
2024.11.13
回答受付終了- 回答数:
- 1
- 閲覧数:
- 29
-
- 中古車本体価格
-
258.8 万円 〜 1650.0 万円
-
- 新車価格(税込)
-
1898.0 万円 〜 1939.0 万円
B5を見た人はこんな車と比較しています
BMWアルピナ B5 についてもっと詳しく
- 似たタイプの車種を探す
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。
ログイン
BMWアルピナ B5のみんなの質問ランキング
-
デミオ スカイアクティブD ディーゼルは車業界の人によると故障が怖くて扱えないしろものだそうですが、ホンダのリコールよりやばそうでしょうか? http://blog.goo.ne.jp/cari...
2015.5.15
解決済み- 回答数:
- 5
- 閲覧数:
- 100,261
-
ユンボの、油圧シリンダーのパッキンからオイルが漏れています。 ヤンマーBH-B5、0.2㎥ のブームを動作する油圧シリンダーのパッキンからのオイル漏れです。 部品があれば、素人でも直せるでしょ...
2010.12.7
解決済み- 回答数:
- 3
- 閲覧数:
- 30,474
-
零戦て、アメリカの戦闘機より運動性がよくて小回りが利くってなってるのに、どうしてそれがアメリカの戦闘機に後ろから撃たれて墜ちるんですか? 戦闘機の本にアメリカのどの戦闘機よりも零戦は運動性がよく...
2018.6.27
解決済み- 回答数:
- 24
- 閲覧数:
- 420
-
近くの自転車屋さんに頼んだら1万で組み立てるよと言われ高すぎるので、自分でクロスバイクを組み立てようと考えています。 組み立てるのは初めてで説明書を見て頑張ります! 組み立てる時の注意点などあり...
2022.3.8
解決済み- 回答数:
- 21
- 閲覧数:
- 2,784
-
今回のよしさんのバイク事故は若者でも大型バイクを教習所で取れるようになっていなければ起きなかった事故でしょうか? https://news.yahoo.co.jp/articles/ddee15...
2022.11.8
回答受付終了- 回答数:
- 19
- 閲覧数:
- 422
-
車のバッテリーがあがった時に使用するケーブルが欲しいです。 こないだ彼女とドライブに行ったんですが、その時に車のバッテリーがあがったんです。 車の知識が全然なく、ケーブルの存在も知らずにJAFに...
2020.12.16
解決済み- 回答数:
- 19
- 閲覧数:
- 123
あなたにおすすめのサービス
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!