【黎明期のDOHC】ホンダ CB450のバルブスプリング「トーションバースプリング」の挑戦
吸排気バルブの動きを司るバネ=バルブスプリング
二輪車をはじめ現在市販される一般公道用のエンジンは、その多くがレシプロの4サイクルを採用しています。ピストンの上昇と下降に合わせ、カムシャフトにより適時吸排気バルブを開閉して吸気・圧縮・燃焼・排気を繰り返すシステムです。
CT110などに搭載された副変速機ってどんな仕組み? ハンターカブの代名詞といえるメカニズムを分解!!
この基本動作が、車両を走らせるための動力を生み出す源です。エンジンの排気量や仕様にもよりますが、アイドリングでも1分間におよそ300~700回ほどこのサイクルを繰り返しています。まさに目にも止まらぬ速さで運動を続けていますね。
これを実現するための、非常に重要な部品のひとつが「バルブスプリング」です。バルブスプリングは1分間に数百回から、時に数千回の圧縮と伸長を繰り返すため、非常に過酷な条件に置かれる部品であり、追従性はもちろん高い耐久性が求められます。
そんな場所に、「ばね」としてだれもが想像する「コイルスプリング」が多く使われています。これは何十年も前から変わりません。古くはヘアピン型スプリングを採用したものもありましたし、ドゥカティのように開閉の作動をスプリングに頼らない機構もあります(デスモドロミック)。
また近年ではレースマシンを中心に、ニューマチックバルブと呼ばれる圧縮エアでバルブを閉じる機構もありますが、市販車エンジンに使われる主流はあくまでシンプルなコイルスプリングとなっています。
1965年に登場したホンダCB450はDOHC機構だけでなく、バルブスプリングも独特だった
さて、そんなコイルスプリングが大活躍する世界に、かつて独特の機構で斬り込みをかけたモーターサイクルがあったことをご存じでしょうか。
それは、ホンダが1965年に発売したCB450です。国内では「クジラ」と呼ばれ、海外では「キャメルバック(ラクダの背中)」と呼ばれたりする、独特のタンク形状が印象的なモデルですね。空冷の4サイクル並列2気筒で、実排気量444ccから43psを発揮しました。
このCB450のエンジン、なんとバルブスプリングに一般的なコイル型ではなく「トーションバー」を採用しています。「バー(棒)」を「トーション(ひねる)」する。すなわち、金属棒にひねる力を加え、その戻る力を利用することでスプリングとして機能させるものです。
フォルクスワーゲン・ビートル(旧)やトヨタのハイエースなどなど、四輪車のサスペンション用としてはしばしば採用されるこのスプリングですが、条件がはるかに厳しいエンジンのバルブスプリングとして使われた例は極めてまれです。レース用は別として、市販車としてはフランスのパナールが販売していた水平対向エンジン(四輪車)、そしてこのCB450系くらいでしょうか。
ここでひとまず、スプリングという機械部品が機能する原理を見てみましょう。前提として、金属の弾性を利用していることはわかると思います。コイルスプリングも伸ばしてみれば金属棒ですし、ある一点で見るとひねられることで全体が縮み(または伸び)ますから、コイルスプリングもトーションバースプリングも同じ原理で機能していることがわかります。
それでもなお、CB450がややこしい機構を採用した理由とは……?
果たして、この特異なバルブスプリングにはどんなメリットがあったのでしょうか?
1960年代前半当時、ホンダはマン島TTをはじめとした世界のレースシーンで、2万回転も回る4サイクル多気筒エンジンで暴れまわっていました。高回転化・高出力化のため、早くから気筒あたり吸排気各2本の「4バルブ」を採用しており、GPへの挑戦開始からわずかな期間で世界レベルの戦闘力を得ていました。
これらで得た経験から、市販の高性能4サイクルモデルを次々に生み出していったわけですが、大型車市場への参入はまだであり、世界一を目指すメーカーとしてそこの開拓は必須事項でした。
そこで1963年に開発が始められたのがコード「103」、のちのCB450E(エンジンの意)です。ただ、市販エンジンですからレーサーと同じようなレイアウトや材料を採用するのは不可能です。どうしてもバルブ1本あたりが重くなる、2気筒2バルブの大型車でいかに高回転に対応するか……。ホンダの技術者は苦悩しました。
当時はまだ、このクラスの重いバルブに対応できる、量産市販車向きのコイルスプリング材が存在しなかったためです。
このため幾多の検討が重ねられたことと想像できますが、最終的に採用されたのがトーションバーバルブスプリングだったのです。
CB450のサービスマニュアルには、「固有振動数が高く設計でき、サージングがなくなり……」との記載が見られます。バルブ機構におけるサージングとは、カムによるバルブの開閉動作とスプリングの固有振動数が重なったとき、異常な振動を起こしバルブの開閉がうまく行われなくなり密閉性が失われる状態を言います。
当然、エンジンの出力は落ちてしまいます。ここで補足が必要となりますが、実際に開発で問題になったのはサージングではなく、バルブジャンプ(カムの山に乗り上げた勢いで跳ねる現象)とバルブバウンス(バルブシートに叩きつけられた後に跳ねる現象)だったと開発者は語っています。
いずれにせよ、エンジンの作動にとっては害でしかありませんでした。なお、コイルスプリングは内外の二重スプリングを設けることでサージングなどに対処しています。
CB450のエンジンは、吸排気でそれぞれ独立したカムシャフトを持つダブルオーバーヘッドカム機構(DOHC)、ボア70mm×ストローク57.8mmのショートストローク設定などを組み合わせ、450ccツインながらレッドゾーンが9500rpmからという高回転型エンジンに仕上げられていました(モデルチェンジ版のCB450K1は9700rpmから)。
これは、当時の大型車(450ccでも十分に大型車に分類された時代です)としては驚くべきスペックで、最高速は実に180km/hに到達していました。これを実現させた立役者が、トーションバーバルブスプリングだったというわけです。
しかしながら、主要な市場であるアメリカではトルク型のエンジンが好まれ、繊細で「回せば速い」CB450は好まれず、成功作とはなりませんでしたが……。
この経験は4年後に発売されるCB750Fourに存分に生かされることとなりました。
トーションバースプリングが現在主流ではない理由
残念(?)なことに、トーションバースプリングをバルブスプリングとして採用するメリットは、現代においてもはや「ない」と言えるでしょう。理由は明確。材料や加工の技術が進み、寸法や強さの設定および変更の容易なことに加え、さらにはコストの点でコイルスプリングに勝るものはないからです。
今や、クラシックレースの世界ではCB450エンジンのコイルスプリング化がポピュラーであり、ついでに触れると、さらに古いヘアピンスプリング車もコイルスプリング化することが珍しくないくらいです。
4サイクルエンジンの時代が続く限り、コイルスプリングの独壇場に変わりはない……と言えるのかもしれません。
レポート●神山雅道 写真●八重洲出版
こんな記事も読まれています
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
おすすめのニュース
-
-
AUTOCAR JAPAN0
-
AUTOSPORT web0
-
AUTOSPORT web4
-
-
-
-
motorsport.com 日本版0
-
ベストカーWeb0
-
愛車管理はマイカーページで!
登録してお得なクーポンを獲得しよう
おすすめのニュース
-
GQ JAPAN0
-
motorsport.com 日本版4
-
AUTOSPORT web0
-
AUTOCAR JAPAN0
-
AUTOSPORT web0
-
-
motorsport.com 日本版0
-
AUTOSPORT web4
-
-
-
-
AUTOCAR JAPAN0
-
-
-
-
Webモーターマガジン3
-
AUTOSPORT web1
-
AUTOCAR JAPAN0
-
Auto Prove2
-
motorsport.com 日本版0
-
AUTOSPORT web0
-
-
Auto Prove0
-
WEB CARTOP5
-
Auto Prove0
-
motorsport.com 日本版12
-
-
Auto Prove1
-
GQ JAPAN1
-
業界ニュースアクセスランキング
-
660ccのスバル「小さな高級車」に反響殺到!「意外と安い」「上質な軽自動車ってサイコー!」の声も! 快適すぎる“超豪華インテリア”採用した「オトナの軽自動車」ルクラに大注目!
-
「ズラリと並んだ護衛艦」が一斉に出港!“壮観すぎる光景”を捉えた写真を海上自衛隊が公開
-
「ホテルが見つからない」 大阪万博またピンチ! 稼働率全国トップの80%超え、宿泊費2~3倍高騰も! 宿泊難民続出で、兵庫県へ“避難”勧告の現実か
-
「大阪と奈良を直結するJR特急」が大変化!ついに“専用車両”デビュー 側面はド派手
-
ホンダが世界初の「新型エンジン」公開で反響殺到! 伝統の「赤ヘッド」&“V型3気筒”に「面白そう!」「これでこそホンダ」と称賛の声! 超進化した新型「すごいエンジン」に大注目!
コメントの多い記事
-
ついにエルグランドが2026年フルモデルチェンジ。第3世代e-POWER搭載で低燃費実現へ
-
【震えて待て】アルファード中古価格の下落が止まらない。ローン終了と増産で次なる下値待ったなし
-
まもなく発売される「新型プレリュード」! ほぼ市販モデルのインテリアをじっくり観察したぞ!!
-
スバル新型「フォレスター」発表に反響殺到!?「歴代で一番好き」「間違いなくヒット」の声も! ゴツいタフ顔&強化ハイブリッドで別次元に!? どう変化したのか
-
「ホテルが見つからない」 大阪万博またピンチ! 稼働率全国トップの80%超え、宿泊費2~3倍高騰も! 宿泊難民続出で、兵庫県へ“避難”勧告の現実か
あなたにおすすめのサービス
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
新車見積りサービス
店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!







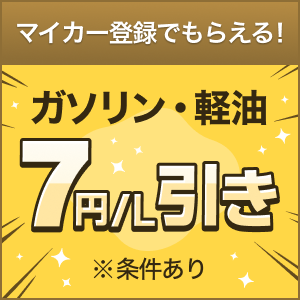
みんなのコメント
ただし
>>当時の大型車(450ccでも十分に大型車に分類された時代です)
の箇所にちょっとだけひっかかりました。
当時の251cc以上の法区分上の名称は「二輪」で、一般の呼称は「重量車」です。
「大型車」は中免制度導入以降に発生した名称です。
老婆心ながら重箱の隅をつつかせていただきます。
それはさておき
当時のパブリックイメージで「重量車」といえば、まずW1。次いでこのCB450、ちょっと差がついてXS-1、すごく差がついてT500といったところだったと思います。「DOHC」にさほどアドバンテージはなかったように記憶しています。