ついに保有か「日の丸病院船」政府が考える2つの役割とは? 自衛隊での前例も
民間船舶を活用しながら整備される「病院船」
政府は2025年3月18日、大規模な災害が発生した時に被災者の輸送や、医療の提供を行う船舶(医療提供船舶)の整備計画を閣議決定しました。
【広~い浴室も完備!】これがフェリー「はくおう」の船内です(写真)
「医療提供船舶」の用途としては、傷病者を被災地外の医療機関へ搬送する「脱出船」と、被災地付近の港に接岸し船内で救護活動を実施する「救護船」の2つを想定。当面は民間の船会社の協力を得てカーフェリーなど既存の船舶を「民間協力船」として活用しつつ、将来的に国などが専用の「病院船」を保有することを目指すとしています。
石破 茂首相は、総理官邸で開かれた船舶活用医療推進本部の会議で、「この計画は南海トラフ地震や首都直下型地震などの大規模災害の発生時に、陸上の医療機能を補完し、船舶を活用した医療を提供するために必要な措置を定めるものだ」と述べ、関係閣僚に向けて2026年1月までに船舶を活用した医療提供の体制を整備することを指示しました。
大規模災害が発生した際、被災地の医療現場では、医療資源の不足などにより対応困難な傷病者が多数発生し、陸上の医療機能がひっ迫することが予測されています。
政府は大量の人員や物資を積載して海上を移動し、陸上インフラに頼らず自己完結的な活動ができる船舶に着目した模様です。特にカーフェリー型の船舶は、トラックが入れる車両甲板や、宿泊が可能な客室、食料の保管スペース、広い船内に電力を供給する発電機などのライフライン供給設備などが備えられていることから、医療活動の拠点として活用できると見込まれています。
それでは、改めて前出の「脱出船」と「救護船」について詳しく見ていきましょう。
「脱出船」と「救護船」それぞれの求められる役割とは?
まず「脱出船」は被災した傷病者に必要な医療を提供しつつ、被災地外の医療機関へ搬送することに使用します。
自動車や航空機と比べて広いスペースを持つ船舶は多くの傷病者を収容することが可能で、これにより被災地における医療機能のひっ迫を緩和することができます。さらに医療機関が物理的な被害を受けることも想定しており、傷病者を被災地外の医療機関に搬送することで、十分な医療を提供できるようにすることも狙いのひとつです。
一方「救護船」は被災地付近の港に接岸し、一定期間、被災地の傷病者に対して救護活動を行います。大規模災害時には既存の医療機関がダメージを受け、多数の傷病者に対応しきれなくなるため、船内に発電設備などを持つ船舶が傷病者を受け入れ、救護活動を実施していく予定です。
対象となる傷病者については、被災を原因とする傷病者だけでなく、災害発生以前からの入院患者など、被災を原因としない傷病者も含まれています。さらに時間経過とともに変わる被災地のニーズに対応し、生活物資の輸送や休憩所、支援要員の宿泊施設、要配慮者に対する福祉サービス提供場所など多目的な利用も考えられています。
2024年6月に施行された「船舶活用医療推進法」では、国や独立行政法人などが専用の船舶を保有することが明記されていますが、当面のあいだは国内で定期航路を運航している民間船舶や防衛省が確保しているPFI船舶を使用する方針です。
「民間協力船」については、定期航路に就航していることも考慮し、保有・運航する船社と所管庁との間で、医療提供船舶として活用する際の条件などを定めた協定を事前に締結します。PFI船舶については、防衛・警備の任務を阻害するリスクを回避することを前提に、防衛省と十分に協議・調整を行うとしています
すでに能登半島地震で活用の前例あり!
「民間協力船」に乗船する医師や看護師といった医療従事者は、陸上の医療機能との連携の観点から、被災都道府県の「保健医療福祉調整本部」がDMAT(災害派遣医療チーム)、日本赤十字社などの各種保健医療活動チームと調整し、確保します。
ただ、民間協力船を活用した医療提供は新たな業務となるため、当面の間は政府が医療従事者の確保などについて、同本部を全面的に支援するとのこと。医薬品や医療資器材は、DMATなどが保有し、災害時に持参するもののほか、日本赤十字社が保有するdERU(国内型緊急対応ユニット)の医薬品・医療資器材を活用します。
船上で良好な通信環境が確保できるよう、衛星電話などの資器材については、政府が確保し保管することを明記。さらに船内という特殊な空間で医療を提供することとを考慮し、陸上の医療機関や救護所では使用されていない資器材を、「民間協力船」向けに新たに開発・確保することも必要であると記されています。
PFI船舶については、防衛省がフェリー「ナッチャンWorld」や「はくおう」で一定の実績を残しています。2024年1月に起きた能登半島地震では、「はくおう」が七尾港へ派遣され、船内に休養施設を開設し、被災者の受け入れを実施しています。
「はくおう」は元々、カーフェリーだったため、船内に宿泊施設や入浴施設、飲食施設などを備えています。それらを活用して被災者に癒しを与えたのです。こうした活動は、前述した「救護船」の内容に近いものだと言えるでしょう。
そのような前例がすでにあったからこそ、政府は「医療提供船舶」、いわゆる病院船の運用について具体的に動き出したと言えるのかもしれません。
こんな記事も読まれています
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
おすすめのニュース
-
グーネット1
-
-
motorsport.com 日本版1
-
AUTOSPORT web3
-
-
motorsport.com 日本版1
-
motorsport.com 日本版0
-
-
-
愛車管理はマイカーページで!
登録してお得なクーポンを獲得しよう
おすすめのニュース
-
-
ベストカーWeb0
-
WEB CARTOP14
-
-
-
バイクのニュース4
-
Merkmal3
-
motorsport.com 日本版0
-
-
AUTOSPORT web1
-
-
-
AUTOCAR JAPAN0
-
AUTOSPORT web0
-
-
-
-
-
-
-
-
motorsport.com 日本版7
-
-
motorsport.com 日本版1
-
motorsport.com 日本版13
-
-
AUTOCAR JAPAN0
-
AUTOCAR JAPAN0
-
AUTOSPORT web8
-
業界ニュースアクセスランキング
-
新型エルグランドはアルファード超えの声多し!! 2台を比べるとオラオラ顔じゃない!!! アルファード&ヴェルファイアをやっちゃえ!!!
-
機体空中分解で110人死亡! さらに130億円横領もあった最悪航空会社、台湾「ファーイースタン航空」をご存じか
-
日産が「新型エルグランド」初公開! 豪華「4人乗り仕様」もアリ? 高効率エンジン搭載? 15年ぶり全面刷新の「元祖“高級ミニバン”」どんなモデルに?
-
JALにスゴいサービス出現! 「2路線限定で超安く”当日旅客便飛び乗り”OK」なぜ? 背景には”切実な事情”か
-
【ランクルミニ2025年登場へ】価格・性能・納期は?売れる理由と不安要素を徹底予想!!
あなたにおすすめのサービス
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
新車見積りサービス
店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!







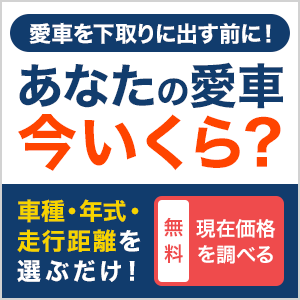
みんなのコメント
①普段から数百名という医療スタッフをどうやって確保し港に集結させるのか?
②津波などで港が使えないと効率の悪いヘリ輸送になるが、船のヘリポートは1~2機分しかない。
③だったらそのヘリで被災地域の外の医療機関に運んだほうが遥かに効率がいいし、医療体制も充実している。
・・・ということで実現しなかった。
そもそも病院船は戦場や派遣した国の医療体制が整っていないなどヘリで飛べる範囲の医療機関が期待できない場合に活躍する「外征型」の装備。日本国内ならヘリや車で被災地外に運んだほうが遥かにたくさんの医療機関に診てもらうことが出来る。
また密閉空間なども問題でアメリカの病院船がコロナの時に投入されたが、艦内で感染が広まって全く役に立たなかった。
車両なら内陸部でも活躍出来るし。
海外で災害支援も行える。
専用船は非合理だと思う。