V型4気筒にモノコックボディ ランチア・ラムダ 100年前の革命児 体験を一変 前編
モノコック構造とV型4気筒のラムダ
100年前のランチアは、現代の革新的なモデルとは比べ物にならないインパクトを持っていた。1922年のパリ・モーターショーで発表されたラムダは、それまでの自動車に対する概念を書き改めたといってもいい。
【画像】V型4気筒にモノコックボディ ランチア・ラムダ 同時代のクラシックと写真で比較 全120枚
エンジンとサスペンション、数名の乗員、走行時の負荷を一手に受け止めたモノコック構造は、セパレートシャシー構造が一般的だった時代の革命児だった。世界初の、独立懸架式となるフロント・サスペンションも同様だろう。
前後のアクスルにはブレーキも組まれていた。エンジンは高性能なオーバーヘッドカムのV型4気筒。他に類を見ないパッケージングによって、1920年代のドライビング体験を一変させた。
確かに1913年のラゴンダは、オールスチール製のモノコックシャシーを採用していた。1899年には、デイムラーがコンパクトなV型エンジンを開発していた。だがランチアは、これらを1台に融合し完成させていた。
ロンドンの西、ハートレー・ウィントニーの町に拠点を置くフェニックス・グリーン・ガレージ社は、そんな歴史的なクラシックカー・オーナーが集まる場所。定期的にランチア・ラムダを集めたミーティングも開かれている。
そこで今回は、ラムダ・エイト・シリーズ・サルーンとトルピード・ツアラーという2台へ試乗する機会を得た。さらに、ヒストリック・モーターカー・ワークショップ社へ場所を移し、フォー・シリーズも体験させていただいた。
軽さと強さが走行性能に貢献する
同一モデルのシリーズ違いは、変化が限定的な場合も多い。いわゆるマイナーチェンジでの違いに近い。だが、前期型と後期型へ大きく分けられるフォー・シリーズとエイト・シリーズでは差が小さくない。9年でナイン・シリーズまで進化を遂げている。
デザイナーのピニン・ファリーナ氏は、ブランド創業者のヴィンチェンツォ・ランチア氏が大西洋を渡る船の構造に影響を受けたと、後に話している。レーシングドライバーでもあった彼は、軽さと強さが走行性能に大きく貢献することを理解していた。
1910年のランチアのカタログには、次のように記されてる。「重さは強さとは異なります。不完全な設計や安価な材料が導くことも珍しくありません。軽く速く、頼れる自動車の強みは過小評価できません」
ラムダが誕生する4年前、1918年にランチアはモノコックボディ構造の特許を申請した。プロペラシャフトが中央を走るトランスミッション・トンネルを備え、その両側には乗員の足もとへ余裕をもたせる窪みが与えられていた。
このボディは、剛性シェルと特許図面では呼ばれていた。アクスルより下側へ空間を広げ、強度を増す事が可能だとも記されている。
この事実を受け、「興味深い特許です。安全性やロードホールディング性、サスペンション設計の改善に効果的なだけでなく、重量の大幅な削減も期待できます」。と、当時のAUTOCARはラムダを予見したように紙面で紹介している。
前後のブレーキに独立懸架式サス
その頃のランチアで主任技術者を務めていたのが、バッティスタ・フェルチェット氏。革新的な設計の旗振り役となった。
100年前の自動車業界では、フロントタイヤ側のブレーキに懐疑的な考えを持つ技術者が多かった。ベントレーを創業した、WO.ベントレー氏も否定的だったという。
それに対し、フェルチェットは試作車でフロント・ブレーキだけを効かせ、安定性に問題がないことを証明。リア側のブレーキも機能させると、一層効果的であることも確認した。
独立懸架式のフロント・サスペンションは、ヴィンチェンツォも望ましいとは考えていなかった、リジットアクスルに対する回答だった。フェルチェットは14種類の設計を試したが、左右個別に掛かる負荷が課題になった。
最終的に、ダンパー内のオイルの流れを制御するバルブを備え、固定されたストラットをハブが上下するスライディングピラー機構を開発。ランチアの特長として40年間も採用されることになった。
V型4気筒エンジンも同社独自の設計。担当したのはプリミティーヴォ・ロッコ氏とアウグスト・カンタリーニ氏という2人で、ブロックの長さが短く操縦性の向上に繋がった。
このユニットも、1976年にフルビアが製造を終えるまでランチアの特長として受け継がれた。シリンダーを微妙にずらして並べることで小さくし、エンジンルーム内からトランスミッションへアクセスすることも可能だった。
ラムダでは、試作を繰り返しバンク角を13.6度に設定。2119ccから当時としては優秀な48ps/3250rpmを発揮させている。
当初はオープンのトルピード・ツアラーのみ
他方、スタイリングも注目に値する。プロトタイプでは丸みを帯びたツアラーボディだったが、最終的には平面的でスクエアなデザインに帰結している。当時の流行でもあった。
セパレートシャシー構造であれば、その頃は一般的だったコーチビルダーやカロッツエリアによるボディの架装が可能だった。しかし、モノコック構造はシャシーと一体なため、当初はランチアで製造されるボディへ選択肢が限定されていた。
ファイブ・シリーズまでは、オープンボディのトルピード・ツアラーのみが作られている。クロスとウッドで仕立てられたバロン・スモンタービレ・ハードトップが用意され、乗員を風雨から守った。
1922年から1931年まで9シリーズ作られたラムダは、モデルチェンジと呼べるほどではなかったが、進化を重ねた。サイズが大きくなり、エンジンの出力も高められつつ、当初のテンプレートは最後まで保たれた。
初期のフォー・シリーズまでの違いは小さく、ファイブ・シリーズからは4速マニュアルが搭載されている。だが最も大きなステップは、1925年のシックス・シリーズだろう。
オプションとして、320mm延長した3420mmのロングホイールベース版の選択が可能になっている。最大で6名乗車が可能なボディが用意され、ドラムブレーキも制動力が強化された。
当初、ラムダのボディの製造を担っていたのはフィアットだったが、ロングボディの誕生を機に契約を終了。直後は職人によるハンドビルドでまかなわれたが、アルビノ・アーリ社に生産が移管されている。
この続きは後編にて。
こんな記事も読まれています
この記事に出てきたクルマ
全国のデイムラー デイムラー中古車一覧 (35件)
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
おすすめのニュース
-
-
-
-
-
-
-
-
-
motorsport.com 日本版0
-
Webモーターマガジン0
愛車管理はマイカーページで!
登録してお得なクーポンを獲得しよう
おすすめのニュース
-
-
-
AutoBild Japan0
-
-
-
AUTOCAR JAPAN1
-
-
GQ JAPAN0
-
-
-
GQ JAPAN0
-
ベストカーWeb0
-
-
-
-
-
-
-
AUTOCAR JAPAN0
-
-
Auto Prove0
-
-
-
バイクブロス1
-
-
Auto Prove0
-
-
Auto Prove0
-
日刊自動車新聞0
-
業界ニュースアクセスランキング
-
「1万円払って」「ナンバー控えた」でSNS炎上! 大阪のドラッグストア「共用駐車場」が招いた誤爆トラブル、なぜ起きた? その裏にあった常識ズレの正体とは
-
「ロンブー田村淳」が約1400万円の「高級車」を納車! 家庭用エアコン&電動昇降ベッド搭載の「めちゃ贅沢」な仕様の「ビッグモデル」!「今まで見た中で一番欲しい」「最高にかっこいい」と反響大な「キャンピングカー」とは
-
1.5リッターエンジンで「300馬力」オーバーに驚きの声!「パワー凄すぎ…」「こんなの初めて」とのコメントも! 超パワフルな“小さな高級車”新「レンジローバー イヴォーク」とは!
-
突然…「ゴールド免許」とサヨウナラ…なぜ? 無事故・無違反なのに「ブルー免許」に変更された? 「更新、気づかなかった…」は自業自得?
-
前代未聞の「ETC障害」で1台ずつ「お金払ってくださいね」の情けなさ レーンも料金所も「もう不要」の海外
コメントの多い記事
-
【高価なのがネックに】新型「クラウンエステート」受注殺到とはならず。ただし納期は今後伸びる可能性大
-
18年の歴史に幕! 日産「GT-R」生産終了へ 3000万円「最後のGT-R」はもう買えない… 匠“手組みエンジン”×高性能パーツ採用の「2025年モデル」買えたのは“幸運な人”だった
-
「広末でーす!」はヤバい行為だった!? サービスエリアで「知らない人」に声をかけるべきじゃない理由! 多様性時代で求められる新たな規範とは
-
「カーナビって必要? スマホナビで充分?」実際どちらが「正解」なのか 思わぬ「デメリット」も存在!? 調査では“驚きの実態”も
-
最近「光るナンバー」を見かけないワケ! LED、安全装備、若者のクルマ離れ…半世紀の光と影、そして復活への道を考える
この記事に出てきたクルマ
あなたにおすすめのサービス
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
新車見積りサービス
店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!







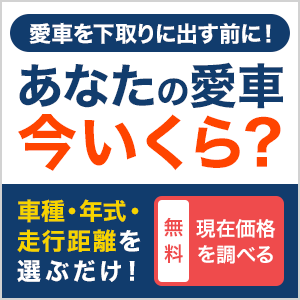
みんなのコメント
迷わずラムダを選ぶ。一生分のタイヤをそえて…
小林彰太郎