武蔵小杉はなぜ「タワマンだらけの街」になったのか? 住民激増、町内会解散…100年前からの歴史を辿る! 令和の都市開発は成功か失敗か
年2900人流入の都市変貌
2025年3月30日付の『読売新聞』が報じた「武蔵小杉の町内会が解散へ、人口増でも新住民の加入進まず…タワマン管理組合も応じるところなく」という記事が注目を集めた。この記事によると、同エリアの小杉町3丁目町会は解散を決めた。背景には、タワーマンションの急増がある。小杉町3丁目の人口は2004(平成16)年に1851人だったが、2024年には5508人にまで増えた。約3倍の増加だ。
【画像】「えぇぇぇ!」 これが35年前の「武蔵小杉」です! 画像で見る(14枚)
一方で、町会への加入率は激減した。役員の高齢化も進み、町会の運営が困難になった。記事には、
「新築マンションに入居してくる世帯の町内会への参加がなかなか難しい」
「人気の地域なので住民は増え子供も増えているのに、町内会は加入してくれない」
といった声も紹介されている。こうした問題は、武蔵小杉だけに限らない。東京湾岸をはじめ、タワーマンションの建設で人口が急増し、地域の雰囲気が大きく変わった場所は全国に存在する。
しかし、武蔵小杉駅周辺の状況はとくに特異だ。武蔵小杉が属する川崎市中原区の人口は、1999年4月には19万4680人。世帯数は9万1760世帯だった。だが2024年4月には、
・人口:26万6966人(37%増)
・世帯数:14万786世帯(53%増)
にまで増えている。年間でおよそ2891人が増加している計算だ。これは、毎年ひとつの小規模自治体がそっくり引っ越してくるような規模になる。
この急激な人口増の大半は、タワーマンション(タワマン)への入居が原因とみられる。しかも、武蔵小杉駅周辺では今もタワマンの建設が続いている。今後も「タワマン乱立地帯」として成長していく可能性が高い。
では、なぜ武蔵小杉はここまでタワマンだらけの街になったのか。この記事では、その理由を探っていく。
学園都市構想から工業都市への転換
一般に、武蔵小杉がタワーマンション集中エリアとなった理由として、
「工場跡地にまとまった土地があった」
ことが挙げられている。これは事実ではあるが、表面的な理解にすぎない。実は、タワーマンションが計画されるよりはるか前から、武蔵小杉は注目される土地だった。
かつて武蔵小杉は農村地帯だった。その開発が始まったのは昭和に入ってからである・1926(昭和元)年2月、東京横浜電鉄(現在の東急東横線)が、丸子多摩川駅から神奈川駅の間で開通した。しかし、この時点では武蔵小杉付近に駅はなかった。
翌1927年3月、南武鉄道(現在のJR南武線)が開通したが、このときも駅は設けられなかった。同年11月、ようやく南武鉄道が、現在のJR駅付近に「グラウンド前停留場」を、また現在の武蔵小杉駅より北にあたる府中街道と交差するあたりに「武蔵小杉停留場」を開業させた。
東京横浜電鉄は駅の設置こそ見送ったが、沿線の土地分譲や学校誘致に力を入れていた。
・中原高等女学校
・日本医科大学予科
・法政大学予科
などを誘致し、同時に宅地開発も進めていた。この時期、武蔵小杉周辺では学園都市を目指した都市計画が進行していた。
しかし、1930年代に入ると状況が一変する。軍需産業の需要が高まり、工場が南武線沿線に進出を始めた。その結果、当初の計画とは異なり、武蔵小杉は内陸部の工業地帯として開発されていった。
工場や学校が集中したことで、周辺住民から駅設置の要望が高まった。1939年12月、東京横浜電鉄が「工業都市駅」を開業する。場所は、現在の東横線が府中街道と交差するあたりだった。この駅は通勤通学に使われ、1日あたり約1万5000人が利用した。周辺には商店街も発展した。
その後、1944年4月に南武線が国有化され、グラウンド前停留場は武蔵小杉駅に昇格する。1945年6月には、東京横浜電鉄も南武線との交点に武蔵小杉駅を新設した。さらに、1953年3月には工業都市駅が廃止され、現在の武蔵小杉駅へと統合された。
この時点で、2路線が利用できる利便性はすでに注目されていた。『神奈川新聞』1978年9月19日付朝刊の連載「この駅この町」では、次のように記されている。
「両線の交差するという格好の立地を得て人口も急増し、それとともに企業の進出も始まった」
戦前、武蔵小杉は軍需産業を支える工業地帯として栄えた。その後も、2路線が交差する交通の利便性は失われなかった。むしろ戦後になると、川崎市は武蔵小杉に保健所や公民館などの公共施設を次々と建設した。行政の拠点として整備が進められた。
1959年には、武蔵小杉駅前にバスターミナルが整備された。これにより、地域の中心地としての役割はいっそう強まった。
地価3倍超が示す住宅需要
戦後の復興期において、武蔵小杉はすでに首都圏のベッドタウンとして注目されていた。『読売新聞』1956(昭和31)年8月23日付の夕刊では、川崎市中原地区の建築ブームについて詳しく報じている。
記事によると、当時の川崎市では人口50万人突破が目前に迫っていた。市役所が同年1月から8月中旬までに受け付けた住宅の建築許可は約3900戸にのぼった。そのうちの43%が中原地区に集中していた。
住宅の種類はアパートや公営住宅、個人住宅など多岐にわたる。特に個人住宅の増加が顕著だった。記事には「農地は(昨年の)2倍近い早さで減っている」との記述があり、急速に宅地化が進んでいたことがうかがえる。
それと同時に、土地の価値も上昇していた。以下に紹介する記事の一節からは、当時の状況がよく伝わってくる。
「1952、53年ごろの南武線武蔵小杉、中原付近は駅の近所で6~7000円、15分ほど歩いて2000円くらいだったのが、今では同じところがそれぞれ1万円、3500円というところ。昨年住宅公団が7000円ぐらいで買った小杉駅前のアパート用地は今年買えば1万円をはるかに越したろう」
記事では「住宅の建築が市中心部では飽和点に達し、農地を潰して西北部に伸びてきている」と解説されている。この記述から、武蔵小杉の最初のベッドタウン化は、川崎市中心部の人口増にともなって起きた現象だったことがわかる。
1967年になると、武蔵小杉は川崎市でも有数の人口集中エリアに成長していた。『読売新聞』1967年4月13日付朝刊は、「サラリーマンのベッドタウン」として発展する武蔵小杉の姿を報じている。
記事によると、大型スーパーの出店が相次いでいた。それに対抗する形で、地元商店街は団結を強めていた。特に注目すべきは、2路線が交差する武蔵小杉駅周辺に、商店街加盟店舗が170店もあったという点だ。これらの動きは、当時からすでに武蔵小杉がベッドタウンとして大きく発展していたことを物語っている。
その後も武蔵小杉の発展は続いた。『神奈川新聞』1979年12月24日付の「新ショッピング地図」では、
「(川崎市の)真ん中といえば中原区だし、中原区の中心は、この武蔵小杉です」
という声が紹介されている。さらに、川崎市役所が武蔵小杉に“遷都”する計画があるという報道まであった。
これだけ発展と注目を集めた土地だけに、より利便性の高い街を求める声は、かなり早い段階から上がっていたと考えられる。
不況を越えた交通利便性の期待
こうした再開発を求める声に応えたのが、川崎市が1983(昭和58)年に策定した『川崎市都市整備構想(2001かわさきプラン)』である。新川崎駅付近に位置する「新川崎インテリジェントシティ」は、この構想の代表的な成果といえる。
この計画では、市内に複数の都心を分散させる方針が示された。武蔵小杉駅周辺は、新百合ヶ丘駅周辺などと並ぶ重点開発エリアに位置づけられた。この方針を受け、民間も動き始めた。1988年には東急電鉄などが「コアゾーン研究会」を結成し、再開発の取り組みが本格化していった。
当時の武蔵小杉駅周辺は、急増する人口に対して都市基盤が極めて脆弱だった。JR武蔵小杉駅南口には駅前広場すらなく、周囲には幅4mほどの道路しかなかった。そのうえ、一方通行や行き止まりが混在し、幹線道路へのアクセスも乏しかった。東急東横線との接続も不十分だった。
行政の打ち出した拠点化の方針を実現するには、都市の大規模な改造が不可欠だった。幸いにも、計画が本格化した時期に、
「工場跡地など大規模な企業所有地の放出」
が相次いだ。これは武蔵小杉にとって大きな追い風となった。しかし、すべてが順調だったわけではない。1994(平成6)年12月9日付『朝日新聞』朝刊は、「ビル造って店子入らず」という見出しで、再開発で竣工した高層ビルに空きテナントが目立つ状況を報じている。不況の影響で、思うようにテナントが集まらなかった。
それでも、武蔵小杉を「第三都心」として育てる計画は粘り強く継続された。再開発が不況下でも頓挫しなかった最大の理由は、将来的な交通利便性の向上が確実視されていたことにある。特に注目されたのが、2000年に予定されていた東急目黒線の武蔵小杉駅への延伸だった(同年8月に目蒲線を分割し、目黒線に移行)。
東急東横線はすでに東京メトロ日比谷線と直通運転を行っていた。これに加えて、目黒線が都営三田線・東京メトロ南北線と直通すれば、武蔵小杉から
・六本木
・赤坂
・銀座
・新宿
方面へ乗り換えなしでアクセスできるようになる。
さらに2005年4月には、川崎市とJR東日本が横須賀線の新駅設置に合意した。これにより、武蔵小杉は首都圏でも有数の交通利便性を備えるエリアになると期待された。
なお、この時期には川崎市営地下鉄の計画も存在していた。新百合ヶ丘駅~武蔵小杉駅~川崎駅を結ぶ構想だったが、こちらは実現しなかった。
武蔵小杉変貌の背後にある複数要因
交通インフラの充実を背景に、武蔵小杉の成功をさらに後押ししたのは、2000年代から始まった郊外タワーマンションのブランド化だった。
郊外タワーマンションのブランド化が最初に顕著だったのは、千葉県浦安市だ。2007(平成19)年頃、この地域のマンション価格は3LDK100平方メートルで4000万円台前半だった。同じ価格で、豊洲や横浜では80平方メートル程度。利便性と価格のバランスが取れていた。
新浦安周辺の主婦たちは「マリナーゼ」と呼ばれ、セレブの一類型とみなされるようになった。これを受け、武蔵小杉駅周辺のタワーマンションは
「第二のマリナーゼ」
になれる場所として人気を集めた。武蔵小杉の優れた交通利便性と郊外タワーマンションのブランド化が相乗効果を生み、かつての工業地帯は短期間で首都圏屈指のタワーマンションエリアに変わった。
これは高度成長期の「量重視」の住宅開発から、景観や設備、社会的ステータスを重視する「質の時代」への移行が、武蔵小杉という都市で顕著に表れた現象だ。2010年代に入ると、高層マンションの乱立により武蔵小杉の街並みは完全に変わった。この新しい都市景観は、首都圏の都市開発の象徴として多くのメディアで取り上げられた。
武蔵小杉がタワーマンション乱立地帯になった理由はひとつではない。いくつかの要因が重なった結果だ。まず、古くからの交通の要衝という地理的優位性があった。1980年代から始まった行政主導の再開発構想や、工場移転によって生じた広大な跡地も要因だ。
さらに、複数の鉄道路線の新設や増強による交通利便性の向上があった。そして、都心の地価高騰を背景に、「手の届く価格で郊外に豊かな生活を」という新たな価値観が生まれた。これらの要素が、2000年代に絶妙なタイミングで重なり、武蔵小杉の急速な変貌を促した。
しかし、都市開発としての成功が住民生活の充実とは必ずしも一致しないという矛盾が浮かび上がっている。冒頭で触れた町会解散の問題は、急速な再開発が地域社会の連続性を断絶させた象徴的な出来事だ。人口は3倍近く増えたが、タワーマンションの管理組合と旧来の地域組織との連携は進まず、住民同士の交流も薄いままだ。地域の歴史や文化を共有する機会は減り、同じ街に住む者という
「共同体意識」
が育まれにくい状況となっている。
急成長する街、住民意識の不均衡
注目すべきは、これらの問題が2000年代初頭から既に危惧されていたという点である。
『日経アーキテクチャ』2006(平成18)年12月11日号は、川崎市が新旧住民の融和を目指して設立した「NPO法人小杉駅周辺エリアマネジメント(現・一般社団法人武蔵小杉エリアマネジメント)」を報じている。大量の新住民流入によって変わりつつある街をどう一体化させるかは、タワーマンション建設初期からの重要課題だった。
『都市問題』2018年10月号に寄稿した同NPOの副理事長・山中佳彦氏は、行政の対応が後手に回っていると指摘し、
「堅牢なタワーマンションの個々の防災備蓄・装備をいかに充実させるかが肝要であり、そのような提案はエリマネの使命であると考えている」
と述べている。2019年には台風19号の浸水被害が発生。多くのタワーマンションが水に浸かり、街の脆弱性が明らかになった。この出来事で、危機管理のための地域コミュニティーの必要性が認識されたかと思われたが、実際には進展しなかった。
『東京新聞』2024年12月29日付電子版は、「武蔵小杉タワマン街で町会が解散へ 20年間で人口2.5倍なのに… タワマン住民向け別組織も人がいない…」と、厳しい現状を報じている。
「エリマネの運営も厳しい。当初はマンション全戸から月300円を徴収していたが、住民の不満が根強く、任意加入へと変更。会員数は5000人から500人に激減した。その後も減少に歯止めがかからず、現在は約70人。役員の一人は『エリマネも存亡の危機にある』と訴える」
このことをどう捉えるべきだろうか。災害を経ても、武蔵小杉には立派な建物や施設を利用する消費者は多い。しかし、地域の発展や課題に主体的に関わり、長期的視点で街づくりに参画する「住民」が育っていないという実態がある。
成功した都市開発とコミュニティ不足
筆者(昼間たかし、ルポライター)は、再開発前の武蔵小杉とはまったく違う街となった現在の姿に驚いている。商業施設は充実し、水害リスクを除けば、交通アクセスや生活利便性において、首都圏有数の暮らしやすい街になったことは間違いない。
だが、その急成長の陰で、地域コミュニティーの成長は追いつかなかった。武蔵小杉の事例が示すのは、多くのタワーマンション住民にとって、この街が「終の住処」ではなく、一時的な
「仮住まい」
としてしか機能していない現実である。
この事例は、都市開発の成功と地域社会の断絶という矛盾を浮き彫りにしている。今後の課題は、消費者を真の「住民」に変えることだろう。
こんな記事も読まれています
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
おすすめのニュース
-
-
AUTOSPORT web0
-
-
-
-
GQ JAPAN1
-
Webモーターマガジン0
-
-
-
愛車管理はマイカーページで!
登録してお得なクーポンを獲得しよう
おすすめのニュース
-
driver@web7
-
AUTOSPORT web0
-
-
motorsport.com 日本版3
-
-
WEB CARTOP9
-
-
AUTOSPORT web9
-
-
-
motorsport.com 日本版1
-
GQ JAPAN0
-
-
AUTOSPORT web0
-
motorsport.com 日本版3
-
motorsport.com 日本版0
-
-
-
-
AUTOCAR JAPAN0
-
-
Auto Messe Web1
-
くるくら0
-
-
motorsport.com 日本版0
-
-
AUTOSPORT web2
-
-
-
業界ニュースアクセスランキング
-
ホンダ「“新”N-BOX」発表に反響多数!? 「迫力すごい」「高級感ある」 “日本一売れてる軽”が精悍「メッキ増しデザイン」採用! 上質「2トーンカラー」も追加の“改良モデル” 18日発売
-
中央道で「中国人女性」が「路上寝そべり」で批判殺到!?「永遠に入国禁止で」「入国税を高額に」の声も…実際法律でどうなのか
-
1リッター“30km”以上走る!「ガソリン高すぎ…!」でも余裕!? 燃費の良い国産車TOP3
-
沈めた敵艦の乗組員に「当時ではスマートすぎる事後対応」WW2下で実在した“武士道溢れし艦長”とは
-
トヨタ“新”「ランドクルーザー“300”」発表! “トヨタ初”の「“盗難対策“機能」搭載!? 受注再開どうなった? デビュー4年目の「本格SUV」進化も”買えない“ってマジ?
コメントの多い記事
-
「タダだから乗っている」 産交バス運転士が“障害者”に暴言! 問われる公共交通の存在、問題の本質は何か?
-
日産が不況にあえいでいるのがまるで嘘のようなほど絶好調! 2024年に日本一売れたEVは3年連続で日産サクラだった
-
中央道で「中国人女性」が「路上寝そべり」で批判殺到!?「永遠に入国禁止で」「入国税を高額に」の声も…実際法律でどうなのか
-
「アルファード」は「残価ローン」がないと売れなくなる? 法人が「現金一括」を好む意外な理由も
-
【中国】ホンダ「新型フィット」まもなく登場! 全長4.2m級ボディに精悍「2段ライト」×大口“台形グリル”採用!? デザイン一新した「ビッグマイナーチェンジ」を実施か
あなたにおすすめのサービス
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
新車見積りサービス
店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!







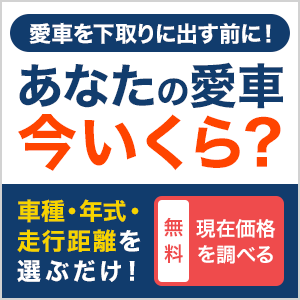
みんなのコメント
人間濁流!
人間荒波!
人間津波!