「練習は家でしてください」 大阪ストリートピアノの炎上騒動! 「練習 = 家」は正しい? 誰のための自由? 騒音vs文化、公共空間の哲学を問う
公共のピアノは誰のものか
駅や商業施設、観光地の一角に置かれたストリートピアノ。誰でも自由に弾けるという開放的な理念のもと、各地で設置が進んでいるが、一方で騒音問題やマナー違反などが指摘されることも少なくない。
意外と知らない? インターチェンジの近くに「ラブホテル」がやたらと多い理由
大阪・南港の商業施設内に設置されたストリートピアノでは、
「練習は家でしてください」
との掲示がSNSで大きな物議を醸した。ピアノを弾く自由は保証されるべきなのか、それとも演奏の質や周囲の環境を考慮した制限が必要なのか――。議論が噴出する背景には、そもそも
「自由とは何か」
という根本的な問いがある。ストリートピアノをめぐる問題は単なる音の快・不快の話ではなく、公共空間の在り方そのものを問う問題へとつながっている。本稿では、なぜストリートピアノが論争の的となるのかを、都市環境や経済的視点も交えて考察する。
ストリートピアノの歴史
ストリートピアノは、公共の場所に設置され、誰でも自由に演奏できるピアノのことだ。鉄道駅や空港に設置されるものは
・駅ピアノ
・空港ピアノ
とも呼ばれるが、設置場所は街角だけでなく、建物のロビーなども含まれる。演奏に特別な許可は不要で、公共性のある場所に設置されたピアノがストリートピアノとして認識される。
その発祥には諸説があり、英国のイングランド中部の工業都市・シェフィールドで2003年、引っ越し時に放置されたピアノをきっかけに広まったという説が存在する。
また、2007年にはアーティストのルーク・ジェラムが「Play Me,I’m Yours」というアート活動を通じて、世界中にストリートピアノを設置し、大きな反響を呼んだ(以上、中村亮「駅ピアノ-NHKの番組から-」。ニッセイ基礎研究所)。
この活動は、音楽を通じて人々や街を繋げ、自由に演奏できる環境を提供することを目的としている。
ストリートピアノの賛否両論
ストリートピアノの目的は、誰もが気軽に楽器に触れる機会を提供することにある。ピアノは高価であり、住宅事情によっては自宅に設置することが難しいため、公共の場にピアノを設置することで、音楽に親しむ機会を多くの人々に提供する狙いがあった。
しかし、実際には「自由に弾いてください」といいながらも、今回の炎上騒動のように
「周囲の迷惑にならないように」
「練習目的ではなく演奏を」
という条件が付けられることがある。このような制約は、一見矛盾しているように思えるが、自由には常に一定の制限がともなう。
例えば、街角に設置されたベンチは誰でも自由に座れるが、長時間寝そべることは通常禁止されている。同様に、ストリートピアノも弾くことは自由だが、周囲の快適さを損なわない範囲で、という暗黙の条件が求められる。問題は、この
「範囲」
の解釈が人によって異なる点にある。公共のピアノという考え方は、基本的に音楽は人を楽しませるという前提に立っている。しかし、実際にはすべての音楽が歓迎されるわけではない。例えば、クラシックの名曲を完璧に演奏する人には拍手が送られる一方で、初心者がつっかえながら弾く様子を
「騒音」
と感じる人もいる。このような受け取り方の違いが、ストリートピアノを巡る対立の根本にある。
ストリートパフォーマンスの歴史を振り返ると、路上での音楽活動は常に賛否を呼んできた。ロンドンでは19世紀から「バスキング(路上演奏)」が盛んに行われ、演奏許可制が導入されるなど、自由な演奏には規制が設けられてきた。日本においても、駅前でのギター演奏やドラム演奏が騒音と見なされ、取り締まりの対象となることがある。
ピアノの場合も例外ではない。オープンスペースに置かれたピアノは、誰でも弾けることが魅力となるが、その誰でもが、どんな演奏でも許容されることを意味するわけではない。
「公共」と「私的」の境界線
ストリートピアノが公共財なのか、それとも私的なものなのかという問題は再考すべき重要な点である。公共財とは、一般的に
・非排除性(誰でも利用できる)
・非競合性(他者の利用を妨げない)
を備えたものを指す。公園の噴水や街灯などがその代表例だ。一方、ストリートピアノは誰でも使える点では公共的だが、ひとりが長時間使用すると他の人が使えないという点から、完全な公共財とはいえない。
そのため、ストリートピアノを適切に運営するためには一定のルールが必要となる。しかし、ルールが厳格化しすぎると、ストリートピアノの本来の目的である自由に弾ける場という理念との矛盾が生じる。
このジレンマを解消するために、いくつかの工夫が行われている。例えば、利用時間を制限する(例:1回15分まで)、予約制を導入する(例:事前登録した人のみ演奏可)、設置場所を選定する(例:商業施設のフードコートではなく駅の広場に設置)などがある。これらの措置は、ストリートピアノの公共性を維持しつつ、周囲への配慮を可能にする試みだ。しかし、誰にとっての自由なのかという根本的な問いは依然として残る。
ストリートピアノが設置される場所は、駅や商業施設、観光地など人が集まる空間であることが多い。ここでは、音楽を楽しむこと以上に集客という
「経済的な意図」
が絡む。商業施設にとって、ピアノの設置は単なる文化的施策にとどまらず、訪問者の滞在時間を延ばし、消費行動を促進する戦略となる。駅に設置する場合も、話題性を提供することで駅のイメージアップが期待される。
一方で、クレームが増加すれば撤去される可能性もあるという現実も存在する。施設側にとって、ストリートピアノは
「利益を生む存在」
でなければならず、トラブルの原因となれば、維持することが困難となる。
実際、南港の事例では、「練習目的の利用が多く、クレームが増えた結果、撤去の可能性が浮上した」という流れがあった。このように、ストリートピアノが公共のものとされている一方で、その運命は設置者の経済的判断に大きく左右されることがわかる。
「自由」の線引きをどう考えるか
ストリートピアノの問題は、単なる演奏技術に関するものではなく、公共空間における自由のあり方を問い直す重要な問題だ。誰もが弾けるという理想は魅力的だが、現実には誰もが快適に過ごせることとのバランスが求められる。そのためには、個人の自由と公共の利益を適切に調整する必要がある。
では、最適なバランスとは何か。それは、ピアノを弾く側だけでなく、聴く側や周囲の環境、さらには設置する側の事情を総合的に考慮することで見えてくる。ストリートピアノの未来は、誰のための自由なのかという問いに、社会がどのように向き合うかにかかっている。
最後に私見を述べると、筆者は今回の炎上騒動の発端となった
「ストリートピアノは、どんなに下手でも、ホームレスでも、誰でも自由に弾けるものだ。それなのに、まるでTikTokerの感動的な演奏だけを求めているような姿勢が透けて見えて浅ましい。そんな掲示は、ストリートピアノの精神を踏みにじるものだ。実にみっともなく、恥ずかしい」
といったような内容のつぶやきを支持したい。
前述で多角的な視点から問題を考察したが、われわれはストリートにおける表現活動や予測不可能な出来事にもっと寛容であるべきだと感じる。そして、その設置の本来の哲学を理解することが、現代人の堅牢な精神の解放に繋がるのではないだろうか。
こんな記事も読まれています
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
おすすめのニュース
-
ベストカーWeb0
-
-
-
-
-
乗りものニュース0
-
Auto Prove0
-
-
Auto Prove0
-
愛車管理はマイカーページで!
登録してお得なクーポンを獲得しよう
おすすめのニュース
-
ベストカーWeb7
-
レスポンス0
-
-
-
-
-
-
-
ベストカーWeb9
-
motorsport.com 日本版2
-
-
-
Auto Prove0
-
-
-
-
-
乗りものニュース8
-
日刊自動車新聞0
-
-
-
motorsport.com 日本版0
-
AUTOCAR JAPAN0
-
Auto Messe Web0
-
-
-
-
-
-
AUTOSPORT web0
業界ニュースアクセスランキング
-
史上空前の大量発注「軍艦12隻ちょうだい、おまかせで!」同盟国の要請に日本どう応えた?
-
トヨタ「ちょっと小さな高級ミニバン」に反響多数!? 「渋い」「悪くない」 丁度良い“5ナンバー”ボディ×「アルファードグリル」採用!? 「豪華内装」もイイ「エスクァイア」とは何だったのか
-
最大80km/h以上! 海自の最速艦が「宗谷海峡」に急行か 戦車揚陸艦の出現に警戒監視
-
政府はなぜ国民を苦しめる? 税金取りすぎ…「ガソリン減税は実現する?」 7月にも価格に変化か… 忘れられた「トリガー条項発動」よりも「暫定税率廃止」を! 今後のシナリオは
-
15年ぶり全面刷新! 日産が「新型エルグランド」初公開! 元祖「キングオブミニバン」に史上初の「ハイブリッド」&高性能4WD搭載? 待望の「アルファード対抗馬」2025年度後半デビューへ
コメントの多い記事
-
石破総理が…! ガソリン価格「1リットルあたり10円引き下げ」宣言も…賛否の声多し!?「暫定税率の廃止が先では」とも… 5月22日から、みんなの反響は
-
15年ぶり全面刷新! 日産が「新型エルグランド」初公開! 元祖「キングオブミニバン」に史上初の「ハイブリッド」&高性能4WD搭載? 待望の「アルファード対抗馬」2025年度後半デビューへ
-
GW初日の宿泊予約、「4割」がインバウンド! もはや日本人は泊まれない? 都市観光の異変、誰のためのGWなのか?
-
「ごみ出しに1万5000円」 町内会の退会者に命じられた利用料! 福井地裁の判決が突きつけた“地域崩壊”の危機とは
-
「テスラがスランプ」世界でも地元アメリカでも販売が鈍化した理由が厳しい。なぜ急落しているのか?
あなたにおすすめのサービス
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
新車見積りサービス
店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!







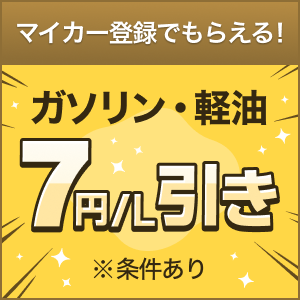
みんなのコメント
愉しく会話しながらピアノの練習されたなら、平気な人もいるし勘弁してくれと思う人もいるでしょうね
そもそも論で、設置場所間違っています
それなら演奏用ピアノとし、設置者がコンサート開催などするべきだった。