物流危機 「2024年問題」は序章に過ぎなかった! 2025年以降も深刻化必至? 9万トン規制、CLO選任…荷主が変わらなければ――の現実
物流危機は2024年を乗り越えても終わらない
2024年4月から時間外労働の上限規制がトラックドライバーにも適用された。いわゆる「2024年問題」だ。4月1日を起算日とする事業者であれば、2024年4月1日から2025年3月31日までの時間外労働は960時間以内に抑えなければならない。すでに時間外労働が960時間に達しているトラックドライバーは、3月末まで法定労働時間を超える勤務は許されない。そのようなドライバーが一定数存在すれば、3月末に向けてトラック不足に陥る可能性がある。
【画像】マジ!? これがレギュラーガソリンの「全国平均価格」です! 画像で見る(8枚)
ただし、これはあくまでも4月1日を起算日とする事業者の場合だ。1月1日を起算日とする事業者であれば、2025年1月1日から時間外労働の上限規制が適用される。その場合、該当する事業者が多ければ、トラック不足のリスクは2025年末に顕在化するだろう。いずれにせよ、2024年問題は
「まだ終わっていない」
のである。では、2025年を乗り越えれば物流危機を脱することができるのか。結論からいうと、そんなことは全くない。少子高齢化により人手不足はさらに深刻になるからだ。
貨物輸送の減少と人手不足
国内の貨物総輸送量は、産業構造が重厚長大型から軽薄短小型にシフトしたこともあり、2010(平成22)年頃まで年率2.5%で減少してきた。それ以降、国内総生産(GDP)あたりの輸送量は微減傾向にあるが、総輸送量の減少幅は縮小した。
日本ロジスティクスシステム協会の推計によれば、2025年以降もその傾向は続くだろう。一方で、成り手不足が顕著な営業用トラックのドライバーは年率2%以上で減少しており、今後もその傾向に歯止めがかかることはない。物流危機は、貨物輸送の増加という需要の問題ではなく、担い手の不足という供給の問題によって引き起こされる。そして、この需給ギャップは2025年4月以降も拡大し続ける。
政府の有識者会議である「持続可能な物流の実現に向けた検討会」は、「最終取りまとめ」において「2024年で対策が終わりということではなく始まりである」と記している。人手不足のさらなる深刻化を見据えた施策を実行し、物流効率を中長期的に高めなければ、「荷物を運べない時代」の到来は避けられないと考えるべきだ。
新物効法の施行による物流の効率化
2024年5月に公布された物流改正法(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律)は、物流効率を中長期的に高めるための政策的措置だ。その最も大きな特徴は、物流改正法に基づき改正された新物効法(物資の流通の効率化に関する法律)で、運送会社をはじめとする物流事業者だけでなく、荷主にも物流効率化への取り組みを義務づけた点だ。
実際、荷主が物流の効率化を妨げることが少なくない。例えば、荷主が情報漏洩を防ぐために他社との混載輸送を禁止すると、積載率を高める方法がひとつ減ることになる。積載量の最大化を優先するあまり、パレットやフォークリフトを使わず、手作業で荷物を積み下ろすよう指示すると、労働生産性が低下する。また、荷主が指定した時間にトラックが到着しても、出荷準備が整っていなかったり、積み下ろし場所であるバースが混雑して待たされることもある。
新物効法では、発荷主だけでなく、入荷側である着荷主にも物流効率化への努力義務を課している。日本では、発荷主が物流事業者と委託契約を結び、物流費を支払うことが多い。その場合、物流事業者への委託内容は発荷主との協議で決まるが、実際には着荷主からの指示で契約にない作業をこなしたり、待機させられたりすることがある。物流事業者は直接契約のない着荷主の指示を受ける必要はないが、発荷主との関係を踏まえて対応することが多い。新物効法で着荷主にも努力義務が課されたことは、この状況に一石を投じることになる。
この努力義務は2025年4月1日から施行される。罰則規定はないが、物流効率化への意識を高めるきっかけにはなるだろう。一定規模以上の特定荷主には、努力義務に加えて、物流統括管理者の選任や、物流の効率化に向けた中長期計画の作成・報告が義務付けられる。特定荷主の指定基準は「取扱貨物の重量が年間9万トン以上であること」が予想される。これは出荷した貨物の重量だけでなく、入荷した貨物の重量が年間9万トン以上であれば該当する。特定荷主に着荷主も対象としたことの重要性が反映されている結果だ。
特定荷主の指定や物流統括管理者の選任、中長期計画の作成・報告については2026年4月1日に施行される予定だ。まだ1年以上の猶予があるが、大手荷主は自社の取り扱い貨物の重量を確認し、年間9万トン以上であれば物流統括管理者を選任し、中長期計画の作成に取り掛かることが望ましい。
CLOとは何か
特定荷主が選任しなければならない物流統括管理者は、どのような役割と権限を持つのだろうか。
新物効法に基づいて設置された国土交通省・経済産業省・農林水産省の審議会による合同会議は、「取りまとめ」において物流統括管理者を次のように規定した。
「物流統括管理者は、物流全体の持続可能な提供の確保に向けた業務全般を統括管理する者である。物流統括管理者の業務を遂行するためには、運送(輸送)、荷役といった物流の各機能を改善することだけではなく、調達、生産、販売等の物流の各分野を統合して、流通全体の効率化を計画するため、関係部署間の調整に加え、取引先等の社外事業者等との水平連携や垂直連携を推進することなどが求められ、これらの観点から事業運営上の決定を主導することとなる。このため、ロジスティクスを司るいわゆるCLO(Chief Logistics Officer)としての経営管理の視点や役割も期待されていることから、その立場としては、基本として、重要な経営判断を行う役員等の経営幹部から選任されることが必要である」
最も重要なのは、物流統括管理者が「物流部長」ではなく、経営幹部から選任される
「CLO」
であるということだ。その管掌範囲は物流にとどまらず、調達、生産、販売などを含むサプライチェーン全体での最適化を進めることが求められる。役職名は物流統括管理者やCLOである可能性があるが、実際には「CSCO(Chief Supply Chain Officer)」と呼ばれるにふさわしい役割・権限を持つ存在であると期待されている。
サプライチェーン全体を最適化することの重要性
では、なぜ新物効法でCLOの選任が義務付けられることになったのか。それは、サプライチェーン全体の最適化が十分に追求できていないことが物流の効率化を妨げていると認識されたからだ。実際、筆者(小野塚征志、戦略コンサルタント)のコンサルティング経験でもサプライチェーンの全体最適が課題となった例は多い。
例えば、筆者がコスト構造改革を支援した機械メーカーのA社は、X工場で部品を加工し、Y工場で組み立てた後、納品先に出荷していた。このX工場からY工場へのトラック輸送は1日3回行われていた。輸送の頻度が高ければその分だけ工場内の在庫を減らせるからだ。これはトヨタ式の「ジャスト・イン・タイム」を徹底した結果である。
しかし、国内生産はピーク時よりも大きく減少しており、X工場からY工場に向かうトラックの積載率は常に30%を下回っていた。つまり、積載率が30%にも満たないトラックを1日に3回も走らせていたのだ。
筆者が指摘した結果、A社は1日1回に変更することで、トラック輸送のコストを半分以下に削減した。もちろん、輸送頻度を下げたため工場内の在庫は増えたが、余剰スペースがあったため追加の費用は生じなかった。
こう書くと、読者は「なぜA社はこの問題に気づかなかったのか」と思うかもしれない。A社の工場からすると、トラック輸送は物流部門で計上されるコストであり、在庫を増やさないことが重要だった。対して、物流部門は積載率が30%に満たないことを認識していたが、1日3回の輸送は工場からの指示であり、その範囲内で改善活動を行うしかないと考えていた。そして、経営者は改善活動を徹底させた結果、効率化が進んだと錯覚していた。
また、チラシやポスターの制作を主とする印刷会社のB社は、「朝一での納品」を基本としていた。B社の営業マンは「得意先が朝一での納品を求めているから」といっていた。これにより、明け方から20台ほどのトラックが動き出し、昼前には戻ってくる。大半のトラックは午前中の数時間しか稼働していなかった。
筆者は、このB社の得意先に本当に朝一での納品が必要なのかと聞いてみた。すると、大多数の得意先は「B社の営業マンが“朝一に納品します”というから、お願いしますと答えていたが、別に朝一に持ってきてもらう必要はない」といった。結局、「朝一での納品」は営業マンの決まり文句に過ぎなかったのだ。
B社は、このマインドを改めるため、朝一での納品が不要な案件を獲得するとボーナスが増えるルールを導入した。結果として、営業マンは「時間指定のない納品」を提案し、午後もトラックを活用できるようになった。これにより、必要なトラックの台数は半減し、ボーナスの増加分をはるかに上回るコスト削減効果が得られた。
CLO選任は義務ではなく有効な手段と捉えるべき
A社にしろB社にしろ、工場、営業、物流といった個別の現場に問題があったわけではない。工場や営業が協力することで物流コストを下げるといった「全体最適」の考え方が欠けていたのである。
では、その全体最適は本来誰が担うべきだったのだろうか。それは紛れもなく「経営者」および「CLO」である。
欧米企業では、CLOやCSCOは決して珍しい役職ではない。それだけが原因ではないが、日本企業よりも全体最適への意識が相対的に高く、収益力の差となって現れることもある。
だからこそ、CLOの選任は新物効法で義務付けられたことに従うだけの取り組みとして捉えるべきではない。サプライチェーンの全体最適を実現するための手段である。2026年4月の施行を待つことなくCLOを選任し、相応の役割・権限を付与することでサプライチェーン全体の最適化を推進すれば、他社に先んじて収益力を高めることができる。
また、物流危機のさらなる深刻化にも備えることができる。現場の属人的ノウハウに依存し、個別最適を優先しがちな日本企業の経営体質を変えるきっかけにもなるだろう。
こんな記事も読まれています
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
おすすめのニュース
-
-
-
AUTOSPORT web0
-
-
乗りものニュース1
-
motorsport.com 日本版1
-
motorsport.com 日本版1
-
-
motorsport.com 日本版6
-
AUTOSPORT web0
愛車管理はマイカーページで!
登録してお得なクーポンを獲得しよう
おすすめのニュース
-
-
-
AUTOCAR JAPAN2
-
Auto Messe Web1
-
グーネット4
-
Webモーターマガジン47
-
motorsport.com 日本版0
-
バイクのニュース7
-
レスポンス18
-
AUTOSPORT web0
-
乗りものニュース1
-
-
-
AUTOSPORT web0
-
motorsport.com 日本版0
-
AutoBild Japan1
-
-
motorsport.com 日本版1
-
-
motorsport.com 日本版1
-
-
-
GQ JAPAN0
-
AUTOSPORT web1
-
AUTOSPORT web0
-
Auto Prove0
-
AUTOCAR JAPAN0
-
-
-
AUTOSPORT web0
業界ニュースアクセスランキング
-
「車中泊トラブル」なぜ後を絶たない…!? 「ご遠慮ください」案内を無視する人も… 背景にはキャンプと「混同」も? 現状はどうなっている?
-
海自のミサイル艇と中国海軍の主力艦が「にらみ合い」!? 中国艦を “真横”から捉えた画像を防衛省が公開
-
新型RAV4発売秒読み!? レクサスNX並のボディ形状か!?
-
政府はヤル気なさすぎ…! 腰重いなかで、やっと「ガソリン価格」6月から値下げも… 定額「10円」を検討? 「暫定税率の廃止が先」の声も! 家計負担大きいのはどうにかならないの?
-
大阪→熊本で「ロングラン夜行列車」運行へ JR西の“客車”が九州に乗り入れ 所要は15時間超え!?
コメントの多い記事
-
「WR-V」一部改良に賛否。好意的な声の一方「値上げでは」との批判も…なぜここまで評価が分かれるのか?
-
「車中泊トラブル」なぜ後を絶たない…!? 「ご遠慮ください」案内を無視する人も… 背景にはキャンプと「混同」も? 現状はどうなっている?
-
ついに公正取引委員会がトヨタモビリティ東京に対し独禁法違反にあたる えげつない「抱き合わせ販売」をやめるよう警告!! ユーザーの怒りが通じた!!!
-
どんだけ金食い虫なんだよ! 自衛隊に配備目前「F-35戦闘機のコスト」調べてみた 納税者なら知っておくべき?
-
「不正通行にはならない」ETC障害で国交相、刑事責任に問われる可能性を否定 NEXCOは「お支払いを」 どういうことなのか?
あなたにおすすめのサービス
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
新車見積りサービス
店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!







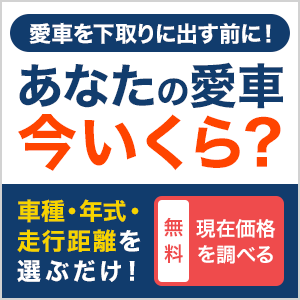
みんなのコメント
移動時間や積み時間や待機時間をより効率化させなきゃ無理
あと今は小規模運送会社が法令違反して走行しているから、現状どうにかなってる状態
でも、頭のおかしい経営者は収益増加で笑ってるというね
運転手が大きい事故を起こせば詰むのに事故起こさないとでも思っているのだろう
最後に
本当の物流崩壊は今の50代60代がリタイヤした時
今の物流の50%を支える層が離脱したらどうすんだろうね?
80代になってもバラ積みバラ卸し頑張れとでも言うのかな?
しかも安い単価で