かのジウジアーロ氏も納得のスタイリング
1991年9月に発売され、2万4365台が生産されたアルシオーネSVXは、スバルファンから奇跡の大傑作名車として崇められているが、一般的なクルマ好きからの評価は今ひとつ。クルマ雑誌などでも「デザインが良かった過去の日本車」的な企画でたまに思い出される程度にとどまっているので、この場を借りてその素晴らしさをアピールしたい。
【スバリストが選ぶライバル】歴代最強の三菱ランサーエボリューションはこれだ!
まずは素敵でオシャレ、かつ重いテーマが込めらたネーミングから。「アルシオーネ」とは、スバルのマークである牡牛座の六連星の中で一番大きな星のことで(プレアデス星団の一番星)、名前からしてスバルのフラッグシップという意味が込めらているが、「SVX」はSubaru Vehicle X の略で、かつてない革新的なスバル車と解釈される。「SVX」の車名が決定したのは発売直前のことで、バブル経済が崩壊し、経営再建中だった旧富士重工業が新境地を切り開こうと渾身の開発を行った入魂車だったことを表している。
そんなアルシオーネSVXの注目すべきポイントは多岐にわたるが、ここでは ・ジウジアーロ氏も納得した原案デザインの再現
・技術革新を要した全面3次元ラウンドキャノピーの実現
・高度な操縦性と耐久性、そしてラウンドキャノピーにも対応した高剛性ボディ
・完全バランスを追求した3.3L水平対向6気筒NAエンジン
・FRの回頭性と操舵感、AWDの安定性を備えたVTD-AWD の5つを特筆ポイントとして挙げたい。
スバリスト以外からも評価の高いエクステリアデザインは、1986年にジョルジェット・ジウジアーロ氏率いるイタルデザインに打診し、数案のスケッチのなかからもっとも空力に優れ、スバルらしさを表現しやすいと判断された「クーポラ」というデザイン案がピックアップされたことに始まる。「クーポラ」とは、ウインドウからルーフがドームのような形状で、ラウンドキャノピーと呼ばれる三次元ガラスで構成する斬新な案だ。
初期段階では初代レガシィベースの5ナンバーサイズボディだったものが、搭載エンジンが当初の予定だった4気筒から新開発の6気筒となり、それに見合うサスペンション設計や居住空間の確保のためにボディを拡幅。さらにラウンドキャノピーの生産性、とりわけ三次元カーブガラスの量産が困難ななかでオリジナル案そのままというわけにはいかなかったが、良い妥協点を見出してジウジアーロ氏も納得するスタイリングを再現した。
ジウジアーロ氏の長年のパートナーであり、日本メーカーとのコラボの際は通訳としても活躍した宮川秀之氏の父は中島飛行機に勤務した経緯があり、宮川氏はスバルデザイン部の上層部に知人が多かったことも、スバルとイタルデザインの共同作業が上手くいった要因のひとつとされる。ジウジアーロ氏は宮川氏とともに開発中に何度も群馬を訪れ細部をチェックしたなど、単にデザイン工房として原案を提供しただけではなかったのだ。
困難を乗り越えて実現した全面3次元ラウンドキャノピー
アルシオーネSVXの外観デザインの肝といえる全面3次元ラウンドキャノピーの実現は困難を極めた。フロント、サイド、リヤのウインドウ間にピラーが露出しないグラスtoグラスのラウンドキャノピーは、当時の大手ガラスメーカー3社に打診するも、どこも従来製法では無理との回答で、従来のガラス製法では不可能とされた。
単にカーブしただけのガラスを作るのは簡単だが、問題はガラスにカーブを与えることによる視界の歪みで、透視歪みや二重像などの光学的な難題が立ちはだかる。わずかな歪みがガラス越しの風景を大幅に歪曲させてしまい、自動車としてまともな視界が得られなくなってしまうのだ。
そこで、日本板硝子で開発されたプレスベンティングという、ガラスを炉の中で熱しながらプレスで曲げる方法を採用。フロントウインドウのカーブの深さは、レガシィの8ミリに対して15ミリとなったが、これはガラスの歪みの限界であり、ワイパーの追従性の限界だった。
さらに、ミッドフレームの上部を構成するアッパーサイドのウインドウは、細長くカーブがきついため曲げ加工が難しかったが、一方から圧力をかけ、一方からバキュームで型に密着させる新製法を開発。これらのガラスのピラーへの取り付けも困難を極めたが、エンキャップシュレイテッドモールという、ガラスを型に入れて周囲にウレタン樹脂を射出し、モールと一体構造にしてしまう方法でこれを解決。このように、全面3次元ラウンドキャノピーはさまざまな困難を技術革新で乗り越え実現している。
全面3次元ラウンドキャノピーの実現には、ボディ側の革新も求められた。当時はまだ世界的にも量産車での採用例が少なかった100%亜鉛メッキ鋼板で構成されたモノコックボディを採用。
キャビンの外面にピラーを露出しないようにするため、ピラー部分は必要な強度を確保しながら可能な限り細くすることが求められた。溶接を見直し、亜鉛メッキの厚みを表す目付け量は1平方メートルあたり60~80グラムと非常に贅沢な値とすることなどでこれを実現。
さらに、地面に近いためサビやすいフロアの補強材の多くを床上に配置した点も車体設計の特筆ポイントだ。たとえば、実質2名乗りの当時のポルシェ各車は居住空間を犠牲にしてフレームを居住空間にまで張り出させて剛性を高めていたが、グランドツアラーを目指すアルシオーネSVXは、メインフレームだけは床下に配置することでセダン並みの居住生と快適性を確保することを求めた。結果として、剛性が高くサビにも強く、室内が広く使える車体が出来上がった。25年以上経った今乗っても驚くほど高い剛性感を備えている。
内装に関しては、外装に比べると地味でつまらないと過小評価されがちで、確かに地味さは否めない。しかし、それは幾何学構成のシンプルさを追求した結果で、ある意味狙い通りといえる。地味ながら質感の高さはフラッグシップに相応しく、今見ても感心させられる点が多い。
また、円形モチーフの温度調整スイッチは、温度表示の円形窓そのものがシーソー式のスイッチになるというアイディアで特許も取得するなど、創意工夫が多々見られる。さらに、当時の新素材エクセーヌ(今ではアルカンターラやウルトラスエードとも呼ばれる)は、直接太陽光が当たらない箇所に配置するべきものだったが、SVXの全面3次元ラウンドキャノピーはUV機能を備えるため、シート表皮など内装の広範囲に配置することができるようになったなど、SVXならではの美点は内装にもしっかり活かされた。
また、全面3次元ラウンドキャノピーは室内の温度上昇を抑制する効果も高く、空調面でもメリットが大きい。当時はエンジンの高負荷時で冷却性能に余裕がなくなるとエアコンをカットするシステムが一般的だったが、コンプレッサーの外部制御システムでこれを克服している。
さらに見えないところでは、ポリエチレンとナイロンを接着した3種5層構造で、安全で複雑な形状を可能とした樹脂製燃料タンクの新採用も当時としては斬新であった。
素直は回頭性をもつ4WDを目指して「VTD-4WD」を開発
エンジンは、ターボという選択肢も検討されながら、ピークパワーよりもリニア感のある太いトルクを求めて、当初の予定だった3リッターからさらに拡大した3.3リッターの大排気量(スバルとしては)のNA6気筒を採用。試作エンジンのひとつに、レガシィで実績のあるロッカーアームをもつバルブメカニズムとしたDOHCの世界トップクラスのバルブ有効開口面積を持つ高回転型のスポーツユニットも作られ、これは高回転域のフィーリングが極めてスポーティだったが、SVXのキャラには合わずお蔵入りに。
最終的にはDOHCでありながらレガシィ用のロッカーアームをもつバルブではなく、ダイレクトプッシュ式とすることで、よりグランドツアラーに適したトルク特性を追求したタイプが採用された。これにはインテークマニホールドの充填効率の大幅な向上と、共鳴過給効果と慣性吸気効果を切り替える可変吸気機構も採用。スロットルバルブのプログレッシブ化やATの特性見直しなどにより、アクセル全開時にはスポーツカー的な加速性能を発揮しながら、通常時には大排気量NAならではの落ち着きのあるジェントルな質の加速が味わえるセッティングとなっている。
当時としては珍しい、2500~5800回転の広範囲で最大トルクの90%以上を発揮するフラットなトルク特性を実現した。またエキゾーストは左右等長で、当時のスバル車とは一線を画す静粛性も実現している。
操縦性にも特筆ポイントが満載だが、とりわけ注目すべきは「VTD-4WD」の新採用だ。スポーツカー的なハンドリングを求めた開発において、FRの走りの魅力は当時のスバルのエンジニアたちにも十分に理解されていた。今と違ってまだレオーネ時代のイメージが強く、「スバル=アンダーステア」のレッテルを払拭するためにも、FR的な操縦性と操舵フィールを追求したいとの思いが強かったという。
しかし、だからといってFRを選択すべきとの声は誰からも挙がらなかった。スバルが今も昔も重視するアクティブセーフティという基準で考えれば、FRに対して4WDの方が絶対的に優位であることが明らかだったからだ。
当初は初代レガシィにも搭載予定の電子制御油圧多板クラッチ式のACT-4が搭載される予定だったが、当時のACT-4はFF状態と直結4WDの間で駆動トルクを配分するシステムであり、3.3リッターの大トルクがフロント寄りに配分されることによる操舵フィールと回頭性の悪化が問題視された。
グランドツアラーとして質の高い操舵フィールの確保と、回頭性の鈍さを解消するにはACT-4では力不足となり、新規の4WDシステムを開発。前後の駆動トルク配分比を後輪寄りとし、連続的に可変制御する「Variable Torque Distribution(VTD)」と呼ばれるシステムが誕生した。
基本的なトルク配分を前輪35%、後輪65%とすることでFRのような回頭性を実現しつつ、前後直結状態まで連続的に可変させることで安定感を確保するというものだ。真冬のフィンランドなどの極限的な環境下でも入念に走り込んでセッティングを煮詰め、当時の開発陣が掲げた理想的なハンドリングを実現。
いわゆるGTカーと呼ばれるモデルの多くは今でもFRが主流だが、悪天候時の安定性ではVTD-4WDのアドバンテージは極めて大きい。VTD-4WDシステムはその後も改良が重ねられ、今のレヴォーグやWRX S4にも搭載されている。
このように、アルシオーネSVXはスバルファンとしての贔屓目を全力で排除し、冷静に客観的な評価をしてもやはり名車と称えたくなる傑作車なのである。唯一残念なのは燃費の悪さで、当時の広告コピーのように1日500マイルの距離を走るには2度給油する必要があるが、1991年デビューの6気筒モデルとして考えれば全然許容できる範囲といえる。
こんな記事も読まれています
この記事に出てきたクルマ
全国のスバル アルシオーネSVX中古車一覧 (23件)
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
おすすめのニュース
-
-
-
-
AUTOSPORT web0
-
バイクのニュース0
-
-
乗りものニュース0
-
-
-
motorsport.com 日本版0
愛車管理はマイカーページで!
登録してお得なクーポンを獲得しよう
おすすめのニュース
-
-
-
ベストカーWeb4
-
-
LE VOLANT CARSMEET WEB0
-
-
motorsport.com 日本版0
-
-
WEB CARTOP1
-
-
motorsport.com 日本版1
-
LE VOLANT CARSMEET WEB1
-
-
-
-
日刊自動車新聞0
-
-
-
motorsport.com 日本版0
-
-
AUTOCAR JAPAN0
-
ベストカーWeb3
-
-
カー・アンド・ドライバー0
-
Webモーターマガジン0
-
-
motorsport.com 日本版0
-
-
LE VOLANT CARSMEET WEB3
-
業界ニュースアクセスランキング
-
赤信号を無視した女、警察官に「緊急のオペがある。人が死んだらどうする」と説明… その後再三の出頭要請に応じず逮捕! 一体何が起きた?
-
もはや“ミニ”Sクラス──新型メルセデス・ベンツCLA詳報
-
なぜ「免許センター」を「電車で行けない場所」に作ってしまうのか…SNSで共感の声多数!?「栃木やばい」「京都も遠すぎ」不便な立地には「納得の理由」があった!?
-
約“7000cc”の「V型12気筒/ツインターボエンジン」搭載! 超パワフルな「新型セダン」発表! 斬新すぎる「大神殿グリル&豪華内装」採用した新型「ゴースト・シリーズII」ロールス・ロイスが発売!
-
京都~敦賀が「無料でほぼ信号ゼロ」に!? 北陸最短ルート「琵琶湖西縦貫道路」工事どこまで進んだのか 「激烈渋滞エリア」4車線化もまもなく!?
コメントの多い記事
-
「うわぁ!懐かしい!」 “腕回しバック駐車”は過去の話? 昭和で当たり前だったけど“令和で消えそう”な「クルマ運転あるある」5選!
-
軽の「黄色いナンバー」を「普通の“白い”ナンバー」に変えられる!? 「黄色は恥ずかしい…」「むしろかわいい」意見も? 軽専用の「目立つナンバー」に反響あり
-
新車当時140万円切り! 日産「7人乗りミニバン キューブキュービック」に注目! 全長4m以下で斬新“カクカクデザイン”採用! セレナより安い「お手頃ファミリーカー」に熱視線
-
使える!遊べる!もっと自由なクラウン「エステート」公開。大人の好奇心に応えるロングツーリング性能も磨かれている。
-
レクサス「LBX」が「スピンドルグリルをぶっ壊した」理由とは?【レクサス・インターナショナル プロジェクトチーフデザイナー袴田浩昭氏:TOP interview】
この記事に出てきたクルマ
あなたにおすすめのサービス
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
新車見積りサービス
店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!







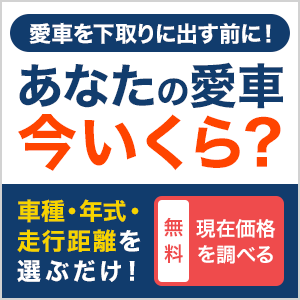
みんなのコメント
この記事にはまだコメントがありません。
この記事に対するあなたの意見や感想を投稿しませんか?