もはや立ち入る隙はない? EV含め全方位開発に邁進するトヨタが牙を剥いた相手は誰か!?
年の瀬も迫った2021年12月14日。年末の慌ただしさを吹き飛ばすようなニュースが自動車業界を駆け巡った。
トヨタが「2030年までにBEV(バッテリー式電気自動車)30車種を発売し、年間販売台数の約4割に相当する350万台をBEVにする」と発表したのだ。
1兆ドル越えグループの仲間入り! テスラは10年以内に日本でふつうになる日は来る!?
無数のBEVモデルに囲まれ誇らしげに立つ豊田章男社長の姿は、今まで「トヨタはEVに消極的だ」と噂していた巷の声を沈黙させるにはじゅうぶんすぎるインパクトだった。
なぜこのタイミングで、トヨタはBEVビジネスの大幅拡大を表明したのだろうか。トヨタが自社のスタンスを本当に発信したかった相手は誰なのか。井元康一郎氏が解説する。
文/井元康一郎、写真/TOYOTA、AdobeStock
[gallink]
■2030年までにBEV30車種、350万台!!
2030年までにBEV30車種を発売し、年間販売台数の約4割に相当する350万台をBEVにすると表明したトヨタ。ずらりと並んだ他種多様なBEVは圧巻
年の瀬も迫る12月14日、BEV(バッテリー式電気自動車)ビジネスの大幅拡大を表明したトヨタ。2030年までにBEV30車種を発売し、年間販売台数の約4割に相当する350万台をBEVにするという。
なかでも高級車ブランドのレクサスについては現在より20万台以上多い100万台を目標とし、そのすべてをBEV化すると意気込む。5月の決算発表時にFCEV(燃料電池式電気自動車)を含め200万台という計画を発表していたが、わずか半年あまりでその計画を大幅に上方修正した格好だ。
豊田章男社長が「電気自動車はつまらない」と繰り返したり、日本の急速充電規格であるCHAdeMO協議会に首脳級を送り込むことを渋ったりと、BEVについては何かと消極的な態度が目についたトヨタだが、その姿勢に変化が生じる兆候を見せ始めていた。
■象徴的だった電動化技術の呼称変更
象徴的だったのは、BEV+FCEVで200万台という目標を出した時に電動化技術の呼び名を世界標準に変えたこと。それまでトヨタはクルマの呼び名に「EV」の文字を入れることを極度に嫌ってきた。
燃料電池車については当初は「ハイブリッド技術が入っているから」とFCHV(燃料電池ハイブリッドカー)、市販車「MIRAI」を出してからはFCV。
プラグインハイブリッドについては一般的なPHEVではなくPHV、ハイブリッドカーはHEVではなくHV――といった具合に、トヨタ独自の呼び名を使い、それを世間に広めてきた。
それだけに200万台計画のプレゼン資料でBEV、FCEV、PHEV、HEVという用語に変えた時は驚いた記者も少なくなかった。
■BEVでの一斉転換に対する危機感
ハイブリッドカー可愛さというきらいがないでもなかったが、トヨタがBEVに消極的だったのにはちゃんと理由がある。実は2040年に電動化100%という野心的な目標を発表したホンダも、BEVについてはつい最近まで消極的だった。
両社に共通しているのは電動化技術について膨大な知見を蓄積しており、現在のBEVの技術で世の中のクルマを一気にBEVに転換するのがいかにリスキーであるかを熟知していることだ。
BEVは現在の普及率くらいであれば別に何の問題も生じない。価格が高い、航続距離が短い、充電に時間がかかる、バッテリーが劣化すると電池の交換に高額な費用がかかるなどといった問題はユーザーが納得していればすむ話である。
■BEVへ一変することで起きる不都合とは
充電などのインフラの問題もあり、一朝一夕にBEVの世界とはならないのが実情だ(Artinun@AdobeStock)
が、近い将来世界で年間1億台に達する自動車のうち何割かをBEVにするということになると、話はまったく異なってくる。
バッテリー製造の資源をどうするか、走らせるための電力をどうするかといった問題があるのはもちろんのこと、ちょっと交通需要が増えるたびに充電スポットにBEVが殺到し、長い待ちの行列ができる。
充電に時間がかかれば、充電器を設置する業者のほうも採算が取れない。少なくとも5分で400km分くらいの電力を耐久性や安全性の懸念なしに充電できるようにならないかぎり、クルマは今までのように移動の自由を担保する乗り物ではなくなってしまう。
将来的にはそういう技術も出てくるだろうが、そうなるまではハイブリッドカーを含む従来型のエンジン車のエネルギー効率改善でCO2低減を図るほうがベター――というのがトヨタ、ホンダに共通する基本スタンスだったのである。
■トヨタがBEVに舵を切った理由
そのトヨタが急にBEVに前のめりになったのは、恐らくBEVが主流になっても大丈夫と言えるほど電動化技術が進化したからではない。もちろん技術はここ10年で進歩はしたが、ガソリン車やディーゼル車への置き換えができるにはほど遠い。
問題はむしろ、世界各国の政府がカーボンニュートラル(CO2の排出量と吸収量を均衡させること)を旗印にBEV誘導政策を推進していることにある。もちろん既存のクルマの燃費を向上させることでもCO2排出量の削減は可能だが、今のBEV誘導策はその選択肢を事実上否定するものだ。
いくらカーボンニュートラルを掲げたところでユーザーのほうが納得しなければ、電動化は進まない。例えばヨーロッパでは、ヴァカンスのシーズンになるとクルマで旅をする人が増える。日常ユースでも長距離走行の機会は日本よりはるかに多い。
ドイツに本社を構える自動車部品世界大手、ZFで電動化技術の開発を手がける幹部すら「電動化と簡単に言うが、ユーザーが簡単にヴァカンスの習慣を捨てられるとは思わない。自分だって嫌だ」というほどだった。
■コロナをきっかけとした『SDGs』の波
コロナ禍以降、世界中で急速に推進されつつあるSDGs(beeboys@AdobeStock)
ところがここに来て、その空気に大きな変化が起こっている。きっかけとなったのは昨年来続いているコロナ禍だ。世界的流行が起こった当初から逆境をどう乗り切るかではなく「新しい生活様式」だの「ニューノーマル」だのと、元には戻さないことを前提とした号令が世界中で起こったことは記憶に新しい。
パンデミックで国民の主権制限を行うことが可能という実感を抱いた各国の権力者たちは、その余勢を駆ってこれまでなかなか広がりを持てなかった「SDGs」(持続可能な開発目標)を一気呵成に浸透させようとしている。
自動車分野はその典型で、いくらユーザーがBEVは不便だと思ったとしても「気候変動防止のためには我慢すべき」「行動様式のほうを変えろ」で押しまくれると踏んだのだ。
もちろん、それで納得しないユーザーはなお多数残るが、その状況が永続的かどうかは不透明になってきている。各国でESD(持続可能な開発のための教育)が加速しているからだ。
子供たちに「移動は悪」と道徳的に教え込めば、パーソナルモビリティを使って移動の自由を満喫したいという欲求を抑制することも不可能ではない。
■より現実的に未来を見据えるトヨタの思惑
これまで豊田章男社長は「商品を選ぶのはユーザー」と繰り返してきた。が、コロナ禍、そして気候変動防止の枠組みのなかでは「商品を選ぶのは政府」と言ってもいい状況が生まれつつあるのである。
その世界トレンドの軍門に早々と降ったのが2040年電動化100%を掲げたホンダだった。それに対してトヨタは2030年の新車販売の約4割にとどまっている。つまり6割はハイブリッドカーを含む従来型車が占めるというわけだ。
この違いはトヨタがCO2削減は空想的な理想主義では達成できないという考えを捨てていないことによるものだろう。
「すべてをBEV化するなど無謀だと思うが、それしかダメと言うのなら我々はやりますよ。しかし、エネルギー事情、道路事情、経済事情など、国にはそれぞれ立場がある。それを無視してBEV化を世界で推進して大丈夫なんですか?」という問いかけのようなものだ。
■トヨタは内燃機関を捨ててはいない
トヨタが大々的なBEV導入のプランを発表する一方で内燃機関を捨てる表明をしなかったことは、とりわけEU(ヨーロッパ連合)にとっては脅威だろう。
よく、「ヨーロッパはディーゼル排出ガス不正の失地回復のためにBEVに舵を切った」という俗説を耳にするが、EUの電動化プロジェクトはそんな浅いものではない。
筆者はディーゼル不正が起こる前年の2014年、イタリアのヴェネツィアで行われたカーボンニュートラルに関するシンポジウムを取材した。
そこで自動車業界を代表してやってきたアウディの環境担当役員、ウーヴェ・コーザー氏は電動化、再生可能エネルギー開発、さらにはカーボンニュートラルな合成燃料eフューエルなど、多様な取り組みを示しながら、カーボンニュートラルが近い将来、企業への投資判断の材料として取り入れられるようになった時の準備の進捗を得々と語っていた。
ディーゼル不正で慌てて電動化をやったというだけなら、EUはいつでも元の路線に戻れる。が、10年以上の年月をかけて再生可能エネルギーに膨大な投資を行い、経済システムにも低炭素を組み込むなど、自ら背水の陣を敷いた今では後戻りはできない。世界が自分たちになびいてくれなければ困るのだ。
■カーボンニュートラルにハンデを背負う日本
世界中でカーボンニュートラルを推進するというのなら、再生可能エネルギーを増やすのが難しい日本のCO2削減分をEUが引き受けるという気概をみせてくれてもいいはずだ(Soonthorn@AdobeStock)
そもそもEUのカーボンニュートラルの理念は再生可能エネルギーが安定して得られ、地震が少なく核エネルギー利用の安全性も担保しやすい自らの地の利しか考えていない、見方によっては身勝手きわまりないものでもある。
台風や豪雪で再生可能エネルギーを増やすのが難しく、地震が多発することで核エネルギーを増やすにも限界がある日本など、最初から膨大なハンディを負わされているようなものだ。
世界で協調して気候変動に立ち向かうというのが本当ならば、非石油・ガスエネルギー利用で有利な立場にあるEUが日本が本来負うべきCO2削減分の一部を自分たちで引き受けるというくらいでなければならないはずだ。
トヨタのBEV、既存技術の両取り策は、そんな世界のトレンドに対する強烈なカウンターパンチと言えるが、これで技術革新的には非常に面白くなった。EU、それと協調路線を取る中国がそれに対抗するには、BEVを本当に現在のクルマの代替技術に育てるしか手がなくなったようなものだからだ。
今までトヨタは電動化に関する膨大な知見や開発リソースを持ちながら、日本のBEVの発展にほとんど寄与することがなかった。BEV、エンジン車の両取り策で日本の自動車産業のポジション回復に貢献できるかどうか、これからの展開が大いに見ものである。
[gallink]
こんな記事も読まれています
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
おすすめのニュース
-
-
-
-
-
レスポンス0
-
-
-
-
WEBヤングマシン2
-
愛車管理はマイカーページで!
登録してお得なクーポンを獲得しよう
おすすめのニュース
-
乗りものニュース16
-
AUTOSPORT web3
-
-
-
ベストカーWeb4
-
-
-
-
-
-
AutoBild Japan0
-
-
AUTOSPORT web0
-
driver@web0
-
-
-
-
-
-
-
-
WEB CARTOP46
-
-
motorsport.com 日本版0
-
-
AUTOSPORT web0
-
GQ JAPAN0
-
-
GQ JAPAN0
-
motorsport.com 日本版1
業界ニュースアクセスランキング
-
史上空前の大量発注「軍艦12隻ちょうだい、おまかせで!」同盟国の要請に日本どう応えた?
-
最大80km/h以上! 海自の最速艦が「宗谷海峡」に急行か 戦車揚陸艦の出現に警戒監視
-
トヨタ「ちょっと小さな高級ミニバン」に反響多数!? 「渋い」「悪くない」 丁度良い“5ナンバー”ボディ×「アルファードグリル」採用!? 「豪華内装」もイイ「エスクァイア」とは何だったのか
-
15年ぶり全面刷新! 日産が「新型エルグランド」初公開! 元祖「キングオブミニバン」に史上初の「ハイブリッド」&高性能4WD搭載? 待望の「アルファード対抗馬」2025年度後半デビューへ
-
石破総理が…! ガソリン価格「1リットルあたり10円引き下げ」宣言も…賛否の声多し!?「暫定税率の廃止が先では」とも… 5月22日から、みんなの反響は
コメントの多い記事
-
ホリエモン、日本のタクシーに喝! 「行き先アプリ指定機能入れて」 ドライバーのミス連発の裏に潜む制度の壁とは?
-
石破総理が…! ガソリン価格「1リットルあたり10円引き下げ」宣言も…賛否の声多し!?「暫定税率の廃止が先では」とも… 5月22日から、みんなの反響は
-
クルマの要らない装備で「パワーシート」が上位に挙げられるのはなぜ? 超便利装備に「不要論」を唱える人の言い分とは
-
CX-5は8年でロードスターは10年! マツダ車のモデルライフが長いワケ
-
15年ぶり全面刷新! 日産が「新型エルグランド」初公開! 元祖「キングオブミニバン」に史上初の「ハイブリッド」&高性能4WD搭載? 待望の「アルファード対抗馬」2025年度後半デビューへ
あなたにおすすめのサービス
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
新車見積りサービス
店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!







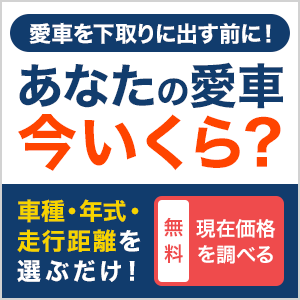
みんなのコメント