ディーゼルエンジンでカーボンニュートラル!マツダが目指す「市販車へのHVOドロップイン」は、日本でも実現するのか
スーパー耐久シリーズはまさに、内燃機関の未来を育む「走る実験室」。水素をはじめ合成燃料やバイオディーゼルなど、CO2排出量実質ゼロを目指したエンジン車たちが、それぞれの課題に向き合い、克服するために切磋琢磨しています。一方で気になるのは、そうした挑戦が市販車の世界に生かされるのは、果たしていつなのか?今回はディーゼルの活路を開こうとしているマツダの取り組みに注目。開発担当者の「市販化」に向けた展望など、ディーゼルファンはもちろん、内燃機関の将来に期待したいクルマ好きにはぜひ期待して欲しい「これから」のお話です。
ディーゼルに使えるカーボンニュートラル燃料「HVO」とは
2023年のENEOSスーパー耐久シリーズは、11月の富士4時間耐久を最後に今シーズンが終了しました。
●【くるま問答】ガソリンの給油口は、なぜクルマによって右だったり左だったりするのか
2021年から新設されたST-Qクラス(他のクラスに該当しない、オーガナイザーが認めた開発車両)ではマツダ、トヨタ、スバル、日産、ホンダ(ゼッケン順)の国内5社がそれぞれに得意とする分野での内燃機関搭載車両・計7台のマシンを投入、健闘しました。
そんな中で唯一、ディーゼルエンジン搭載車で参戦しているマツダ3(MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept)に使われるカーボンニュートラルな燃料(CNF)が、「HVO」と言われるバイオディーゼルです。
バイオマス由来の成分濃度が100%の「HVO100」としてマツダは、今シーズン前半は国内のバイオテクノロジー企業ユーグレナから、後半はフィンランドの大手エネルギー企業 ネステ社から供給を受けました。
HVOとは「HydrotreatedVegetable Oil(水素化植物油)」を略したもの。主に植物性の廃食油・非可食油を原料に、化学処理(水素化精製プロセス)を経て合成されます。
燃焼時にはCO2を排出しますが、生育過程で光合成によってCO2を酸素に分解する植物を原料としています。そのため、実質カーボンニュートラルな燃料としてHVOは、欧州において軽油代替燃料として急速に普及が進んでいます。
とくにスカンジナビア地域(スウェーデン、ノルウェー、デンマーク)を中心に、2022年2月時点で600カ所以上のガソリンスタンドでHVOが取り扱われている、とのこと(アウディ調べ)。
ボルボが2024年初頭に、全ディーゼルエンジン搭載モデルの生産を終了すると発表していますが、そのおひざ元であるスカンジナビア地域で内燃機関向けのインフラ整備が進んでいるというのも、不思議な話です。
ドイツでも2023年3月から、e-fuelなどとともに、給油所での100%合成燃料の販売が政府から承認されました。
すでにアウディは、2021年6月以降に生産された直4ディーゼルターボについて、HVO100の使用を承認しました。3L V6ディーゼルターボについても、2022年2月中旬時点で製造されたモデルすべてにつき認証。フォルクスワーゲンブランドでは、同型エンジンを搭載したトゥアレグにHVOを使うことが可能とされています。
HVOと軽油の価格差は約1割。積極的に使いたくなる値付けだ
取り扱う事業者によって、呼び名こそHVO100だったりRenewable Dieselを略したRD100だったりするので少々ややこしいのですが、基本的には同様のものを指します。
マツダが供給を受けているネステ社が、欧州向けに生産しているHVO100の量は、年間で約520万トンに達するそうです。もっとも、シェアだけを見れば、北米向けの年産約540万トンを合わせてもHVO100はすべての自動車向け燃料のうちの数%ほどにすぎません。
それでも、昨今話題のガソリン車向け合成燃料(たとえばe-Fuel)の供給量が年間数万トンレベルであることと比べると、欧州においてHVOはすでにかなりのボリュームで、環境に優しいモータリゼーションの取り組みを支えていると言えるでしょう。
注目すべきは、HVO100のCO2削減効果です。アウディが2021年に発表した試算によると、化石燃料由来のディーゼル(軽油)と比べて70~95%もの削減効果が期待できるといいます。
同様に、マツダが2023年半ばからスーパー耐久シリーズで実戦投入しているNESTE社製HVO100をもとにしたCO2削減率は、「つくる・はこぶ・つかう」までの全プロセスを入れると実に93.7%に達すると試算されています。
これはEUが設定する軽油排出量約86g/MJと比較したデータで、「はこぶ」に関しては横浜300km圏内の国内での輸送を含んだものです。
気になる価格は、マツダ調べによれば、一般軽油がリッター当たり1.60~1.75ユーロで販売されているのに対して、HVO100は1.74~1.90ユーロほどと、おおむね1割ほど高くはなっているようです。
とはいえ、日本とは違いもともと欧州において軽油は、自動車用燃料としてはガソリンよりも高級品ということもあり、いわゆる意識高い系のユーザーにとってはそれほど負担になる価格差ではありません。だからこそ普及が進んでいる、と考えてもいいでしょう。
3.3Lユニットはすでに対応。ただし解禁は最短で2024年から
日本の自動車メーカーの中でもマツダは、クリーンディーゼル車の開発に非常に積極的に取り組んできました。2012年2月のCX-5向け2.2Lを皮切りに、SKYACTIVE-Dと名付けられた新世代クリーンディーゼルエンジンを市販化。1.5L/1.8Lとバリエーションを増やしながら、現在ではロードスターとMX-30、軽自動車を除くほとんどのラインナップに設定しています。
リリースベースでは、SKYACTIV-D搭載車は2019年に国内累計販売台数累計50万台を達成しました。2023年からは次世代のラージ商品群向けに直列6気筒の3.3L SKYACTIV-Dを投入するなど(国内はCX-60から)、BEVトレンドが奔流のように押し寄せる中で、内燃機関の新たな価値を提案し続けています。
しかも早ければ2024年には欧州において、この3.3Lディーゼルエンジンに対してHVO100燃料の使用を解禁する計画まで、公表されました。
そもそもCX-60に搭載されているディーゼルエンジンは、ハード的にはすでにHVO100に対応しています。つまり今、そのままの状態でHVO100を給油しても、エンジンが壊れることはありません。
ではなぜ、解禁がすぐすぐではなく2024年になってしまうのでしょうか?そして日本向け商品のバイオディーゼル燃料対応は今後、どのような展開が予定されているのでしょうか??
その背景と事情、今後の展望について、マツダ株式会社 パワートレイン開発本部 エンジン性能開発部長 森永真一氏に直接、お話を伺うことができました。
部品レベルでの「品質保証」が課題。税法上の取り扱いも要注意
森永氏によれば、欧州における解禁に向けての大きな課題となっているもののひとつが、長期での使用に対するさまざまな部品の保証だと言います。各サプライヤーからの賛同が得られていないために、現状では万が一の故障に対するサポートが不誠実なものになりかねない、という懸念があるのだそうです。
「欧州のユーザーからはHVO100を入れてもいいだろうか、という問い合わせが少なくありません。しかし今は、入れても大丈夫だけれど部品に対する保証には対応していません、と答えるしかないんです」(森永氏)
実はこれこそが、「走る実験室」と言われるスーパー耐久レースにマツダが積極的に取り組む、ひとつの大きな理由です。燃焼技術やインジェクション関連の噴射コンポーネンツなどの信頼性を、レースという極限状態の中で長期にわたって検証することで、部品の品質に対する悪影響がないことを実証する=商品としての品質が担保されていることを確認するための取り組みに、他なりません。
マツダはスーパー耐久シリーズという舞台において、2021年からCNFへの対応技術を熟成、2023年からは第二段階として欧州HVO燃料への対応に向けた検証に取り組んできました。そこで得られたデータと知見をもとに最短で2024年には、欧州においてHVO100の使用に対するメーカー保証の継続が、宣言される予定です。
一方で、日本のCX-60はどうなるのでしょう? 実質的に日本仕様もHVO100には対応可能だと言います。けれど、今のところは日本において解禁宣言を出すのは、現実的ではなさそうです。なぜなら、そもそもHVOを一般的に手に入れることができないからです。
それではなぜ日本で、HVOが一般向けに販売されていないのでしょうか。それは軽油に課せられる実質的な負担が、ガソリンと比べて少なくなっているためです。具体的には、ガソリンのガソリン税にあたる軽油引取税がそもそも安く、さらにガソリン税のように消費税がかかりません。
だからこそ、軽油取引税における「軽油」の定義に合致することが求められるのですが、HVO100は軽油に対して比重がやや軽く、現行の規格にはあてはまりません。つまり税法上の規格を変更しなければ、HV100を軽油として正規に販売することはできないことになります。
もしもそれを無視して無許可で販売した場合は、脱税という罪に問われます。(一部、バイオディーゼルの製造・販売を行う事業者の中には、車検証に廃食油併用であることを併記すれば問題にならない、としている場合もあります)
「そのまま使える」ことを目指して日本でも公道にてテスト
とはいえ事業所向けには特例として、ディーゼル車へのHVO100販売がすでに始まっています。たとえば伊藤忠エネクス株式会社は、NESTE社のリニューアブルディーゼル(RD)を調達、グループが運営する東京都内の給油所において、公道実証を目的とする配送トラックなどへの給油販売を行っています。
また、大阪・関西万博関連工事を担う竹中工務店との協業により、現場で使用する建設重機などに対してRDを使用した際のエンジンへの影響についての検証が実施されています。同様の取り組みは、事業所で利用する乗用車にまで枠が広がっているようです。
国内では、ユーグレナがミドリムシ由来の第三世代バイオディーゼルを軽油に10%混合した燃料を、2021年に初めて一般向けに市販して話題になりました。ただしこれは10%のみの混合比率で、しかもあくまで試験的な2日間限定の取り組みです。
ユーグレナはスーパー耐久では、2023年半ばまでマツダにHVO100を提供していました。今後はマレーシアにおける合弁事業として大型プラントを建設し、本格的なHVO事業へと乗り出すことを明らかにしています。
欧州に比べれば、そうとう出遅れ感のある日本におけるバイオ燃料の普及活動ですが、東京都が「バイオ燃料活用における事業化促進支援事業」を公募、助成を行うなど、確かな変化は起きつつあります。HVOに限らず、バイオエタノール、e-fuelといったCNF導入には、JAMA(一般社団法人 日本自動車工業会)からも、たびたび要望的な形でのレポートが提出されています。
国策レベルでも、燃料のカーボンニュートラル化に対する検証は進められているようです。令和2年には環境省 資源エネルギー庁に対して、三菱総合研究所から「令和 2 年度燃料安定供給対策に関する調査等(バイオ燃料を中心とした綿国の燃料政策の在り方に関する調査)」と題したレポートが提出されています。そこでは、バイオエタノール、バイオディーゼル燃料、その他の代替燃料の導入状況や導入促進策、研究開発動向等に関する諸外国の動向がかなり細かく分析されています。
また、令和5年4月には経済産業省から、「エネルギー源の環境適合利用に関する石油精製業者の判断の基準」と題した告示が出されました。石油精製業者が化石エネルギー原料の有効な境適合利用を図るにあたって、バイオエタノールを混和して自動車用の燃料を利用する、とされています。
利用するバイオエタノールの量は、2023年~2027年度までが原油換算で年度ごとに50万キロリットルが目標。さらに2028年~2032年度までの5年間は、次世代バイオエタノールの利用目標量が、各年度ごとに原則1万キロリットルに設定されました。
おそらくは今後も、確実に進む燃料のカーボンニュートラル化に向けて今、まさに万全の体制をとるために、マツダはレースシーンでの検証・研究を進めています。
「マツダの取り組みとして将来的には、燃料の性状に応じて燃焼を最適化するプログラムの実現も目指しています。クルマ自体はそのままに、HVOが「ドロップイン」(それ用の改造やキャリブレーションなしで使用)で使えるように認証できれば、ユーザーに負担をかけることはありません」と、森永氏は語ってくださいました。
スモール商品群のSKYACTIV-DもドロップインOK。ただし・・・
さて、実際に法整備が進み、HVOが一般的にガソリンスタンドなどで販売されることになったと仮定しましょう。ここで気になるのは、CX-60よりも前の世代でも使ってもいいのか、ということです。いわゆるスモール商品群と呼ばれるクルマたちに搭載されている1.5L~2.2LのSKYACTIV-Dには、給油しても大丈夫なのでしょうか。
森永氏によれば、ここでもマツダはドロップインでの対応に向けた、検証を行っているそうです。
2022年6月から、日本国内では中日リース株式会社系列の名港潮見給油所において、ユーグレナが手掛ける「サステオ」の販売が始まっています。バイオディーゼル混合率は20%なので、車両側のキャリブレーションなどは必要ありません。
価格はリッター300円と、軽油(2023年11月21日現在:132円/L)と比べると、やはりお高い印象ではありますが。
一方、森永氏によれば初代CX-5以降に販売されたマツダのディーゼルモデルはすべて、HVO100を使っても壊れることはないのだそうです。ただし、先に触れた「保証」の対象にはならないことに加えて、フィーリング面でちょっとした変化が起きる可能性があるそうです。
原因は、軽油よりもセタン価が高い(約30%)=着火しやすいというHVOの性質によるもの。具体的には、エンジン回転数によっては燃焼するポイントが少しずつズレるケースが考えられるために、ディーゼル特有のノック音の発生具合や音量が、軽油使用時とは異なってくる可能性があるのだそうです。
商品としての品質の問題というわけですが、裏返せば「法的そして保証面での問題をクリアした上で、ユーザーがフィーリングの変化をカーボンニュートラルフューエルならではの特性として理解してもらうことができるのなら、スモール商品群に対してもマツダが解禁を宣言する可能性はあります」(森永氏)。
その場合はもちろん、メーカー保証が継続適用される、と考えてもいいでしょう。
ユーザー側はHVOに興味津々。LCAではBEVを逆転する可能性も
スーパー耐久レースのイベント広場に設けられたマツダブースでは、ボディサイドにBIO FUELと描かれたCX-60と、初期型のレース仕様のデミオが展示され、CNFに関する掲示物が並べられていました。
訪れたユーザーの中には、マツダだけでなく他メーカーも含めたディーゼル車に乗っていて、今後、どこまで愛車と気後れすることなく付き合えるのか気になる、という人が少なくなかったそうです。
詳細は後述しますが、マツダが試算したLCA(ライフサイクルアセスメント)という手法でのCO2排出量の優位性比較が、ちょっと興味深い結論を導いています。
2019年に論文発表されたレポートによれば、20万kmを走るという前提での部品・車両の製造段階から廃棄・リサイクル段階までに排出されるCO2の総量を試算した場合、実は、通常の軽油を使ったクリーンディーゼルであっても、従来の日本における製造過程・発電インフラを継続使用した場合のフルバッテリーEVに対してわずかに優位性が保たれる可能性が高いといいます。
もちろん、製造技術や廃棄・リサイクル技術の進化にともなって、それぞれの数値は変わります。しかしHVO100でなく、すでに日本国内でも少しずつ進んでいるバイオ由来20%混合の燃料であっても、CO2排出量は大幅に抑制できるかもしれません。
運転する楽しさを与えてくれるパートナーとしての進化
MAZDA SPIRIT RACINGによるレース活動には、他にも恩恵があります。カーボンニュートラルだけでなく、ディーゼルエンジンの効率向上の研究・開発にも取り組んでいます。富士最終戦で走ったマツダ3は最高出力300ps/最大トルク530Nmを発生させるなど、ここ1年の間にも大幅なポテンシャルアップが図られています。
そうした技術のすべてが市販車にフィードバックされるかどうかはわかりません。あるいはさらに一歩進んだ技術、たとえばハイブリッド化も含めたさらなる高効率化が検討される可能性もありえるでしょう。
いずれにしろスーパー耐久における自動車メーカー5社の取り組みは、これからも内燃機関が環境に優しいテクノロジーとして、そして運転する楽しさを与えてくれるパートナーとして、まだまだ活躍できる可能性を切り拓いてくれるものであることは確かです。
可能ならそれに先行する形で、バイオ燃料にせよ合成燃料にせよ、さまざまなカーボンニュートラル燃料の普及が日本でも順調に進んでいくことを願いたいものです。
同時に、クルマを使うユーザーの側がそうした変化を理解し、認識を深めることで普及が促進され、さらに供給量が増えていけば価格についてもそうおうの競争力をつけることができる・・・という、好循環が生まれることに期待したいですね。
【付記】ライフサイクルアセスメントでの試算は「考え方」によって違いが
走行時のCO2排出量のみに限れば、BEVは非常に環境に優しく、内燃機関搭載車の評価は厳しいものにならざるを得ません。
しかし自動車使用時以外の部品および車両製造時や廃棄・リサイクル段階まで含めたCO2排出量を定量的に評価する、ライフサイクルアセスメント(LCA:CO2等等価排出量)という計算手法に則ると、環境負荷に関する評価が変わってくる可能性があります。
2019年に発表されたマツダのLCA研究活動に関するレポート「Estimation of CO2 Emissions of Internal Combustion Engine Vehicleand Battery Electric Vehicle Using LCA」の中では、(a)EU(b)日本(c)米国(d)中国(e)オーストラリアの5カ国について、エリアごとの電力の状況や燃費/電費、生涯走行距離といった要素を加味した、CO2排出量の優位性を評価するグラフが掲出されています。
そこでは生涯走行距離20万km、BEVは16万kmで駆動用バッテリーを交換する、という仮定でシミュレーションを実施。欧州と日本の環境下では製造時に大量のCO2を排出するBEVがディーゼルに対する「遅れ」を挽回するのに、走行距離約11万km走る必要がある、と試算されています。
しかもいったんは逆転した排出量が、BEVの駆動用バッテリーが交換される16万km付近で再逆転、ディーゼルの方がトータルでのCO2排出量が少なくなり、さらに20万km時で廃棄・リサイクルされる段階でもわずかにBEVのほうが環境負荷が多い、という結果が出ています。
つまり、このどこかの段階でHVOを利用し始めれば、少なくとも現状の発電環境やバッテリー製造の過程を踏襲している限り、クリーンディーゼルはBEVよりもLCAでの環境負荷が少なくなる、ということが推察されるわけです。
BEVが環境に優しくない!というわけでは決してない
だからと言ってBEVが環境に優しくない!というわけでは決してないので、ご安心を。
たとえばフォルクスワーゲンが2019年に発表したEV(e-ゴルフ)とディーゼル車(ゴルフTDI)のLCA比較では、20万km時点でのLCAは圧倒的に電気の力が優位である、と結論付けています。
しかも将来的にリチウムイオンバッテリーの製造段階でのCO2排出量が25%削減され、充電の原資も再生可能エネルギーオンリーとなることで、その差がますます開いていく可能性が大きいことを示唆しています。
LCAに関しては日産もわかりやすい指標として公式HPで試算データを公表しています。リーフ、アリア、サクラについて、同クラスのガソリン車との対比ではLCAを約17~32%削減していると言います。さらに日産では生産段階だけでなく、廃棄段階でもバッテリーの積極的リサイクルに取り組むなど、環境負荷低減の可能性を模索しています。
試算によっては、HEVのLCA評価がトップに躍り出る場合もあるようです。ちなみにエネルギー効率の観点に立った場合、HEVに合成燃料100%を使うのがもっとも効率が高い、という研究報告もありました。
CN達成に向けてのクルマ動向を総括してみるなら、JAMAが2022年9月に発表した「2050年カーボンニュートラルに向けたシナリオ分析」というレポートも参考になります。
JAMAは2050年CN達成に向けて全力を傾けています。そのためにIEA(International Energy Agency:国際エネルギー機関)が提示した完全なるBEV・FCEV化というシナリオをベースに、削減目標を達成する可能性について異なるシナリオについても検証しています。
そこでは、完全ではないけれど電動化を積極的に進めるシナリオに加え、CN燃料を積極的に活用するケースも検討し、その結果、BEV・FCEV向けの脱炭素化を徹底した電気の供給とともに、今後も販売台数が飛躍的に伸びる途上国や、先進国においてもすでに販売されている車両のために、CN燃料が必要である、と指摘しています。
燃料の供給や発電インフラ、クルマの使われ方といった地域性の違いを精密に見極めながら、それぞれのエリア事情に最適化されたクルマたちを開発・販売していく必要性は今後、ますます高まっていくことになりそうです。
本当の意味での「マルチパスウェイ」という目線に立てば、スーパー耐久シリーズでの「共挑」は、非常に理にかなった取り組みなのだということを、改めて感じました。来シーズンはより多くの自動車ファンに、注目してもらえることを期待したいものです。
[ アルバム : ディーゼルエンジンでカーボンニュートラルを実現 はオリジナルサイトでご覧ください ]
こんな記事も読まれています
この記事に出てきたクルマ
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!
愛車を賢く売却して、購入資金にしませんか?
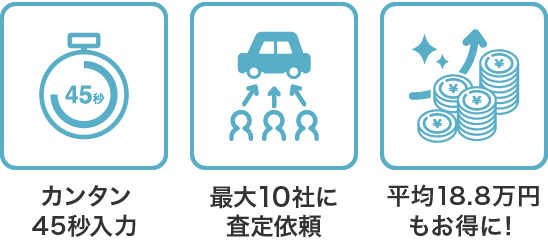
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!
愛車を賢く売却して、購入資金にしませんか?
おすすめのニュース
-
-
AUTOSPORT web1
-
motorsport.com 日本版0
-
Auto Messe Web6
-
motorsport.com 日本版0
-
-
AUTOSPORT web0
-
motorsport.com 日本版1
-
-
愛車管理はマイカーページで!
登録してお得なクーポンを獲得しよう
おすすめのニュース
-
-
LE VOLANT CARSMEET WEB12
-
motorsport.com 日本版0
-
WEB CARTOP10
-
-
-
WEB CARTOP0
-
日刊自動車新聞0
-
-
-
-
-
motorsport.com 日本版0
-
-
-
バイクのニュース0
-
月刊自家用車WEB2
-
ベストカーWeb12
-
-
-
AUTOSPORT web0
-
THE EV TIMES1
-
motorsport.com 日本版0
-
レスポンス16
-
motorsport.com 日本版0
-
-
-
AUTOSPORT web1
-
motorsport.com 日本版1
-
業界ニュースアクセスランキング
-
660ccの「小さな高級車」って最高! めちゃ上品な「オトナの軽自動車」に称賛の声! ダイハツ本気の「ラグジュアリー仕様」が凄かった!
-
もしやヴェゼル窮地!? お、値段以上に立派なバカ売れWR-Vってコスパ最強じゃない!?
-
「覆面パトカー」どうやって見分ける? 「クラウン」だけではない!? 「走り方」や「ナンバー」にも注目! 共通する特徴とは
-
マツダ「すごいロードスター」実車公開! 国内初の「2リッターエンジン」搭載した“最強ソフトトップ仕様”! 市販前提「スピリットRS」登場!
-
古い「ETC」使えなくなるってマジ!? 「勘弁して」と嘆きの声も! 使用不可な「車載器」の見分け方は?「10年以上使用」は要注意か








みんなのコメント
燃料の価格がほどほどな事
供給インフラの問題
車両メーカーが使用を認めること
話が長いよ、、