世界一有名な自動車広告スローガン 14選 心に刺さる名フレーズ特集
人々の心に残る名フレーズ
これまで存在したほぼすべての自動車メーカーは、自社をアピールするためにさまざまな「スローガン」を掲げてきた。キャッチフレーズやキャッチコピーなど呼び方はさまざまだが、あまりに有名なため日常的に使われるようになったものも少なくない。
【画像】有名なスローガンを体現するクルマたち【アウディ、BMW、日産などの代表的なモデルを写真で見る】 全111枚
スローガンは時代によって変化するのが一般的だが、遠い昔に作られたものが、今でも使われ続けているケースもある。そこで、最も有名なスローガンにまつわる物語と、その企業が現在使っているスローガンを見ていこう。
アウディ:Vorsprung durch Technik(1)
80年代初頭、アウディはBMWやメルセデス・ベンツのライバルというよりも、フォルクスワーゲンの高級版と広く見なされていた。しかし、クワトロのようなエキサイティングな新型車が登場すると、そうもいかなくなってくる。英国の広告代理店バートル・ボーグル・ヘガティ(BBH)は、そのイメージチェンジを任された。
1982年、BBHのジョン・ヘガティ氏は、アウディのインゴルシュタット工場を訪れ、インスピレーションを求めた。彼は、工場の壁に貼られた色あせたポスターの「Vorsprung durch Technik」という文言に目を留める。これは、「技術による先進」を意味し、多くの消費者がドイツ車に憧れを抱いていたことを文字どおり伝えるものだ。
アウディ:Vorsprung durch Technik(2)
ヘガティ氏は後に、「あれほどまでに人気が出るとは思ってもみなかった」と回想している。「すべてを語りながら、実は何も語っていないのです。でも、人々の想像力をかきたてるものでした」
このように、「文字通りのわかりやすさを追求する」というコミュニケーションにおける基本原則は、見事に破られたのである。テレビCMで、ジェフリー・パーマーという「退役軍人」の声を使ったのも、天才的な判断であった。
このフレーズは、米国、英国、フランス、カナダなど非ドイツ語圏の国々でも使われるようになった。
アウディの現在
クルマの高性能化が進むにつれ、今日のアウディは、40年前に憧れていた高級車ブランドとして大いに認知されている。最近、アウディは「For the epic or everyday(壮大なスケールから日常まで)」というような新しいフレーズを使うこともあるが、いずれも「Vorsprung durch Technik」の足元にも及ばないだろう。
アウディは2010年、このスローガンを商標登録することに成功した(登録にあたり欧州で法廷闘争も起きたが、その話は割愛)。また、アウディは最近、欧州市場で一部モデルの上級グレードに「Vorsprung」の名を使っている。
どの業界でも、40年前の広告スローガンが今も現役で使われていることは少ないが、「Vorsprung durch Technik」は時代を超えて受け継がれているようである。
メルセデス・ベンツ:Engineered like no other car in the world(世界のどのクルマにも真似できない設計)
第二次世界大戦中、ダイムラー・ベンツの工場は激しい空襲を受けたが、50年代半ばには立ち直りつつあった。そして、190SLと300SLという2台の記念すべきモデルが世界デビューを飾る。同時に、英語圏の輸出市場を視野に入れた「Engineered like no other car in the world(世界のどのクルマにも真似できない設計)」というスローガンも初めて採用された。
このスローガンはその後、米英を含む世界中の国で、何十年にもわたって使われることになる。シンプルで効果的、そして率直に言って「事実」であった。当時、自動車の信頼性が現代に比べて非常に低かった時代、メルセデスの製品は良くできているということを声高に謳ったのである。
1992年に発売されたSクラスW140(写真右)でも、オーバーエンジニアリングを強調するために使用された。
メルセデス・ベンツの現在
1990年代半ばに、それまでよく働いてきたスローガンはひっそりと廃止された。40年の時を経て、さすがにもう限界だと思ったのだろう。また、信頼性においても日本車という強力なライバルが現れたことで、このスローガンの正当性が揺らいだのかもしれない。
1989年のレクサスLS400は、メルセデスのようなブランド力にこそ欠けるものの、驚くべき快適性と、トヨタから受け継いだ岩のような信頼性が特徴であった。実際、メルセデスはこれに驚き、W140の発売を遅らせて、この予想外の挑戦者を撃退するために改良を加えたと言われている。
その後、クライスラーとの合併、北米での生産開始、そしてメルセデスのオーバーエンジニアリングを意識的に取り除こうとした結果、規格ではなく予算で作られたようなモデルが登場し、一時期ブランドの評判に影響を及ぼしたことがあった。現在はその時期からほぼ回復し、再びドイツの高級車メーカーを代表する販売台数を誇っている。
現在のスローガン?いやいや、100年以上前から使われているスリーポインテッド・スターが、すべてを語っている。
BMW:The Ultimate Driving Machine(究極のドライビングマシン)
70年代初頭、GM出身のボブ・ラッツがBMWのセールス&マーケティング責任者に就任する。当時、ドイツの自動車会社が外国人(ラッツは米国人)をこのような上級職に就かせることは極めて異例だった。しかし、米国市場での地位を確立しようとするBMWにとって、彼はまさにうってつけの人物だったのだ。
当時、「The Sportsman’s Car(スポーツマンのクルマ)」という米国向けのスローガンに失望していたラッツは、消費者の心に刺さる文言を求め、広告代理店のAmmirati&Puris社と協力。走り好きのドライバーに選ばれるブランドとしてBMWを確立するため、新しいスローガンを探したのである。
その結果、「The Ultimate Driving Machine(究極のドライビング・マシン)」というスローガンが誕生した。伝えたいメッセージを曖昧にすることなくシンプルに表現している。しかし、多くの競合車が快適性を重視していた当時としては、一味違ったアプローチとなった。このスローガンは1973年に米国で使用され始め、その後他の市場にも広がり、瞬く間にBMWの代名詞となった。
BMWの現在
「The Ultimate Driving Machine」は現在も使用されており、BMWの英語版ウェブサイト(米国や英国向け)を訪れると、たいてい最初に目にするのはこのスローガンである。たびたび、海外で物議を醸した「Joy」(2009年に初めて使用)などのシリーズが登場することもあったが、いずれも短命に終わっている。「Joy」はあまり受けが良くなかったようで、2012年に廃止されると、再び「Ultimate」が使われ始めた。
日本で有名なのは、「Freude am Fahren(駆けぬける歓び)」というスローガンだろう。英語圏でも同じ意味合いの「Sheer Driving Pleasure」が使われており、「Ultimate」と並ぶBMWの二大スローガンといえる。
BMWは2018年ごろから、英語圏の市場でもドイツ語を用いて、ドイツらしさをアピールするようになったと思われる。そのため、しばしばBMWの正式な社名である「Bayerische Motoren Werke」が使われることもある。
いずれにせよ、「究極のドライビングマシン」で「駆けぬける歓び」という、一貫性のあるスローガンが使われているのは素晴らしいことだ。半世紀近く前に作られた文言でありながら、今なお鮮烈に感じられるのは、マーケティングの成功と言えるだろう。
クライスラー:Imported From Detroit(デトロイトからの輸入車)
94年の歴史を持つクライスラーの最も有名なスローガンが、2011年に作られたものだというのは、何度も経営危機に陥った同社の不手際を暗示しているといえるかもしれない。
それにしても、「Imported From Detroit(デトロイトからの輸入車)」というスローガンは刺激的だ。多くの米国人は、自国の自動車産業の栄光と衰退を体現するモーターシティを、犯罪や麻薬にまみれた異国の地と感じているということを、このスローガンは暗に揶揄しているのだ。
「Imported From Detroit」は、デトロイトのラップスター、エミネム(写真)が出演する新型クライスラー200のテレビCMもあって、大いに注目を集めた。広告代理店のWieden + Kennedy社が制作したこのCMは、クライスラーとその生まれ故郷の最近の窮状を、エミネムの曲「Born of Fire」をキーに、軽快に表現している。そして、CMの最後でエミネムは、「これがモーターシティだ、そしてこれが俺たちのしていることだ」と訴える。
クライスラーの現在
この素晴らしいCMの後、みんなすぐにクライスラー200を買って、二度とBMW 320iを買おうとは思わなくなり、みんな幸せに暮らしましたとさ……とはならなかった。残念ながら。自動車業界は厳しい。たった1本のCMで、200のような平凡なクルマやクライスラーというブランドを救うことはできないのである。
2016年、フィアット・クライスラー社のセルジオ・マルキオンネCEOは、クライスラー200とその兄弟車ダッジ・ダートについて、「我々がこれまで行ってきた事業の中で最も金銭的な報酬が少ない事業」と発言した。200は同年末に廃止され、クライスラーのラインナップは現在、ミニバンのパシフィカ(写真)とボイジャー、そして2004年発売の300だけになっている。300は2023年モデルで生産終了となる予定だ。
クライスラー・パシフィカは平凡なミニバンだが、グーグルから分社化したウェイモ(Waymo)との提携によって、自動運転車のテスト車両として使用されている。……現在のクライスラーで、それ以外に特筆すべき点がないのが残念だ。加えて、「Imported From Detroit」というスローガンももはや通用しない。米国で販売されるクライスラーは、すべてカナダで製造されるようになったからだ。
クライスラーはかつて偉大なイノベーターだった。ディスクブレーキ、電動ウィンドウ、パワーステアリングなどを搭載した世界初の市販車を世に送り出したのだ。しかし、今日では、親戚にあたるジープとラムの影に隠れてしまっている。
ジャガー:Grace, Space, Pace(グレイス、スペース、ペース)
このスローガンは、1930年代にジャガーではなくMGが新型のSAとWAを宣伝するために、「Space, Grace, Pace(スペース、グレイス、ペース)」と使ったのが始まりだ。そして戦後、ジャガーの創始者ウィリアム・ライオンズがMk5セダンを宣伝するために転用し、その後の歴史に名を残すことになったのだ。
「Grace, Space, Pace(グレイス、スペース、ペース)」は韻を踏んでいて舌の上をよく転がるフレーズであり、ジャガーの信条を簡潔な表現で伝えている。数十年にわたり、ほとんどのモデルがその理念を十分に発揮してきた。しかし、このスローガンは、ジャガーがブリティッシュ・レイランド(BL)に吸収された、英国系自動車メーカーにとって暗黒時代といえる1960年代に消滅した。
ジャガーの現在
ジャガーは1984年にBLから脱却して独立を果たすが、1989年にフォードに吸収された。ジャガーは現在、公式には「Grace, Space, Pace」という言葉を使用していないが、これに由来する車名を新しいSUVシリーズに与えたことで、英国では称賛を集めた。
2015年にFペイス(F-Pace)を発表したデザインチーフのイアン・カラム氏は、ジャガーは常にスタイルとスピードを追求してきた一方で、スペース(広さ)が欠けていたことを認め、同社初のSUVでそれを叶えることにしたと語っている。
昨今のジャガーの主要スローガンは「The Art of Performance」であり、とても風通しの良いものではあるが、50年代のオリジナルには及ばないだろう。
ランドローバー:The best 4 x 4 x far(間違いなく最高の4×4)
ランドローバーは、どこにでも行けて何でもできることを常に謳ってきた。創業当初は「The go anywhere vehicle(どこでも行けるクルマ)」「Britain’s most versatile vehicle(英国で最も多用途なクルマ)」といったスローガンを掲げていた。
1986年、ランドローバーはさらなる高みを目指す。ウェールズ中部にある高さ70mのダムを、ランドローバーがほぼ垂直によじ登る様子を撮影。50年代の名作戦争映画『暁の出撃(原題:The Dambusters)』の音楽と『スタートレック』でおなじみパトリック・スチュワートのナレーションに乗せて、テレビCMとして放映したのだ。ここで使われたのが「The best 4 x 4 x far(間違いなく最高の4×4)」である。
これは、四輪駆動を示す「4×4(フォー・バイ・フォー)」と、「遥かに、群を抜いて」という意味の熟語「by far(バイ・ファー)」をかけたダジャレだ。
その約30年後、BBCの人気番組『Top Gear』のリチャード・ハモンドが、別のダムでこのCMの再現を試みた。チャレンジは見事に成功し、ハモンドは「テレビの魔法」と表現しているが、実はオリジナルのCMでは上部で巨大なウインチが使われていたのである。
ランドローバーの現在
「The best 4 x 4 x far」のスローガンは、今でも時々、ランドローバーの広告やプレゼンテーションで使われている。しかし、ランドローバーの主要スローガンは「Above & Beyond(はるか先へ)」であり、これはこれでいいのだが、筆者はやはり前者を好む。
1986年当時、ランドローバーに直接的なライバルはほとんどいなかったが、今ではフォルクスワーゲンからロールス・ロイスまで、世界中のほぼすべての自動車メーカーが何らかの形でSUVを製造している。クルマの電動化も着々と進む中、ランドローバーがこの先どのようにして存在感を発揮していくのか、注目したい。
日産:You can with a Nissan(日産でできること)
長い間、日産は多くの海外市場で「ダットサン」の名で販売されており、現在の日産ブランドは1970年代から徐々に導入された。米国や英国では、1984年にダットサンから日産に切り替わっている。日本ならまだしも、海外の消費者から見れば日産はいわば「新しいブランド」であり、改めて認知度を高める必要があった。
そこで、英国では、「You can with a Nissan(日産でできること)」という韻を踏んだフレーズを作成。写真のテラノII(スペイン製造で、日本向けにはミストラルとして輸出)のようなSUVの宣伝に使うことで、それなりの効果を発揮した。
米国では、「The name is Nissan(その名は、日産)」という超ストレートな表現が使われた。また、高性能モデルの宣伝においては、「Built for the Human Race」という、人類(Human Race)とレース(Race)をかけた巧みなフレーズが用いられたことがある。
日産の現在
いわゆる「ライフスタイル」に焦点を当てたマーケティングが主流の現代において、日産のスローガンは広告の山に埋もれてしまっている。日本では、2015年から使われ始めた「やっちゃえ日産」がクルマ好きの間では有名だが、その後の「ぶっちぎれ 技術の日産」や「日産がやらなくて、ほかに誰がやる」などは正直ちょっと印象が薄いのではないだろうか。
なお、米国・英国で掲げられているスローガンは「Innovation that excites(ワクワクするようなイノベーション)」であり、日本向けと同じように「技術」を推していることがわかるが、面白みはあまり感じられない。
フォルクスワーゲン:Think Small(小さく考える)
1950年代、フォルクスワーゲンは北米への進出を目指したが、ある問題があった。当時、市場を席巻していた艀(はしけ)のように巨大なアメ車に比べ、ビートルは非常に小さなクルマだったのだ。そこで、このことを恥ずかしがるのではなく、堂々と、小さなクルマの素朴な良さをスローガンに表現したのである。
「Think Small(小さく考える)」というスローガンは、1959年に米国の広告代理店ドイル・デイン・バーンバック(DDB)でコピーライターを務めていたジュリアン・コーニッヒ(1921-2014)が考案したものである。広告の大部分は白抜きで、ビートルのサイズを強調。その下にテキストで駐車のしやすさ、燃費、保険代や修理代の安さなど「小さい」ことのメリットを訴求した。
この広告は大成功を収め、60年代後半には北米で年間40万台以上の販売を達成。1999年、マーケティング業界誌『アドバタイジング・エイジ』によって、今世紀最高の広告キャンペーンに選ばれている。
フォルクスワーゲンの現在
フォルクスワーゲンは、「ドイツ車」というものに対するステータスや信頼性、性能、技術水準などの面で、世界中の消費者が抱くポジティブなイメージに支えられてきた。これは、他のドイツの自動車メーカーも同様だろう。
そのため、21世紀に入ってからもこのブランド力を利用し、2008年からは米国をはじめ多くの英語圏市場で「Das Auto」というスローガンを使っている。これは、ドイツ語で文字通り「クルマ」を意味する言葉であり、しばらくは成功とみなされていた。そう、しばらくの間は。
2015年、いわゆるディーゼルゲート事件が発生し、同社の評判に甚大なるダメージを与えてしまった。これにより、「Das Auto」のやや帝国主義的なスローガンが不吉な空気を帯び、スキャンダルが発覚してからわずか3か月で使用を取りやめることになった。
現在、フォルクスワーゲンのロゴの下に書かれているのは、すばり「Volkswagen」である。2019年のフランクフルト・モーターショーでは、新しく簡素なロゴとブランド・アイデンティティを発表。新たなスタートを切ろうとしている(写真)。
ボルボ:For Life
この驚くほどシンプルでスマートなボルボ・カーズのスローガンは、フォードが同社を買収した直後の1999年に初めて使用されたものだ。このスローガンの秀逸な点は、ボルボが安全性、耐久性、オーナーの生活にフィットする能力、他のブランドを買う必要がないこと(理論的には)、さらには環境への配慮を重視していることを、「For Life」というたった2つのシンプルな単語で表現しているところである。
「For Life」を日本語に直訳するなら「一生」となるが、スローガンとして意訳するなら、「生きるために」といったところだろうか?
フォード傘下の11年間で、ボルボはモデルレンジを拡大し、2002年には大型SUVであるXC90を発売して大ヒットを飛ばした。GMがスウェーデンのサーブを所有し、消滅させるよりははるかにマシな結果を残している。
ボルボの現在
「For Life」は、ボルボ・カーズが2010年に中国のジーリー(吉利汽車)の傘下に入ってからも、20年近くメインスローガンとして掲げられてきた。ジーリーの資金力を活かし、ボルボはモデルレンジの若返りと拡大を図り、ドイツの高級車ブランドに対抗するライバルとして台頭してきている。
それに伴い、ボルボは2018年に新しいスローガンと社是である「Freedom to Move(モビリティの自由)」を発表した。ボルボのホーカン・サミュエルソンCEO(当時)は、「Freedom to move……それは、まさにクルマの美点です。いつでも好きな場所に移動することができますが、それはもちろん、持続可能で、パーソナルで、安全なものでなければなりません」と語っている。
キャデラック:The Standard of the World(世界のスタンダード)
壮大なスローガンだが、欧州などで華々しい活躍を残していないことを考えると皮肉に聞こえてしまう。このスローガンは、100年以上前の英国での出来事にそのルーツを辿ることができる。1908年、RAC(王立自動車クラブ)は、キャデラックの製造工程における高度な「標準化」を評価し、権威あるトロフィーを授与したのだ。
まず、無作為に選ばれた3台のキャデラック・モデルKが、サーキットで10周、約40kmを走る。そして、完全に分解された後、地元のディーラーから提供された89個の部品を混ぜ合わせ、再び組み立てたところ、800kmの距離をトップスピードで走ったのである。これは、当時のキャデラックの技術力、製造力の高さを示す偉業とされた。
こうして、キャデラックは自らを「The Standard of the World(世界のスタンダード)」と呼ぶようになり、このスローガンは何十年にもわたって広告に掲載された。その後、標準化が進みむと、エレガンスやラグジュアリー、パワーを意味するスローガンに変更された。キャデラックは走る宮殿であり、余裕のパワー、堂々としたデザイン、大排気量のV8を特徴としていた時代を象徴するものだ。
キャデラックの現在
2022年のキャデラックは、世界のスタンダードと呼べるほど器用なものではない。なぜなら、キャデラックは多くの市場から姿を消しているからだ。今は米国と中国での市場競争に時間、エネルギー、資金を投入しており、ドイツのアウディ、英国のジャガー、日本のレクサスは、キャデラックを脅威とは感じていないはずだ。
しかし、2019年に導入した「Rise Above(超越)」というキャッチフレーズは、「The Standard of the World」と誇らしげに宣伝していた時代をほんの少しだけ彷彿とさせる。キャデラックは2000年代、万人向けのブランドになろうとしたため、確固たるイメージと方向性を見失ってしまった。キャデラックの車種は、有能でありながら調和がとれていないことが多かったのだ。
2010年代後半、キャデラックは原点に戻り、ラグジュアリーとアメリカン・スピリットを再び重視することになる。同社にとって「Rise Above」とは、障害を克服し、ライバルを追い越して、再び世界中の消費者が欲しがるブランドになるという意思表示であろう。
消費者にとっては、一生懸命働いて人生の難局を乗り越え、お金を稼いで良いクルマを買うという、憧れのスローガンなのだ。2019年に使われた広告では、SUVラインナップを強調していたので、文字通り「ステップアップ」を意味するのかもしれない。
シボレー:The Heartbeat of America(アメリカのハートビート)
シボレーは、自社製品を「The Heartbeat of America(アメリカのハートビート)」として売り出すことで、米国の消費者のハートを掴もうとした。このスローガンが導入された1985年、シボレーは日本車の台頭により、市場シェアが低下していくのを目の当たりにしていたのだ。
「The Heartbeat of America」は、シボレーのクルマが国土に根付いたものであることを示すスローガンだ。トラックは農場で働き、バンは西海岸から東海岸まで荷物を運び、乗用車は子供たちを学校に連れて行く。ノスタルジーと親しみやすい愛国心が感じられる。
このスローガンを使ったテレビCMは、キャッチーなジングルが特徴で、シボレーのメッセージを消費者の心に定着させるのに一役買った。
シボレーの現在
シボレーは2013年、「Find New Roads(新たな道を切り開く)」を新たなスローガンに採用した。親会社のゼネラルモーターズ(GM)が2009年に破産を申請したため、イメージを刷新する必要があったのだ。その根底には、シボレーが学び、進化し、変化してきたというメッセージが込められている。
「Find New Roads」は、後述するフォードの「Go Further(さらに先へ)」とよく似ているが、けっこう曖昧な表現だ。ダイレクトにメッセージを伝えるのではなく、消費者の想像力に任せている。シボレーの「The Heartbeat of America」というスローガンは、ほとんどすべての米国人が知っていたが、「Find New Roads」はそれほど有名なものではない。
それは、自動車を運転する人が雑誌、テレビ番組、ラジオに触れる機会が昔よりずっと少なくなったからかもしれない。Netflixでシボレーの広告を見ることはない。スローガンを定着させることは、1980年代より難しくなっている。
ダッジ:Grab Life by the Horns(人生の角をつかめ)
英語の慣用句に「Grab the bull by the horns」または「Take the bull by the horns」というフレーズがある。いずれも直訳すると「雄牛の角をつかめ」となり、「困難に立ち向かえ」といった意味合いが含まれている。ダッジはこれをもじって「Grab Life by the Horns(人生の角をつかめ)」とし、2001年にスローガンに採用した。
ダッジのロゴは巨大な角を持つ雄羊(牛ではない)で、大胆で恐れを知らないブランドイメージを表現するものだ。ダッジに乗る人は、平凡なクルマで通勤している人よりも大胆で、刺激的な人生を歩んでいる……。それが、このスローガンのメッセージだ。
ダッジのマーケティング部門は、2000年代前半に退屈なクルマの代名詞となっていたトヨタを意識していたのだろうかと邪推してしまう。「Grab Life by the Horns」は、多くの米国人に馴染みやすいフレーズだったので、すぐに定着した。しかし、広告スローガンとしては少し長かったので、2007年に「Grab Life(人生をつかめ)」に短縮している。
フォード:Built Ford Tough(タフなフォード車)
「Built Ford Tough(タフなフォード車)」というスローガンは、1979年のモデルイヤーに米国でデビューした。度重なる石油危機に見舞われた激動の10年を終え、1980年代を迎えようとするフォードが掲げたものである。ピックアップトラックのFシリーズが1977年にベストセラーとなったことを受け、タフネスを強調して勢いを持続させるスローガンとして構想された。
スローガンには、主要ライバルであるシボレーやダッジよりも高い耐久性を持つという意味が込められている。短くて覚えやすい、シンプルなメッセージということもあり、驚くほどの広告効果を発揮した。特に、米国でフォードを支えているピックアップトラックのオーナーの心に響いた。
「Built Ford Tough」は何十年にもわたって使用され、ナンバープレートフレーム、Tシャツ、帽子など、さまざまなものに使用された。米国のディーラーも採用しており、現在でもよく見かける。「Built Ford Proud(誇り高いフォード車)」も使われている。
フォードの現在
フォードは2009年の経営危機から立ち直った後、2012年に現在の「Go Further(さらに先へ)」を展開した。「Go Further」は、これまでのスローガンとは異なり、消費者だけでなく従業員にも語りかけるように作られた。
同社の経営陣によると、このスローガンの根底にあるのは、フォードが自己満足に浸っているうちに会社組織全体が劣化し、危うく倒産に追いやられるところだったというメッセージである。インターン生から役員、そしてすべての従業員に、健全で利益を上げられるよう努力を求めるために採用されたようだ。
こうした意味合いは、フォードの従業員であれば理解できるだろうが、クルマを買おうとしている消費者にはちょっと難しいだろう。クルマでさらに遠くへ行く?新しいSUVでさらに荒野を目指す?正直なところ、どのようにでも受け取れる曖昧なスローガンであり、明確な定義がなく、フォード車との関連も不透明なのが実情だ。
GMC:We Are Professional Grade(わたし達はプロフェッショナル・グレードです)
GMCのピックアップトラックやSUVは、兄弟ブランドのシボレーとほとんど差別化されてこなかったが、概して高価なものが多い。2000年には「We Are Professional Grade(わたし達はプロフェッショナル・グレードです)」という直球のスローガンを掲げ、兄弟車よりも過酷な要求に応えることができると訴えた。
しかし、このスローガンからはちょっと怪しいニオイが漂ってくる。というのも、エンボイのような内装レザー張りのファミリー向けSUVにプロフェッショナルなイメージはなかったからだ。また、シエラがシボレー・シルバラードよりもプロフェッショナルである理由を問われたとき、GMCは具体的な根拠を示さなかった。
それでも、広告の効果はあったようだ。2000年代に親会社のゼネラルモーターズがオールズモビル、ポンティアック、ハマー、サターンなどのブランドを次々と廃止した際にも、高い価格設定を許されるGMCの不思議なパワーによって、ブラックリストから外されたのである。
GMCの現在
GMCは2017年から「We Are Professional Grade」を「Like a Pro(プロのように)」に変更している。基本的な意味は同じで、シボレーが1990年代に使用した「Like a Rock」を踏襲している。ただし、かつてのスローガンよりも信頼性が高い。新型シエラの基本構造は、シボレー・シルバラードと同じままだが、デザインと装備でしっかり差別化しているのだ。
GMCシエラは、マルチプロと名付けられた6ウェイ・テールゲートと、カーボンファイバーを使った高耐久性のカーゴボックスという、シボレーにはない上級装備が用意されているのが特徴的だ。
こんな記事も読まれています
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!
愛車を賢く売却して、購入資金にしませんか?
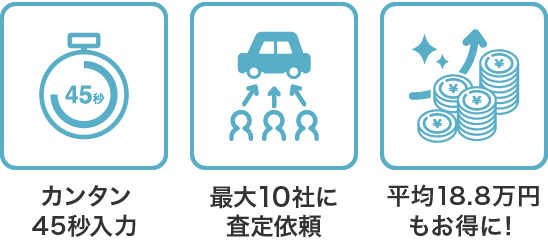
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!
愛車を賢く売却して、購入資金にしませんか?
おすすめのニュース
-
-
-
-
ベストカーWeb0
-
-
AUTOCAR JAPAN4
-
-
ベストカーWeb3
-
motorsport.com 日本版1
-
バイクのニュース1
愛車管理はマイカーページで!
登録してお得なクーポンを獲得しよう
おすすめのニュース
-
-
-
-
motorsport.com 日本版1
-
WEB CARTOP4
-
-
-
バイクのニュース62
-
-
くるまのニュース6
-
motorsport.com 日本版0
-
AUTOCAR JAPAN0
-
-
AUTOSPORT web2
-
Auto Messe Web0
-
-
Webモーターマガジン0
-
カー・アンド・ドライバー0
-
-
Auto Prove66
-
AUTOSPORT web0
-
motorsport.com 日本版2
-
-
AUTOSPORT web0
-
-
-
-
AUTOSPORT web1
-
-
Auto Messe Web1







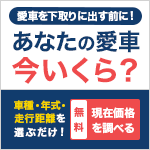
みんなのコメント