AT、CVT、DCT……2ペダル車のシフトノブ&シフトレバーは果たしてどれが正解なのか!?
最近、クルマのシフトレバーはどんどん進化してきている。一般車だけじゃなく、筆者が走っていたころのF2やF3000マシンは5速のMTだった。それが6速になり、レバーを前後に動かすだけのシーケンシャルシフトになり、今ではスーパーフォーミュラもパドルシフトだ。
ただ、クルマ(一般車)のシフトレバーはレーシングマシン以上に進化し続けており、特にAT車のシフトレバーは各社&各車さまざまな方式が登場してきている。筆者自身、試乗会などで新型車に乗るたびに、シフト操作に戸惑うことがよくあるもの。
AT、CVT、DCT……2ペダル車のシフトノブ&シフトレバーは果たしてどれが正解なのか!?
そこで、今回は数あるシフトレバーの方式のよし悪しを検証し、どれが最適解かを考えてみようと思う。題して「シフトレバー、どれにする?」
文/松田秀士、写真/トヨタ、ホンダ、マツダ、日産、メルセデス・ベンツ
■多段式ATとCVTとの違いとは?
ところで、この話を進める前に、ATのトランスミッションにはいわゆる多段式のATとギヤを持たないCVT(発進用ギヤを持つ場合がある)、さらにBEV(バッテリーEV)に至っては変速機を持たない直結タイプがあることを知っておく必要がある。主にここでは多段式ATの話をメインに進め、必要に応じてCVTやBEVの場合を付け加える。
まず、いちばん一般的なのが前後に動かすストレートタイプ。一番前からP⇔R⇔N⇔D⇔2(S)⇔L(B)と動かすたびにゲートをチョイスしたカチッと感があり、長らく慣れ親しんだセレクトレバーだ。このタイプで重要なのは、車庫入れや縦列駐車時にNを飛ばしてR⇔D間を繰り返しスムーズに移動できるか?であり、どのメーカーもかなりのレベルで使いやすくなっている。
一番オーソドックスなストレートタイプのシフトレバー。ボタンを押しながら操作すると確かにÐレンジ飛び越え、LレンジやBレンジにぶっこんでしまう恐れがないわけではない
ただし、このタイプの問題点は、D以下に(D→2→L)シフトした時に2段下げてLにシフトしてしまったり、逆に上げた時にDを飛び越してNにシフトしてしまったりするなど、ギヤをMTのようにチョイスしたいドライバーには使いづらい面もあった。
また、5速ATでありながら一般道で自動的にオーバートップの5速にシフトして力不足を感じないように、また高速道路での追い越し時に4速にシフトダウンできるようシフトレバー横に設けられたボタンで5速→4速にシフトする方式も現れた。
しかし、これは見た目も使用感もダサ過ぎたことと、ATのシフトプログラムが進化してエンジンの低速トルクもアップしたことから、今ではほとんど採用されていない。
■メルセデスが採用していたゲート式は今や小型車を中心に普及!!
ストレートタイプのこのような問題点を解消するためにメルセデスが採用したのが、ストレートタイプからギザギザを付けて、左右の移動をプラスしてシフトするゲート式だ。このタイプはD⇔L間シフト操作でのミスも起こりにくく、状況に応じてのギヤの使い分けを好むドライバーにも、また一般のドライバーにも好評だった。
ベンツが特許権を持っていたというゲート式。今は小型車を中心に普及している。ゲートの位置によりどのシフトに入っているかが確かにわかりやすい仕様である
ただし、これはメルセデスの特許があったので、特許が切れてから遅れて一般に普及し始めた。メルセデスATシフトタイプというイメージが定着していたので、なんだか高級! という幻想を多くのユーザーが抱いたものだ。ただ、メルセデスに関して言うと、このタイプは左ハンドル用なので、右ハンドルのメルセデスでは左手で同じシフトゲートを操作することになり、逆に使いにくかった。
このような使いづらさもあってか、すでにメルセデスはステアリングの右側コラムにレバーを備えたシフト方式に統一している。昔、MTのコラムシフトがタクシーや教習車、実用トラックなどに多く採用されていたが、スポーティの定番となっていたフロアシフトがフロアスペースを奪っていたこと、さらにステアリングに近い位置にシフトレバーがあることが理想的ということでコラムシフトが採用されていた。
メルセデスのコラム式シフトレバーは大変使いやすく、上下にR⇔N⇔DのみでPは横のボタンを押すだけ。個別にギヤをセレクトしたい場合は、ステアリング左右のパドルシフトで操作する。特に、この方式は車庫入れや縦列駐車時の頻繁にR⇔Dを操作する時に手の移動距離も最短で使いやすい。BEVのテスラもメルセデスとまったく同じ方式を採用している。
■シフト・バイ・ワイヤーの採用によりシフトレバーの形態も多種多様に進化
このメルセデスの方式もそうだが、近年シフトそのものがシフト・バイ・ワイヤーという物理的に繋がっていない電子制御式になったことで、シフトレバーの位置はどこにでも自由におけるようになった。マクラーレンの限定スポーツモデルでは天井にセットされているくらいなのだ。
このシフト・バイ・ワイヤー方式が一般的になったのがハイブリッドのプリウスだろう。シフトレバーは常にある位置に中立していて、軽く短いタッチでDやR、時にはNにシフトする。目的のギヤに入ったかどうかを確認するにはインジケーターのランプを見る必要がある。シフトレバーはすぐに元の位置に戻るので、手の感触で確認することはできない。
このため、例えばDにシフトしてしようとした後に携帯電話が鳴って話し込んだあとなど、Dに入っていることを忘れてしまうと厄介だ。ストレート式やゲート式では、見た目にも触った位置などでどのギヤがセレクトされているのかわかりやすいが、ハイテク感を演出するこのプリウス式のものは高齢者ほど気を付ける必要があると思う。
最近では輸入車にもこのプリウス式シフトタイプが使われるようになってきた。コンパクトでスッキリしたデザインにできるため、シフトノブに高級なクリスタルを使用するメーカーもある。
■結局シフトは極力シンプルなのが使いやすい!?
ジャガーのダイヤル式シフト。基本走行中はÐレンジに入れた後はステアリング操作に集中できる。なおエンジン停止時は格納され、インパネとツライチになる凝った仕様だ
なかでも注目なのがジャガー。エンジンを始動すると丸いダイヤルがポップアップしてきて、そのダイヤルをひねって回すことでDなどにシフトする。ダイヤルのすぐ上に「P R N D S」と表示され、どのギヤがセレクトされているかが見やすいタイプもあり、さらに指でひねる動作は神経が集中しているからか、意外とどのギヤをセレクトしたのか覚えているもので、慣れればこれはこれで扱いやすいと感じたもの。
さらに、エンジン停止状態ではシフト面がシフトテーブルとフラットになっているから、ペットや子供からの悪戯もされにくい。これはダイヤル式ゆえ走行中にも言えること。
ホンダは最近シフトにボタン式を採用している。デザイン的にはスッキリしているし、Rはちょうど指1本で短く引き上げる方式。ただ、ボタン式は相当慣れるまで目視してボタンを押してしまいがちで、やはり慣れるまで使いにくいのと、ボタンを押すのは操作回数が増えているように思えてならない。
さて、筆者のなかでの最適解はやはり昔からあるスライド式。軽自動車などレンジの少ないCVTにも多く採用され、シフトした手の感触と目視で直感的にどのギヤにセレクトされているかがわかりやすいからだ。
こんな記事も読まれています
この記事に出てきたクルマ
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!
愛車を賢く売却して、購入資金にしませんか?
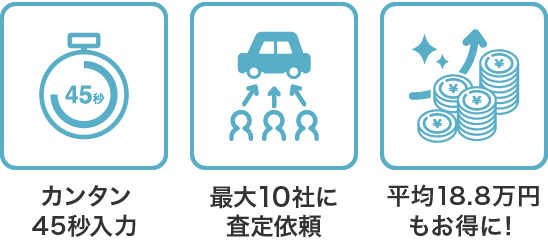
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!
愛車を賢く売却して、購入資金にしませんか?
おすすめのニュース
-
motorsport.com 日本版0
-
-
-
-
WEB CARTOP0
-
カー・アンド・ドライバー0
-
日刊自動車新聞0
-
AutoBild Japan1
-
-
レスポンス0
愛車管理はマイカーページで!
登録してお得なクーポンを獲得しよう
おすすめのニュース
-
-
WEB CARTOP7
-
WEBヤングマシン5
-
-
-
motorsport.com 日本版0
-
-
Webモーターマガジン0
-
-
-
-
-
-
webオートバイ0
-
ベストカーWeb7
-
月刊自家用車WEB1
-
-
AUTOSPORT web1
-
AUTOSPORT web5
-
ベストカーWeb0
-
-
-
-
AUTOSPORT web1
-
-
AUTOSPORT web0
-
AUTOSPORT web0
-
-
AUTOSPORT web1
-








みんなのコメント