「ザ・イタリアンジョブ」さながらに
ランボルギーニ・ミウラSVで、あの有名な映画「ザ・イタリアンジョブ」(邦題:ミニミニ大作戦)の冒頭のシーンのロケ地を探す旅に出る、という企画ほど、面白いものはない。
ランボルギーニ、「ウルス」発売を前に生産施設を1.4倍へ 音響実験施設も新設
多くの読者の方々にとっては、ジュリア・スーパーのパトカーと、ミニがカーチェイスを繰り広げる、この映画に魅了された経験を持つ人が多いと思う。
しかし、それよりももっと衝撃的だったのは、冒頭で、ランボルギーニ・ミウラがトラクターによって、崖から突き落とされるシーンだ。
そのシーンを撮影した場所に、40年ぶりに立ってみよう、というのが今回の旅の趣旨だった。
ピーター・コリンソン監督の古典的名作の40周年を記念して、フランス、イタリアを通り、帰りには映画の冒頭の場所、グラン・サン・ベルナール山岳路を経由して高速カーチェイスをする、という計画が実行に移されたのである。
1966年の3月に、ジュネーヴ・モーターショーでランボルギーニ・ミウラが登場し、自動車業界に一大センセーションを巻き起こした。
その時の会場からほぼ目と鼻の先にあるホテルの玄関ホールから外へと1歩踏み出すと、個性のない現代の車の間にあって、金色に輝くSVを直ちに発見した。
流麗で、セクシーで、曲線美あふれるそのスーパーモデルのような存在の前に、周囲のあらゆるものが色あせ、取るに足りない存在に見えてしまう。
762台生産された中の1台。今見ても、それが新車であった時と同様に魅了される。だが、究極のミウラとされ、148台しか生産されなかったSVは、その中でも、ひときわ魅力的だ。
このメタリック・ゴールドの傑作は、フランスの実業家ジャック・デンビエルモン氏が注文したものだ。氏は、SVを定期的に運転している。
イタリアで最近、全面的にリビルドされた車体番号4878は、ジュネーヴ-モン・ヴァントゥ往復による記念すべき慣らし運転から戻ってきたばかりだ。
オーナーが、クルマは走るためにあるという信念の持ち主であったため、勇敢にも、我々の巡礼の旅にSVを気前よく貸してくれた。
そのオーナーがキーを渡す時にこう警告してくれた。「市内を低速で走るとギクシャクします。サスペンションはハードです。後輪のタイヤは交換が必要です。でも、大いに楽しんで下さい」
フロントカウルの下にフルサイズのスペアタイヤを寝かせているため、ミウラは、現代の大半のスーパーカーよりもはるかに実用的であり、リヤの狭くて深いトランクにこれほど荷物が積めるのは驚きである。
SVの官能美を堪能しつつ、駐車場の狭い出口から抜け出す作業に神経をすり減らす。高めの位置にあり、かなり上を向いた3本スポークのハンドルを囲むように膝を曲げ、座面の低いシートから見回す。この1971年に製造された素晴らしいSVは、1775mmよりもはるかに車幅があるように感じる。
フランスからモンブラン・トンネルまで南に向かって爆走する。ハンドルとクラッチの位置が体から遠く、ハンドルの上部に手を届かせるため、また、クラッチを踏み込むため、腕と足をかなり伸ばさなければならない。
短めのバケットシートに少し身をかがめると、70年代風のおしゃれなブルーノ・レザーに張り替えたばかりのガラスのように光るコクピットは驚くほど広々としている。
目がくらむような真昼の日差しが反射し、計器が見えにくい。人間工学的には問題があるものの、まるで航空機のように頭上にスイッチが並ぶレイアウト、そして突き出たハンドルは、流麗な外見に見事にマッチしている。
快適とまでは言いがたいものの、背中の痛みと引き換えに、このエキサイティングな体験があるのなら本望だ。
フロントウィング越しに前方を眺めると、まるで“ラクエル・ウェルチェが寝起きに自分の豪華な足を眺めている”ような気分になる。
その曲線美、そして快楽中枢を直撃する魅惑に満ちた横置きのV12エンジン、さらにそれらを強調するトランスファーギヤの切り裂くような切ない音色が合わされば、ミウラの細かな欠点など一切気にならない。
途中で、ミウラ信者の教祖サイモン・キッドストンの粋なブラックのSVと合流する。
衝撃的な末路をたどるトンネルへ
栄光に輝く2台のSVは、ロジャー・ベッカーマン扮するマフィアの裏切り者が衝撃的な末路をたどるトンネルを探してペースを上げる。
70年代前半のカーアクション映画では、スーパーカーがブルドーザーに激突したりするのがお約束だったが、コワルスキーの乗るダッジ・チャレンジャーも、バニシング・ポイントで似たような乱暴な結末を迎えている。
映画で使われた初期のP400の正体は、長らく謎であった。映画をスロー再生すると、ブルドーザーによってラ・トゥイール・トンネルの出口から渓谷に突き落とされたシャシーは、映画とは全く関係の無い事故でクラッシュし工場に戻ってきた、エンジンのないシェルであることが確認できる。
峡谷の急流に放り込まれる前に重要なパーツを全てシェルから取り外してあった。ミニクーパーの場合と同様、魅惑的な残骸を回収できていないため、その名残がアオスタにあるバルティー川の川床に今なお眠っていることは疑いようがない。
「くまなく探したものの、ついに見つかりませんでした」。特殊効果担当のクルー・メンバーを務めたケン・モリス氏はそう回想する。
真相を言えば、アクションシーンに使われた登録ナンバーBO296を付けたオレンジ色のP400は、実は工場が納車前のクルマを提供し、営業担当役員がアルプスまで運転していったものだった。
「本を書くために調べている時に、還付を受けるために税務署に提出されたレシートを見つけたのです。撮影にかかった3日分の燃料のものでした」
「最初のオーナーは、納車された新しいミウラが実はその前に山間部を走り回っていたとは、夢にも思わなかったはずです」
1968年以降に、トンネルの両端が延長されているため、トンネルを直ちにそれと認識できなかった。だが、雪を頂いたグラン・ロチェレ山の絶景を背に谷を見下ろすと、ベッカーマンがミウラに乗って苛酷な運命に向かって山岳道路を疾走していた時の最後のローアングルからのシーンとやはり一致する。
ご想像の通り、そのシーンを再生し、2速に落としてエンジンをうならせながらトンネルを走り抜けた。フィルムのシーンとは実に対照的だが、トンネルの出口で我々を待ち受けていたのは、ツール・ド・フランスの開催に備えている町の人々だった。
おあつらえ向きに、映画に出てきたキャタピラーのブルドーザーもサイクリストたちのための整備のために存在していた。
コリンソンの映画は、イタリアでは余り人気がなかった。相も変わらずイタリアでの生活を一面的に描いたギャング映画である点を考えれば、とりたてて不思議なことではなかった。そのためでもなかろうが、我々を歓迎してくれる者は村人の中にいないように見えた。
ラ・トゥイールで折り返し渓谷に沿って道をモルジェまで下り、ガソリンスタンドで燃料を補給し、我々もエスプレッソで一息入れた。
同行したガレージのオーナー、キッドストンは、自分のミウラについてよく知っており、珍しいSV仕様については饒舌だった。だが、この映画に関する彼の蘊蓄も、やはり40年を経た古典だった。
彼のオフィスには、イージーライダーのポスターなど、ハーレーの写真が貼りめぐらされている。燃料を補給後、E25号線を東に向かう。
その後、山岳シーンが撮影された道は、ヴァッレ・グラン・サン・ベルナールの伝説的な山岳道路に向かって分岐する。2車線の高速道路が谷を縫うように下り、アオスタまで6つのトンネルを抜ける。
そこで、キッドストンは、わたしを自分の粋な黒のSVの助手席に招いた。わたしは、彼がレース用シートベルトを着用するのを見て、高速走行に備えて、心の準備をした。
SVを11年所有し、およそ2万km走ったキッドストンは、恐らく、近年、どのオーナーよりもSVを運転している人物だ。
「SVに乗れば、少なくともガレージのスペースが広がる。SVにはいつも整備士が付きっきりだからね」。クルマを発進させながら、彼はそんな冗談を言った。ありがたいことに、E25号線は交通が少なく、ジャンフランコ・イノチェンティ氏の所有していたSVは、東に向かって矢のように走る。
そのチューンされたV12は、勇壮なエンジン音を轟かせながらトンネルを次々と抜けていく。トンネルの暗闇に飛び込み、遠い出口から差し込む光をたぐり寄せるがごとく走る。荒々しい咆吼に、モナコGPのトンネル区間を思い出す。
あくまでクールにハンドルを握ろう
キッドストンの運転は、印象的なまでに滑らかで落ち着いており、次のトンネルに備え、いかしたサングラスを外す以外、右手をハンドルから離すことはない。
大型トラックに警告するためにヘッドライトを点滅させ、ミウラが閃光のように走り抜けることを知らせるためにエアホーンを定期的に鳴らす。
390psのSVは、高速では安心かつフラットに感じられ、初期のP400について批判の多かったノーズリフトの兆しさえない。
高速回転するV12の奏でる壮大な交響曲に聞き惚れ、官能的なフロントウィングに映るネオン灯が流れるように過ぎていくのに見とれている間、キッドストンは静かに運転に集中し、最後の力強い加速のためにアクセルを踏む。
すぐにアオスタの標識を一瞬で抜き去り、E25号線から外れ、アルタンヴァズ川に沿って走るE27号線を上り、峠を目指す。
アルプスのメッカであるアオスタから、サイント・オイエンに近い壮観な高架橋までの上り坂は、道幅が広く、路面が良好で、待避所も多いため、進みが速い。筆者はゴールドのSVの運転席に戻り、2台による高速走行をもう一度楽しむ。
やはり、ミウラの重量配分、レース・スタイルの配置、そして重心の低さが相まって、印象的なハンドリングだ。高速コーナーを抜ける時のSVは最高にバランスが良く、幅広のピレリが流れる気配すらない。
グリップがしっかりしており、何よりもパワーバンドの全域で均一かつ力強く、ひたすら上昇していく出力特性は、高速運転を維持するのに最適だ。
低速ではサスペンションが路面の凸凹を拾うものの、スピードを上げるにつれて乗り心地が滑らかになり、しなやかで洗練されてくる。
サイント・オイエンで旧道に入り、オリジナルの冒頭のシーンを探すためにコーナーで何度かクルマを停めた。南の方角を望むと高架橋がはっきりと視認できる。
そこで、キッドストンがUターンし、あのシーンを再現するために弾丸のように疾走する。V12はルマン・プロトタイプのような音をさせ、爆音とともにヘアピンからヘアピンへと走るが、間もなく高架橋の上に出た。
単にロケーションが正しいかどうかを確認するためだが、ノートPCを取り出してDVDを差し込む。橋のバリアが高くなり、パイロンがないものの、この場所に間違いない。
流れの速い渓流、青々と繁る牧草地、そして日陰の多い林は、スクリーンの中を走り抜けるオレンジ色のP400とともに流れるクインシー・ジョーンズ作曲の催眠的効果とぴったりだ。
狭いルートに入ると、2台のランボルギーニはウインドウを下げペースを落とす。古風な河川橋を渡り、見事な眺望を堪能するために最初のヘアピンで停車する。
この山中にある楽園まで精力的にクルマを飛ばした後、ここで車外に出て、澄んだ空気を吸い、キッドストンのノートPCで映画の冒頭のシーンを再度再生するのは最高の気分だ。
この旅行を計画している間に、全てのロケ地について地図と突き合わせて詳細に解説している素晴らしいウェブサイトに出会った。
ベッカーマンとミウラが山岳道路を高速で走る、どこか夢を見ているようなシーンを撮影したのは、英国の有名な撮影監督、ダグラス・スローカムだった。
スローカムの業績は実に印象的であり、失明するまでの間に、イーリング・コメディから『レイダース・失われたアーク』に至る数々の作品を手がけた。
スローカムには、『The Titfield Thunderbolt』に出てくる蒸気機関車であれ、『ブルー・マックス』の第一次世界大戦における劇的な空中戦であれ、アルプスを走るミウラであれ、映画に登場する機械を美しく描き出す才能があった。『ザ・イタリアンジョブ』冒頭のシーンを注意して見れば、レトロなサングラスをかけ、タバコを吸いながらハンドルを握っている男優ロッサノ・ブラッツィが、かなり慎重に運転していることがわかる。
また、ブラッツィがほとんどシフト操作をしていないことから、シーンの一部を早回ししているのが明らかだ。ルートの上の方でペースを維持するためには、本来であれば、2速から3速に素早くシフトする必要があった。
だが、ブラッツィが、この気むずかしい5段トランスミッションを実際にかまっていたら、あのクールな態度を到底維持できなかっただろう。
道は、我々が休憩した谷底から松林を通る急な上り坂になった。路面が荒れており、補修工事作業が登坂を妨げる。しかし、一時はトンネルに向かう新道の下を通っていた歴史のある旧道は、岩だらけの峰とうねうねと登るタールマックで再舗装した道につながっている。
衝動が…… ふたたびヒルクライムへ
日が暮れる時間帯で対向車が文字どおり全くないため、再度ヒルクライムに挑戦したい気持ちを抑え難い。そうして、2台のミウラは、一瞬の間にきついヘアピンカーブから飛び出し、追いつ追われつしながら坂道を上っていく。
2台のSVが連なって山間に響かせるエンジン音は魅力に溢れる。冷たい空気で冷却され、エンジンがますますスムーズに回る。クインシー・ジョーンズは、ミウラに乗ったことがないに違いない。
有名な音楽プロデューサーである彼がシートベルトを締め、ランボルギーニの工場のテストドライバーを務め、誰も追いつけないニュージーランド出身のボブ・ウォレスと一緒にボローニャ周辺を高速で走っていれば、もっと元気の出る曲が冒頭のシーンに使われていたかもしれない。
最終的には、イタリアの国境警備隊が、けたたましいサウンドを響かせて走る我々に批判的な態度を示したため、その日の運転を終えることにした。山岳道路の上の方には、部分的に凍った湖がある。
その畔に佇むホテル・アルベルゴ・イタリア。このホテルほど、我々が泊まるのに相応しい宿はあるまい。オーナーであるルカ・ブルノッド氏は、映画のクルーが到着した時にまだ10歳だった。
だが、マフィアの腹黒い親分を演じたラフ・ヴァローネにエアライフルを貸した時の事をまだ鮮明に記憶している。
「彼は俳優としては有名でも、射撃の腕はからっきしで、わたしはひどくがっかりしました」
ブルノッド氏は、そう語る。「ミニが崖から飛び出すための特別な傾斜路をスタント班が製作していたのを覚えています。ミニの残骸は全て谷底に放置されており、近年、それによる環境汚染に苦情が寄せられています」
その夜、我々一行は地元のレストランを借り切って盛大にパーティーを開き、赤ワインとおいしい食事のおかげでミウラと映画の話題が大いに弾んだ。
「学校の映画鑑賞の時間に初めて『ザ・イタリアンジョブ』を見たのは1978年でした」。キッドストンは、そう語る。
「あの頃の僕は、カウンタックが王様で、オレンジ色のP400を見ても、その不思議な魅力についてよくわかっていませんでした」
そして、『Observer’s Book of Automobiles』で手早く調べた結果、クルマの正体を知り、それ以来、ミウラが自分にとっての夢のクルマになったという。
「オークション業者のコイズ社で働き始めた時、ぼろぼろのP400が米国からやってきました」
是非とも運転してみたいと思ったのですが、そのクルマを倉庫に届けるよう指示されたのが洗車係だったため、落胆しました。
父が1996年に死んだ時、父の残してくれた財産をはたいてミウラを買いました。最初のドライブは悲惨でした。気に入っていたレストランに妻を連れて行ったのですが、着いた時には、ダッシュボードの下から煙が出ているのを妻が見つけました。
わたしが暗がりの中でAAのスタッフと問題の解決に取り組んでいる間に、妻は、夕食を一人で済ませてしまいました」。
彼は、1998年にステップアップし、特別な履歴のあるSVを買った。「最後に生産されたミウラであり、ルイジ・イノチェンティ氏が息子ジャンフランコさんの21歳の誕生日にプレゼントするために注文したクルマだと考えられています」
特注したのは、クロムメッキのグリルとバンパー、イオタ・スタイルの給油口、そしてチューニングされたエンジンだ。
イノチェンティ・ジュニア氏は、休日のサントロペとの往復を含め、外側をメタリックブラック塗装、インテリアを肌色のレザーで仕上げた自分への夢のようなプレゼントに徹底して乗った後、1974年にカウンタックと交換した
「カウンタックは、ミウラほど速く走りませんでした」。イノチェンティ氏は、そう回想する。
キッドストンは、学生の頃、この山岳道路で自分のアルファ・ロメオ・スパイダーに乗り、カーステレオの音量を上げてOn Days Like Theseを聴きながら、ツインカムエンジンでヘアピンからヘアピンへと駆けめぐった。
「ミウラに乗り、この究極のコースを走ることがわたしの昔からの夢でした。それから12年後。そして、ついに今日、ここに来られたのは奇跡です」
走る「伝説」
キッドストンは、すっかりミウラの魅力のとりこになっている。ユニークなロードスター・モデルのプロトタイプを含め、ミウラの極めて珍しいモデルの売買を仲介し、またミウラ・レジスター・ウェブサイトを立ち上げるだけでなく、彼は、60年代のスーパーカーを代表するユニークなミウラの歴史を完全解説する本を脱稿しようとしている。
彼は、夕食を摂る間に我々をからかいつつ、ミウラをめぐる俗説を正すことも含め、自分の研究の成果を披露してくれた。
「フェルッチオは、確かにセビリアで育つ有名な闘牛の名前が気に入ったものの、巷に流布しているように、ブリーダーであるドン・エドアルド・フェルナンデスの了解を求めたり、フェルナンデスにクルマを贈呈した事実はありません」
ミウラの歴代のオーナーには、ロッド・スチュワート、エルトン・ジョン、ロック歌手のジョニー・アリディ、そしてブラック・サバスのギタリスト、トニー・アイオミなどの有名人もいる。
けれども、フランク・シナトラは買っていないとキッドストンは主張する。
「工場の記録を徹底して調べたところ、それらしき名前はシナトラ博士しかなく、恐らくそれが俗説の生まれる原因になったのではないでしょうか」。野生のイノシシの革張りの話も全くの空想です」
高い標高は、朝まで安眠する助けにはならなかった。2台のミウラが筆者の泊まっている部屋の下に並んで駐車している。
その優雅な曲線が、埃と排気ガスに汚れ、少しくすんで見える。夜明けに眺めて楽しむのに、これ以上の光景はなかなかない。
その後、マルチェロ・ガンディーニがスタイリングを手がけた傑作を洗車していると、ミウラの横に立つ写真を撮るために国境警備隊の隊員と国家憲兵が戻ってきた。
慌ただしいツーリングを締めくくるため、イランの元国王がかつて所有し、現在は幸運なことにグシュタードの近くで保管されている究極のミウラ、すなわちミウラSVJを見せてもらうための計画を立てる。
豪華なスキーリゾートの北側にあるルートは、前日走ったルートと変わらないほど眺めが良いものの、サン・ベルナール山岳道路のスイス側の方が路面の状態は良い。
マルティニーに向かってE27号線を高速で北上する間、追ってきたのはオートバイだけだった。「1台のミウラで山岳地帯を走る以上に素晴らしいことはひとつしかない。それは、複数のミウラで走ることだ」
SVの後方斜め45度から眺める、センターロックを備えた幅広のカンパニョーロ・ホイールを覆うように力強く張り出したリヤウィングはいつまで見ていても決して飽きない。
代を重ねるごとにスタイリングが良くなるクルマは例外的だが、このSVがそうだ。ヘッドライトの前後にあった睫毛状のグリルがないものの、威厳があって粋な容姿は素晴らしく魅力的だ。
また、ジョルジェット・ジウジアーロがいつも主張していたように、ボディのデザインは、ホイールの側面とアーチの端を揃えた方が締まる。筆者にとって、オリジナルのP400は、特にリヤが横に張り出しすぎている。
カーチェイスを繰り広げながらスイスに入ると、特にきついコーナーから立ち上がる前にハンドルをロック位置から戻す時、ハンドルの戻りが奇妙に悪いのが明らかになる。
ただし、ノンアシストのラックのギヤ比が小さいため、ステアリングのフィーリングと重さは、速度が上がるほど改善される。重いシフト操作と同様、山間部を走ると問題が目立つものの、それでも、山道を下り、カーブが緩やかになっていくにつれて、理想にかなり近づく。
その場合も、シャシーが、加速にニュートラルに反応する。ミウラは、その技術チームが証明したいと熱烈に望んだレーシングカーとしての実績が足りないものの、少なくとも公道では、アンダーステアやオーバーステアなどを疑う余地もない。
「そんな経験をしたのは1度だけで、それも路面が濡れたコーナーでした」。これは、SVに乗り、彼らしくハイペースで2万km走ったキッドストンの言葉だ。
ブレーキだけは……
ブレーキだけは感心しない。ブレーキは反応がなく、強く踏んでもほとんど効かない。ヘアピンを次々と下った後でさえ、大型のガーリング製ブレーキディスクがフェード現象を起こす気配はないものの、それでも、信頼感が感じられない。
SVJのシャシー番号687は、伝説的なミウラの中にあってさらに伝説的だ。
「国王は、何か特別な車が欲しくて、そのための対価を支払う用意があった」1971年に標準仕様のSVを生産ラインから抜き出し、自分の開発した粋なイオタのスタイルに改造したウォレスは、そう回想する。
フロントとリヤのエアベント、そして風防カバーを備えた固定式ヘッドライト、レース仕様のフィラーキャップ、フロントオイルクーラー、チンスポイラー、そして1本式のフロントワイパーなど、あらゆる要素が、SVJの外見をさらに引き立てている。
ストレート・マフラーのせいで荷室の大きさが制限されているものの、エンジン音を猛々しい咆吼に変える。このSVJが現在スイスに保管されていることも一種の因縁だ。
というのも、国王は、メタリック・グラナダレッドのミウラにピレリのスタッドタイヤを履かせ、サンモリッツにある自分の別荘に新車で届けさせたからだ。
国王は、納車される前のSVJを入念に調べるようイランのシークレットサービスに命じたものの、テヘランに持って行くまで、アルプスでSVJを1度しか運転していないとウォレスは語る。
国王は、夜明けにニアヴァラン宮殿のガレージからSVJを出させ、武装したメルセデス6.9の軍団が追う中、荒涼とした高速道路で走らせたという。イラン空軍がメンテナンスのためにSVJを飛行機でイタリアに運んだという話も俗説に過ぎない。
1979年にイラン革命が起きた後、民衆は、国王の所有していた3000台の車と一緒にミウラを没収した。それ以降のオーナーには、映画スターのニコラス・ケイジも含まれる。
キッドストンSAが最近、イタリアのコレクターに売却したSVJは、現在、フォイターソアイのエリッヒ・ピヒラー氏が保管している。
ところで、SVJを身震いするほど速く走らせることのできる人物として、ランボルギーニから引退したばかりの同社テストドライバー、ヴァレンティーノ・バルボーニ氏以上の適任者はいないだろう。キッドストンは、彼の近刊に合わせて発売する特製DVDを撮影するためにバルボーニ氏をスイスから招いた。
彼が開発に力を注いだのはカウンタックだ。だが、当時18歳だったバルボーニ氏の心を揺さぶり、村の司祭に付いてサンターガタを訪れた際に仕事がないか問い合わせるきっかけになったクルマはミウラだった。
この顎髭を伸ばした感じの良い人物は、眩しいほど白いキャビンに乗り込み、いつもの癖で、何よりも先に自分の髪型をチェックする。
その間に、筆者がオドメーターを見ると、6000kmしか走っていない。バルボーニ氏は、完全にくつろいだ様子でミウラの中で最も高価なSVJのハンドルを握る。そして、峠の最高地点へとランボルギーニを加速させ、高速コーナーを楽々と駆け抜けて見せることで、楽しそうにお手本を示してくれる。
SVJの方がSVよりもわずかに馬力があるとしても、4本のマフラーからほとばしるその甲高い響きは、SVよりも圧倒的に速く感じる。
グシュタードへと向かう帰りの道は、クルマを取り換え、筆者が2台のSVを追う。
助手席に座るランボルギーニの専門家の中の専門家、バルボーニ氏の存在を意識し、この中毒性のある咆吼と執拗な加速の効果を満喫するため、低めのギヤで走りたい気持ちを抑え難い。
変速も、ステアリングも、ブレーキも、反応が鋭く、新車のように新鮮に感じる。山岳道路を黄昏に向かって2台のミウラを追いかけていると運転する醍醐味を感ずる。
だが、市街地のトンネルに3台で入る時こそ、最高の瞬間だ。3人のドライバー全員が減速し、2速に入れる。バルボーニ氏と筆者がお互いを一瞥し、にっこり笑ってパワーウィンドウのスイッチを同時に押す。
増幅された咆吼は信じられないほどで、出口に備えて減速するとマフラーからアフターファイヤーが勢いよく吹き出し、クライマックスを迎える。
3台のミウラが轟かせるサウンドは、まるでオペラのクライマックスのようだ。そのサウンドに浄化され、亡霊のように頭から離れなかったマット・モンローの歌声が完全に消えていた。
こんな記事も読まれています
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
おすすめのニュース
-
ベストカーWeb5
-
AUTOSPORT web0
-
AUTOSPORT web0
-
ベストカーWeb0
-
AUTOSPORT web0
-
AUTOSPORT web0
-
-
AUTOSPORT web0
-
AUTOSPORT web0
-
AUTOCAR JAPAN0
愛車管理はマイカーページで!
登録してお得なクーポンを獲得しよう
おすすめのニュース
-
AUTOSPORT web6
-
-
-
AUTOSPORT web3
-
AUTOSPORT web0
-
AUTOSPORT web0
-
AUTOSPORT web3
-
AUTOCAR JAPAN2
-
Auto Messe Web1
-
AUTOCAR JAPAN8
-
-
AUTOSPORT web0
-
AUTOCAR JAPAN22
-
Auto Messe Web0
-
AUTOCAR JAPAN1
-
AUTOCAR JAPAN1
-
乗りものニュース27
-
-
motorsport.com 日本版0
-
-
-
-
AUTOSPORT web0
-
motorsport.com 日本版0
-
乗りものニュース10
-
motorsport.com 日本版0
-
乗りものニュース24
-
-
motorsport.com 日本版0
-
Webモーターマガジン0
コメントの多い記事
-
運営ブチギレ!? 一般車が「検問突破」何があった? 国際イベントでありえない"蛮行"発生! ラリージャパン3日目の出来事とは
-
給油所で「レギュラー“なみなみ”で!」って言ったら店員にバカにされました。私が悪いんですか?怒りの投稿に回答殺到!?「なにそれ」「普通は通じない」の声も…悪いのは結局誰なのか
-
ホンダ新型「プレリュード」まもなく登場? 22年ぶり復活で噂の「MT」搭載は? 「2ドアクーペ」に反響多数!海外では“テストカー”目撃も!? 予想価格はいくら?
-
レクサス新型「小型スポーツカー」がスゴい! “テンロクターボ”×初の6速MTを搭載! 最小SUV「LBX MORIZO RR」どんなモデル?
-
不要or必要? やっちゃったらおじさん認定!? 「古い」「ダサい」といわれがちな [時代遅れ]な運転法
あなたにおすすめのサービス
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
新車見積りサービス
店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!







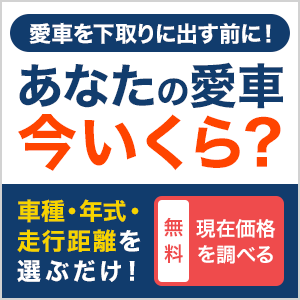
みんなのコメント
この記事にはまだコメントがありません。
この記事に対するあなたの意見や感想を投稿しませんか?