今はなきいすゞの名車5選
いすゞが、日本市場向けの乗用車生産から撤退して約19年が過ぎた。小川フミオがかつての名車を振り返る!
いま自動車好きの一部では、日本の旧車が注目されている。それも手伝ってか、いちどは乗ってみたい、と、思わせるクルマには、いすゞ車が意外と多い。1953年から2002年までしか(日本市場向けの)乗用車を作らなかったのに、旧車の世界では存在感が大きい。
ホンダ・フィットをおもいっきりSUVにしました! クロスター・カスタム登場
1960年代は湘南の自動車メーカーとしてシャレたイメージが強く、レースでの活躍が、若者を中心とした消費者の好感度を高めた。かつ、スタイリングのレベルの高さは、いまの眼で観ても、魅力を感じるほどだ。
1922年にトラックメーカーとしてスタートしたいすゞ(この社名は1949年から)。1953年に初めて手がけた乗用車は、英国で評価の高かったヒルマン「ミンクス」で、ノックダウン生産(部品まで輸入して日本で製造)だった。
1960年代に入ると「ベレル」を発表。これらのモデルは、専門家筋の評価はそれなりに高かったものの、地味といえば地味な印象で、市場での存在感は薄かった。
大きな飛躍があったのは、1963年の「ベレット」。1964年開催の第2回日本グランプリの「T-V」クラス(ツーリングカーのカテゴリー5)に10台も投入された。結果はあいにく、8台エントリーしたプリンス「スカイライン」が1位から7位までを占めることとなったものの、いすゞのイメージはここで大きく向上した。
1964年にはスポーティな「ベレットGT」を投入。おとなから小学生まで、「ベレG」としてたくさんのファンを生んだものだ。レースでも本領を発揮するのは、「117クーペ」用に開発された1.6リッターDOHCユニットを搭載した1969年の「ベレットGTR」である。いずれにせよ、一世を風靡したのは間違いない。
1974年の「ジェミニ」は、1971年に米ゼネラルモーターズとの間で結んだ資本提携の結果、独オペルなどGM傘下のメーカーとある程度設計を共用する「グローバルカー」(当時の言い方)だった。とはいえ、いすゞ開発陣の独自色がかなり入ったのも事実。とりわけ、1979年に導入されたスポーティな「ZZ」(ダブルズィー)シリーズは、いすゞ企画のパワフルな後輪駆動車として、おおいにウケた。私の周囲にも、オーナーが多かったものだ。
いっぽう、いすゞにはもうひとつのイメージがある。スタイリングと品質感に秀でたブランドというものだ。1968年に、当時イタリアのカロッツェリア・ギアにいたジョルジェット・ジュジャーロが手がけた「117クーペ」のスタイリングは大きな話題を呼んだ。
とくに初期型は微妙なボディのカーブが美しかった。じっさいにイタリアからボディ職人が来日して、初期の段階で工作の指導にあたったという。職人が手でボディを叩いているいすゞ藤沢工場は、東京を含めて当時の小学校の社会科見学での、ひとつの人気コースだった。観に行ったというひとも、いまの60代にいる。
1970年代、ジュジャーロは「アッソ」(トランプのエースの意)シリーズを手がけていた。新世代のクーペやハッチバックのスタイリングコンセプト提案である。そのうちの1台として、1979年に発表されたクーペ「アッソ・ディ・フィオーリ」(クラブのエース)を量産車に移し替えたのが、1981年の「ピアッツァ」。まさか同じには作れないだろうという予想をいい方向にくつがえした、みごとなクオリティのデザインだった。
ここまでがいすゞのいわば全盛期。こののち1980年代に入ると、いすゞは、GMグローバルカー戦略から生まれた1983年の「アスカ」や、1985年に満を持して発表された2代目「ジェミニ」などをリリース。いずれも話題にはなったものの、急激に失速していくのだった。
理由としてあげられたのは開発費の不足。自社開発の乗用車を思うように作れない。それはおそらく、そのための資金を調達せず、商用車のほうにあえて軸足を戻した経営陣の残念な判断のせいなのだ。昨今、欧州ではブランド復活ブームが続いてきた。ファッションのみならず、クルマの世界でも「イスパノスイサ」や「ペガソ」が電気で走るスポーツモデルとして、計画されている。
いすゞも、ここいらで次世代に向けて、トンガった乗用車を作ってくれないだろうか。”湘南のメーカー”の復活を、往年のファンとしては願うのである。
(1)117クーペ
いすゞの名を日本の自動車史に永遠に残すことになるはずの立役者が、1968年発表の「117クーペ」だ。低くかまえたノーズや流れるようなサイドのキャラクターライン、それに流麗な輪郭のルーフラインなど、デトマソ「マングスタ」(1967年)をはじめ、1960年代のジュジャーロが得意としてきた官能的ともいえるデザインを、まとめたものといってもよいだろう。
デザインが高度で、それゆえ、当時の日本の量産技術では、大量生産が出来なかった。1973年までは、いすゞの工場で職人の手作業による仕上げが多く、それが逆に、このクルマの希少性につながり、さらに人気に拍車をかけた。それ以降はボディパネルをはじめ、量産化前提のマイナーチェンジがほどこされたのだ。
全長は4320mmと比較的抑えめであったものの、ホイールベースは2500mmと長め。そのため、観た眼の印象と裏腹に、後席にもおとな2人が楽に座っていられた。室内の仕上げもよく、いすゞの意気込みが感じられたものだ。
いっぽう、ステアリング・ホイールは重く、1960年代にはパワフルともいえた1.6リッターDOHCエンジンも、回転マナーがいまいちもっさりしていて、1970年代なかばをすぎると、時代遅れの感が出てきた。いすゞでは最終的に2.0リッターエンジンを用意したものの、外観からくるエレガントなイメージに沿った性能を追求するためにはより大きな排気量が欲しかった。
1981年まで製造されたから、かなり長命なモデルだ。それでもいまでも欲しいのは、1977年以前の丸型ヘッドランプのモデル。できれば(繰り返しになるけれど)1973年以前の”手叩き”ボディのモデルである。観ていて飽きないスタイルだ。
(2)ジェミニ(初代)
シンプルでいいクルマ。後輪駆動のまっとうなセダンで、主眼は機能性と、それに走る楽しさ。1974年に発売され、1985年まで作り続けられた初代「ジェミニ」は、当時の日本のセダンのなかでも白眉ではないかと思う。
企画は、“Tカー”という、米国ゼネラルモーターズが、世界各地の子会社を参画させてコンセプトメーキングしたグローバルカー構想から生まれたもの。ほぼ同時に発表されたモデルとして独オペルの「カデット」や、英ボクゾールの「アスコナ」がある。
欧州的だったのは、前後タイヤとボディのレイアウトをはじめとする、いわゆるプロポーションよさがひとつ。もうひとつは、セダンには、通常のノッチバック4ドアと、ファストバックスタイルの2ドアが用意されていたこと。この2車種はだいぶ観た眼の印象が異なり、とくにファストバックは軽快な印象で、好感がもてた。
ジェミニのよさは、1980年代のモデル後期になっても、高いアピール力をそなえていたこと。時宜を得るように、マニュアル変速機を4速から5速へとグレードアップして、内外装のアップデートもおこなった。それにもうひとつ大きいのは1979年の「ZZ」シリーズ投入だ。
1.8リッターDOHCエンジンに、スポーティな足まわりを組み合わせた「ダブルズィー」シリーズは、ダイレクトな操縦感覚が魅力的なモデルだった。とりわけ有終の美を飾るように設定された「ZZ/R」は、当時の自動車好きにおおいに評価された。いまもういちど乗ってみたいモデルである。
(3)ピアッツア
1981年に発売されたスペシャルティクーペ「ピアッツア」。フラッシュサーフェス化(表面の凹凸を極力なくすデザイン手法)が徹底された卵型シェイプは、量産化に踏み切ったことを英断と称えたいほどだ。
デザインを手がけたジョルジェット・ジュジャーロのイタルデザインとは、117クーペ時代からのつきあいだ。117クーペが、1960年代のジュジャーロデザインの総決算だとすると、ピアッツアは空力シェイプというきたるべき時代を先取りするようなデザインテーマである。
あえてヘッドランプは、半固定式にして、当時多かった完全格納式ヘッドランプを持つフロントマスクのように、没個性的になるのを避けるなど、細かい目配りのあることが観てとれる。
内装も、アッソ・ディ・フィオーリとよばれたショーカーで試みていたレバーを極力廃するサテライト型のコントローラーを備えているのが大胆だった。願わくは、合成樹脂製品の質感が揃っていると、デザイナーの意図が十全に活かされただろう。
ジュジャーロ監修の自身の作品集をひもとくと、117クーペについてはほとんど触れられていない。いっぽう、ピアッツァは大きな写真とともに紹介している。本人にとっても意欲作だったのだろう。おなじ1981年にジュジャーロはデロリアン「DMC12」を手がけている。ウェッジシェイプのデロリアンとは対照的で、おそらく本人が気に入っていたのはピアッツアのほうだろう。
いまでも路上で見かけることがある。まったく古びて見えないのは、本当に基本デザインの完成度が高いからだ。1991年まで生産されたのでこれも、いすゞ車の例にもれず、息の長いクルマになった。最後は「ネロ・イルムシャー」とか「ハンドリング・バイ・ロータス」など、ちょっとこじつけめいたスポーツ仕様が出てきたが、いまでは、それも興味がある。
(4)ベレット
1963年に発表された「ベレット」は、いすゞ独自の開発の乗用車としては2台めであり、初のヒットだ。そして1964年に追加された「ベレット1600GT」で若者マーケットをつかんだ。いまもたまに街で見かけると、キャラクターがたっていて、なかなかよいかんじ。
ベレットは「オーバルシェイプ」と謳われた、大きな弧を描くような山形のベルトラインを特徴としていた。ほぼ同じデザインコンセプトで、4ドアと2ドアを作りわけていた。2ドアがパーソナル性を求めるユーザー向けだったのは、いまのマーケティングにおける、セダンと4ドアクーペの関係に近い。
ベレットGT、通称ベレGは、当時、ほぼ例外なくクルマ好きだった若者市場へのアピールをはかったモデル。当初はノーマルモデルとおなじ丸型4灯のフロントマスクで登場し、すぐに内側の2灯をフォグランプとしたフェイスリストが行われた。
全長は3990mm、ホイールベースも2350mmと、いまの眼からみるとコンパクトなモデルだ。でも1969年に登場した、「ベレGアール」(ベレットGTR)は、小さいけれど存在感が大きい。
さきに触れたとおり、117クーペ用に開発された1.6リッターDOHCエンジンを搭載した後輪駆動で、120馬力の出力は車重970kgのこのクルマには充分パワフルだった。
当初は「GTX」の名称でレースに出走し、のちに「GTR」として市販された。コーナリング性能の高さを誇ったモデルである。
ブラックアウトしたフロントボンネット(オプション)や、4灯に加えバンパーレベルに補助灯を設けたフロントマスクなど、実際のスタイル以上に、開発者の思い入れが伝わってくるからだろう。
ベレットは10年作りつづけられ、1973年に製造中止。1974年には、ぐっと国際的な雰囲気のスタイリングを持つ「ジェミニ」が発売されて、後を継ぐことになる。日本で、いわゆる排ガス規制が実施されるようになった時期と重なり、2台はまったく異なるキャラクターとなってしまった。
(5)ビークロス
日本で作られたなかでもっともスタイリッシュなSUV、と評価する人もいるのが、1997年に発売された「ビークロス」。大胆なスタイリングは、いまも新鮮だ。全長は4130mmしかないのに対して、全幅が1790mmあり、全高は1710mmと高い。
なによりビークロスが個性的なのは、2ドアの2プラス2というコンセプトにある。かつ、フロントバンパーからサイドをまわってリアバンパーにいたるまで、未塗装のような合成樹脂(ポリプロピレン)をあえて使っており、ボディに留めるボルトがむき出しに。当時の言葉でいうと、スチームパンク的なスタイルだ。
塗装してある部分のほうが少ないようなカラースキームや、リアに背負ったスペアタイヤのケースまでボディと同様に2トーンで塗装してしまうなど、手法は大胆。スペアタイヤのせいでリアの視界がさえぎられてしまったので、カメラを使うというのも、ずいぶん時代に先んじていた。
エンジンは3165ccV型6気筒ガソリン。電子制御トルクスプリット4WDは、高速など低負荷の状況では100%の後輪駆動。走行状況や路面状況に応じて、最大50対50のトルクを配分するオンデマンド方式が選べるし、室内からの操作で、あえて後輪駆動を固定することも可能。
サスペンションシステムは、ラリーからのフィードバックを活かしたという。いっぽう、ダンパーは、アルミニウム製モノチューブタイプでありながら、別体タンクを備えてオイル量を増加。乗り心地を追求している。
デザインへの凝りかたはすさまじく、さきに触れた造型に加え、車体色の多さも特筆ものだ。標準色は5色であり、さらにオプションで20色が選べた。
いすゞの販売店が多くて、かつ宣伝にお金が使えて、かつ会社に体力があれば、このユニークなコンセプトは長続きしたかもしれない。じっさいには1999年に生産停止。もったいないという気はした。
デザインのいすゞを象徴するようなクルマで、最後の打ち上げ花火といえるかもしれない。いすゞは2000年代に入ると乗用車の生産を止めてしまった。もういちど復活して、ビークロスのような斬新なクルマを作ってもらいたいと思う。
文・小川フミオ
こんな記事も読まれています
この記事に出てきたクルマ
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
おすすめのニュース
-
AUTOCAR JAPAN0
-
ベストカーWeb0
-
-
WEB CARTOP0
-
日刊自動車新聞0
-
AUTOCAR JAPAN0
-
motorsport.com 日本版0
-
-
AUTOCAR JAPAN0
-
愛車管理はマイカーページで!
登録してお得なクーポンを獲得しよう
おすすめのニュース
-
-
AUTOCAR JAPAN3
-
Auto Messe Web4
-
-
-
-
日刊自動車新聞3
-
バイクのニュース1
-
-
レスポンス2
-
日刊自動車新聞0
-
-
motorsport.com 日本版0
-
-
motorsport.com 日本版12
-
-
バイクのニュース0
-
-
-
カー・アンド・ドライバー0
-
日刊自動車新聞0
-
AutoBild Japan0
-
-
Webモーターマガジン2
-
-
-
-
-
-
Auto Prove0
業界ニュースアクセスランキング
-
「子供が熱を出したので障害者用スペースに停めたら、老夫婦に怒鳴られました。私が100%悪いですか?」質問に回答殺到!?「当たり前」「子供がいたら許されるの?」の声も…実際どちらが悪いのか
-
“650馬力”の爆速「コンパクトカー」がスゴイ! 全長4.2mボディに「W12ツインターボ」搭載! ド派手“ワイドボディ”がカッコいい史上最強の「ゴルフ」とは?
-
トヨタ新型「ミニアルファード」登場は? 「手頃なアルファードが欲しい」期待する声も!? 過去に"1代で"姿消した「ミドル高級ミニバン」があった!? 今後、復活はあるのか
-
セカオワが「愛車売ります!」CDジャケットにも使用した印象的なクルマ
-
8年ぶり全面刷新! 日産新型「小さな高級車」登場! 全長4.3mに「クラス超え上質内装」とめちゃ“スゴいシート”採用! ちょうどイイサイズの「新型キックス」日本には来る?
コメントの多い記事
-
「中古車を買いに来たら『支払総額表示』で売ってくれませんでした、詐欺ですよね?」 「別途費用が必要」と言われることも…! 苦情絶えないトラブル、どんな内容?
-
トヨタ新型「ミニアルファード」登場は? 「手頃なアルファードが欲しい」期待する声も!? 過去に"1代で"姿消した「ミドル高級ミニバン」があった!? 今後、復活はあるのか
-
レクサス新型「“和製”スーパーカー」に反響多数! V8×超美麗ボディに「いつ登場する!?」「憧れる」の声も! 噂の「LF“R”!?」に期待高まる
-
「子供が熱を出したので障害者用スペースに停めたら、老夫婦に怒鳴られました。私が100%悪いですか?」質問に回答殺到!?「当たり前」「子供がいたら許されるの?」の声も…実際どちらが悪いのか
-
もう待ちきれない! [新型GT-R]はなんと全個体電池+次世代モーターで1360馬力! 世界が驚く史上最強のBEVスポーツカーへ
あなたにおすすめのサービス
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
新車見積りサービス
店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!







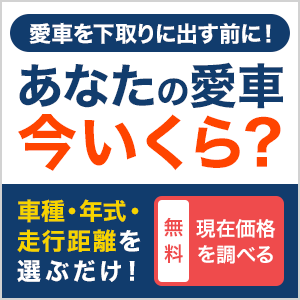
みんなのコメント
ミツオカさんお願い。