思わず言葉を失った意外過ぎるクルマ 40選 前編 どうしてこんなコトを…
思わず言葉を失った「意外」なクルマ&事件
どんな企業であろうと、リスクはできるだけ避けたいと思うものだ。それはほとんどの自動車メーカーも同じである。しかし、そんな彼らも非常に奇妙なクルマを生産したり、大胆すぎるコンセプトを発明したり、戦略的なミスを犯したりすることがある。
【画像】こんなデザインはもう二度と見られない?【ボルボ、ランチア、アストン マーティンの名車を写真で見る】 全31枚
良識的なメーカーがこのような「冒険」をするのは大変面白いものだが、場合によっては取り返しの付かない損失を被ることもある。今回は、傑作から駄作、大事件まで有名な例を年代順に並べてみた。
ロールス・ロイス・トゥエンティ(1922年)
1922年の終わり頃、英国で発刊されていたAUTOCAR誌の読者からのお便りコーナーは、新型ロールス・ロイス20HPについての賛成・反対意見で大いに賑わった。プッシュロッド式のエンジンバルブ、4速ではなく3速のギア、ブレーキは後輪のみという、残念な特徴を持つクルマとして批判を集め、ロールス・ロイスは正気を失ったのではないかと言われる始末。
一方、好意的に捉える読者は、このどれにも問題はなく、20HPをとても気に入っていると答えた。結局のところ、ロールス・ロイスは間違っていなかった。20HPは7年間にわたりよく売れ、1930年代後半まで同様のエントリーモデルが作られた。
シボレー・カッパークールド(1923年)
このクルマのエンジンは空冷式だが、冷却フィンが銅(カッパー)製だったことからこのような愛称がついた。1923年1月のニューヨーク自動車ショーで発表されたとき、ゼネラルモーターズは10月までに月5万台は売れると期待し、水冷エンジンが時代遅れになるのはいつになるだろうと考えていた。
実際のところ、シボレーは見事に外した。カッパークールドは製造が非常に難しく、信頼性も著しく低かった。工場から出荷されたのはわずか759台で、そのうち239台はすぐにスクラップになった。
ブガッティ・ロワイヤル(1927年)
すでにレーシングカーやグランドツアラーで名を馳せていたブガッティは、タイプ41(現在ではロワイヤルとして知られる)で高級車市場に乗り出した。市販車としては最大級の12.8Lエンジンを搭載し、車体の長さと価格の両面で贅を尽くした。
しかし、世界恐慌に陥っていた当時、王侯貴族にとっても高すぎることが判明し、わずか半ダースしか生産されなかった。ロワイヤルの12.8Lエンジンは、フランスの列車に搭載され、一般市民を大量に運ぶという本来とはかけ離れた目的に使われた。
クライスラー・エアフロー(1934年)
クライスラーは1920年代に従来型の自動車を作り始めたが、その後の10年間で世間からの評判をひっくり返した。エアフローのユニボディ構造は、1934年当時としては非常に珍しく、さらに流線型のフォルムは賛否が激しく分かれるところとなった。
大胆で冒険的なスタイリングが大きな要因だが、それがトーンダウンした後も、完全に受け入れられることはなかった。クライスラーは自動車エアロダイナミクスのパイオニアであったが、その先進性に時代が追いつかなかった。エアフローの後の市販車では、はるかに慎重なデザインを採用している。
シトロエン・トラクシオン・アバン(1934年)
トラクシオン・アバンは前項のクライスラー・エアフローのような流線型ではなかったが、ユニボディ構造を採用し、前輪駆動、油圧ブレーキ、独立フロントサスペンションなど斬新な機構を備えている。シトロエン史上最もワイルドな1台であり、1957年まで生産された。
にもかかわらず、シトロエンの冒険は少なくとも短期的には報われなかった。トラクシオン・アバンの開発費と新工場の建設費があまりにも高額だったため、シトロエンは経営破綻し、1935年に大手タイヤメーカーであるミシュランに救済される羽目になった。
エドセル(1958年)
フォードは19年間で1500万台のモデルT(T型フォード)を生産して世界の自動車業界を一変させ、それ以来世界有数の自動車メーカーであり続けている。しかし、常に成功続きというわけではない。
最も顕著な失敗例は、良かれと思って立ち上げたエドセルという新ブランドである。失敗の理由としては、非効果的なマーケティング、低品質、物議を醸すデザイン、消費者の嗜好の変化、不況などが指摘されている。エドセルは、坑道に投げ込まれたグランドピアノのように悲惨な結末をたどった。フォード史上最悪のアイデアかもしれない。
シボレー・コルベア(1960年)
空冷エンジンの苦い経験から40年近くを経た頃、シボレーはコルベアという新型車を開発し、再び痛い目に遭うことになる。ここで問題になったのはエンジンそのものではなく、エンジンをリアに搭載したことであった。コルベアのリアサスペンションは、やや安定性に欠けるスイングアクスル方式を採用しており、そこに重いエンジンを載せてしまったのだ。
そのため、一部の辛辣な評論家・活動家から攻撃の対象とされ、不安定な米国車の申し子になってしまった。シボレーはサスペンションを大幅に改良した新バージョンを導入したが、コルベアの評判が回復することはなかった。
フォード・コンサル・クラシック(1961年)
欧州のメーカーはしばしば米国からスタイリングのヒントを得たが、その成功の度合いはまちまちだった。英国フォードは1961年にコンサル・クラシックを投入したが、当時としては信じられないほど斬新に見えた。それは主に、逆傾斜のリアウィンドウによるものだった。
同じ特徴は2年前に小型のアングリアにも採用されていたが、リアウィンドウ以外はかなり普遍的なデザインだったこともあり、さほど問題にはならず大ヒットを飛ばした。ただ、奇抜さを増したコンサル・クラシックは大失敗を喫し、3年も経たないうちに面白みの少ないコルセアに取って代わられた。
ボルボ1800(1961年)
1950年代後半にごく少数生産されたファイバーグラス製ボディのP1900を除けば、ボルボにはスポーツクーペを作るような気配はまるでなかった。しかも、十数年にわたって生産することになるとは、誰が想像できただろう?
1800のデビューは多くの人を驚かせた。生産後期には派生型のワゴンボディも追加されている。その後のボルボにも良いクルマはたくさんあるが、1800の繊細なエレガンスにかなうものはなかった。
ビュイック・リヴィエラ(1963年)
1940年代以降、ビュイックはフィン、ベンチポート(フロントフェンダーの丸い通気口)、スイープスピア(ボディサイドのトリム)を使い、他社との差別化を図ろうとしてきた。しかし、初代リヴィエラではデザイン責任者ビル・ミッチェル氏(1912-1988)がそれらをすべて捨て去り、シンプルさと視覚的インパクトを併せ持つ、ライバルのデザイナーも賞賛するスタイルを生み出した。
71年型リヴィエラはさらにドラマチックになったが、初期型ほどの衝撃はなかった。初期型は、メカニカル的には普通かもしれないが、スタイル的には画期的なものだった。
ヒルマン・インプ(1963年)
シンガー・シャモアやサンビーム・スティレットなど、さまざまな名で販売されたインプだが、絶大な人気を誇るミニを相手にすることはできなかった。インプの最大の特徴は、コベントリー・クライマックス社が設計した全合金製オーバーヘッドカムエンジンで、トランスアクスルのすぐ後ろの車体後部に、右側に傾けて搭載された。
ヒルマンの非常にオーソドックスなイメージから考えると、ロールス・ロイスが商用バンを出すくらいの驚きだった。これまで一度もこのようなものを発表したことがなかったし、これからもすることはないだろう。インプがまだ生産されていた頃、ヒルマンは新生クライスラー・ヨーロッパの一員となったが、すぐに崩壊し、1970年代後半にはプジョーに救済されることになった。
キャデラック・エルドラド(1970年)
当時の状況からすると、70年型エルドラドの登場は予想の範囲内だが、半世紀を経た今となっては極めて異例だろう。この年、キャデラックは8.2L以上のV8エンジンを搭載し、あろうことか前輪駆動方式を採用した。
当時の米国では大型FF車は決して珍しいものではなく、1966年のオールズモビル・トロネードのように大排気量V8の搭載例もあるが、エルドラドは最も極端なケースだった。燃費と排気ガスへの関心が高まるにつれ、米国車のエンジンはどんどん小排気量化されていき、キャデラックも他社も再びこのような高みに達することはなくなった。
ランチア・ストラトス(1973年)
最大1.6LのV4エンジンで前輪を駆動するランチア・フルビア・クーペは、当時最高峰のラリーカーの1つであったが、1970年代半ばに近づくにつれ、新しいものが求められるようになった。ランチアはそれに応えるべく、先代とはまったく異なるモデルを開発した。
可愛らしいフルビアは、フェラーリ製2.4L V6エンジンをリアに搭載した、近未来的なストラトスへと姿を変えた。まるでランチアが一足飛びに2世代も進化したかのようだった。でも強さは変わらなかった。ストラトスは3年間にわたって世界ラリー選手権を席巻し、社内政治によってフィアット131アバルトに取って代わられなければ、その快進撃は続いていたかもしれない。
アストン マーティン・ラゴンダ(1976年)
第二次世界大戦後、アストン マーティンのボディは印象的な曲線美を持つようになった。もし今、鋭角的なボディを持つ新型車が発表されたら人々は驚くだろうが、残念ながら実現はしない。
しかし、かつては可能だった。デザイナーのウィリアム・タウンズ氏(1936-1993)は、フラットなパネルを隣り合わせに配置するのが好きで、ラゴンダでそうしない理由はないと考えた。その効果はあまりに衝撃的で、以来このようなモデルは出てきていないが、ラゴンダの生産は1990年まで続けられた。
ベントレー・ミュルザンヌ・ターボ(1982年)
ベントレーは1920年代に一部のモデルにスーパーチャージャーを搭載していたが、その後は半世紀近く自然吸気にこだわり続け、再び過給器を搭載したのは1982年、ミュルザンヌの6.75L V8エンジンであった。
この動きはロールス・ロイスよりもスポーティ性を強調するものとして注目を集めた。当時、両ブランドはひとつ屋根の下で同じ釜の飯を食う関係にあり、エンブレムや一部のデザインディテールを除けば、互いに見分けがつかないようなクルマを長年にわたって生産していたのだ。
ホンダNSX(1990年)
ホンダ初の普通乗用車であるS500(1963年)はスポーティな2シーターで、その後も大小さまざまな四輪車を世に送り出してきたが、中でもNSXは並外れた存在であった。
ゴードン・マレーはマクラーレンF1の設計に携わっていたときにNSXに乗り、その瞬間、「フェラーリ、ポルシェ、ランボルギーニなど、わたしが参考にしていたベンチマークとなるクルマがすべて頭から消え去った」と後に書いている。
ヴォグゾール・ロータス・カールトン(1990年)
オペル・ロータス・オメガとしても知られるこのクルマは、ドイツのオペル工場から英国のロータス本社に運ばれた3000GSI 24vをベースに開発された。ロータスが行ったのは、エンジン排気量を3.0Lから3.6Lに引き上げ、ツインターボチャージャーを装着し、サスペンションとブレーキを改良することだった。
当時の最高オクタン価の燃料で382psを発生し、足回りもそのパワーに容易に対応できた。英国では公道からの追放を求める声が上がるほど物議を醸したが、このような要求はヴォグゾールにとっては後にも先にもこれっきりである。
プリムス・プロウラー(1997年)
クライスラー傘下のプリムスのブランド末期には、人々を興奮させるようなものはほとんどなかった。唯一の例外は、古風なホットロッドのようなスタイルを持つプロウラーで、ミーアキャットの檻にいるキリンのように、プリムスの中では際立っていた。
さまざまな議論を呼んだが、V6エンジンとオートマチック・トランスミッションについて文句を言いたい人が多かったようだ。派生モデルとしてV8も計画されたが、量産化されることはなかった。
ロールス・ロイス・シルバーセラフ(1998年)
シルバーセラフはロールス・ロイスの通常の6.75L V8ではなく、BMWの5.4L V12エンジンを採用した。BMWがロールスを買収するはるか以前から、両社の間にはすでに協定が結ばれていたからだ。しかし残念ながら、V12エンジンはこのクルマには合わなかった。
V8よりもパワフルだったが、その性能を最大限に引き出すには、ロールスらしからぬ5000rpmまで回転させなければならない。その半分以下の回転数では、V8の方が圧倒的に力強かった。パフォーマンスに力を入れることは7シリーズでは許容されたかもしれないが、ロールス・ロイスのドライバーが慣れ親しむものではない。エンジンの共有は、ビジネス的には「良いこと」なのだろうが、必ずしも正解には至らない。
こんな記事も読まれています
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
おすすめのニュース
-
AUTOCAR JAPAN0
-
motorsport.com 日本版0
-
-
AUTOCAR JAPAN0
-
-
-
AUTOCAR JAPAN3
-
Auto Messe Web3
-
-
愛車管理はマイカーページで!
登録してお得なクーポンを獲得しよう
おすすめのニュース
-
-
日刊自動車新聞3
-
バイクのニュース1
-
-
レスポンス2
-
日刊自動車新聞0
-
-
motorsport.com 日本版0
-
-
motorsport.com 日本版11
-
-
-
バイクのニュース0
-
-
カー・アンド・ドライバー0
-
日刊自動車新聞0
-
AutoBild Japan0
-
Webモーターマガジン2
-
-
-
-
-
-
Auto Prove0
-
Webモーターマガジン0
-
カー・アンド・ドライバー2
-
-
GQ JAPAN0
-
-
カー・アンド・ドライバー2
コメントの多い記事
-
「中古車を買いに来たら『支払総額表示』で売ってくれませんでした、詐欺ですよね?」 「別途費用が必要」と言われることも…! 苦情絶えないトラブル、どんな内容?
-
トヨタ新型「ミニアルファード」登場は? 「手頃なアルファードが欲しい」期待する声も!? 過去に"1代で"姿消した「ミドル高級ミニバン」があった!? 今後、復活はあるのか
-
「子供が熱を出したので障害者用スペースに停めたら、老夫婦に怒鳴られました。私が100%悪いですか?」質問に回答殺到!?「当たり前」「子供がいたら許されるの?」の声も…実際どちらが悪いのか
-
もう待ちきれない! [新型GT-R]はなんと全個体電池+次世代モーターで1360馬力! 世界が驚く史上最強のBEVスポーツカーへ
-
「財布を忘れて帰ろうとしたら、免許不携帯で捕まりました。今取りに帰るんですよ。私が悪いんですか?」質問に回答殺到!?「事実でしょ」「非常識」の声も…「うっかり」でも許されない理由とは
あなたにおすすめのサービス
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
新車見積りサービス
店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!







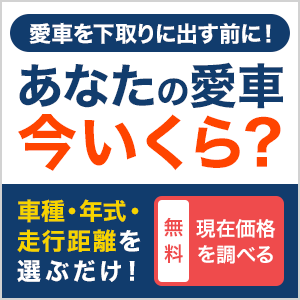
みんなのコメント
記事と写真を行ったり来たりで頭に入ってこない