「写真で見る昭和の風景」経済成長とともに国産バイクも高性能化【1950年代半ば~1960年代】
モータリゼーションの発展と、国内2輪メーカー淘汰の時代
零細規模のものから中小メーカーまでが乱立した、1950年代の国内2輪車産業。その中から、営業力や技術的なセンスを活かして成長するメーカーと、傾き始めて廃業するメーカーとの差が明確になっていくのが1950年代後半から1960年代にかけてのことだった。ここでは、そうした時代の背景を映す写真とともに、経済成長期に入った日本のモーターサイクルの歩みをを追ってみたい。
【画像17点】スズキ・コレダ、ホンダ・ドリーム……1950年代後半~1960年代の日本を走っていたバイクを写真で解説
*当記事は別冊モーターサイクリスト2010年11月号掲載の「国産モーターサイクルの歩み」を元に再構成したものです。
<混雑する丸ノ内界隈/1950年代後半>
皇居の外堀通りと平行する東京都千代田区丸の内側の本郷通り。1950年代後半のモータリゼーション時代に入ると都心の交通渋滞が常態化し、ドライバーからは路面を共用する都電への非難が上がり始めた。その結果、美濃部亮吉東京都知事(当時)は1967年から都電を逐次廃止していく。そして現在、専用軌道の多い荒川線(早稲田~三ノ輪橋)だけが残っている。
自動車の登録ナンバーはまだヒト桁で、5が小型乗用自動車。この数年前までのタクシーはVWやヒルマン、ルノーなどの輸入車が多かったが、徐々にクラウンなどの国産車が登場し始める。
<125ccで築地に通うダンナ/1957年>
東京都北区滝野川から毎日、中央区築地市場までの往復24kmを仕入れに通う魚屋の主人がまたがるのは、2年ほど前同業者に勧められて買った1955年型で2サイクル125ccのコレダST1(スズキ)。「数十kgもの鮮魚を積んで帰ると自転車で片道1時間だが、コレだと20分ほどで戻れるので体が楽だ」と、走行1万7725kmの愛車にベタホレ。維持費はガソリンとオイル代が主で月1500円前後という。1954年から許可制になった125cc(当時)は、中小商工業者に大きく支持され活用された。
<高性能と個性の「コレダ」/1956年>
写真のスズキ・コレダTT250は、日本初の2サイクルツインで18psの高性能を誇った。デザインの担当は当時静岡大学教授だった豊沢 昇。スズキからは「車両価格は少々高くなっても構わないから、ひと目でコレダと分かるデザインを」との注文を受けたという。その結果、バイクの顔を意識した特徴的な巨大ヘッドライトや流線型のウインカーボディ、フィン形状のテールデザインなどが盛り込まれ、2輪のキャデラックと評される個性的なスタイルとなった。当時価格の23万5000円は、単気筒OHCのホンダ・ドリーム250MEより4万3000円も高かった。
<滑る敷石路面を下るライダー/1950年代後半>
敷石と都電のレールで滑りやすい路面(ベルジャンロード)の、東京・文京区の切り通しを下るホンダ・ドリームC70。濡れたレール上を横切るには細心の注意が必要だった。この区間は明治時代に湯島天神と根生院の間を市電(上野広小路~本郷3丁目間)が通るために掘削された坂で、両側には当時の土留めの石垣が一部残っている。この線路には系統No16=大塚駅前~錦糸町間と、No39=早稲田~厩橋(うまやばし)間という2系統の都電が走っていた。
<多摩川大橋上を行くスーパーカブとミゼット/1950年代後半>
第二京浜(国道1号)多摩川大橋上。スーパーカブの横と後ろは1960(昭和35)年型のダイハツミゼットMP3。2ストローク強制空冷単気筒エンジンは305ccで12馬力を発揮。リヤは油圧ブレーキだったが、フロントブレーキはなく、事故で鼻を潰したMP3は当時珍しくなかった。
バイクは戦後、簡便2輪トラックとしてスタートしたが、1950年代後半になると積載量の多い軽三輪車がその役を担い。125cc以上のバイクはスポーツ車のカテゴリーに特化していった。
<ホンダC70で箱根へデート!?/1950年代後半>
ホンダ初のツイン、ドリームC70(250cc/1957年)で、国道1号線を箱根に向かうアベック。神社仏閣式の角張った形状は、薄型鋼板の強度を上げる必要から生まれたデザイン。流麗な形状のサイドバックは流行品のひとつ。自動車が一般人に買えるようになるまで、バイクは夢を乗せて遠乗りに使われた。
1955年の国内自動車保有台数は157万1740台で約半分がトラック。乗用車の大部分は外車だった。また1950年代には、そうしたアメリカ軍等からの払い下げの外車を利用した時間貸し自動車業として、会員制の「ドライブクラブ」(レンタカー事業の前身)が流行ったが、事故やトラブルの多さなどが問題化した。
性能進化とともに、2輪車は実用から趣味の世界にまで拡大
<浅間のレースで上位を占めたスーパーカブ/1959年>
1959(昭和34)年、浅間高原自動車テストコースで開催の第2回全日本モーターサイクルクラブマンレース50ccクラスで快走するスーパーカブC100。#302飯島義二(21)3位と、#322の奧津靭彦(23)4位。この年から同レースに50ccクラスが新設され、上位4台までスーパーカブが独占。5位はヤマグチ・オートペットの西久保 功(21)、6位もオートペットの岩谷隆治(21)、7位にNSUクイックリー(独)に乗る小美濃隆昌(21)が入った。
<浅間レースの大排気量クラスは外国車優勢/1959年>
第2回全日本モーターサイクルクラブマンレース(第3回浅間火山レース併催)の500ccクラスで、砂塵を巻き上げて走る#656石井義男(25)と後方の藤井一(24)はともに東京サイクロンクラブから参戦。クラブ事務所は墨田区石原にあったヒグチモータースで、BSA、BMWの販売店だった関係から、両者のマシンはBSA A7シューティングスター(OHV500ccツイン)だった。1960年代前半までのレースの大排気量クラスは、輸入車が上位を占めていた。
<距離がたった1.3kmの東京高速道路/1959年>
1959(昭和34)年6月10日、東京・銀座を囲む外堀・汐留川・京橋川を埋め立てて造られた東京高速道路が開通。とは言え、開業当初は土橋~鍛冶橋間のたった1.3km、幅員12~35mの北行きの無料開通だったが、珍しいコースを楽しもうと、走り屋の遊び場になり、新数寄屋橋北側にある駐車場には週末にカミナリ族などがたむろした。制限速度は四輪40km/h、バイク32km/h。一方当時のバイク雑誌の広告には、「アクセル一杯、140km/hの魅力」などとスポーツ車の高性能ぶりが謳われていた。
<軽三輪やトヨエースの台頭/1960年>
1960(昭和35)年、東京・江戸川区一之江橋西詰めを起点とし、船橋までが開通した京葉道路。写真は終点付近を千葉方面へ向かうホンダ・ベンリイC92(125cc)。左にはオート三輪の簡易性と四輪車の特徴を生かしたトヨエースの鼻先が見え、その前を幌を付けた軽三輪で角ハンドルのミゼット、その前方には丸ハンドルのミゼットが走る。249cc(後に305cc)2ストローク単気筒で300kg積みの軽三輪車ミゼットは、バイクを商用・配達に使っていた人たちの乗り換え需要が多かった。
<のどかだった表参道/1960年代前半>
今や世界に冠たる洒落た通りの東京・表参道だが、これは1960年代初めの風景。左はホンダ・ドリームC70(250cc)、右はヤマハYD2(250cc)のようだ。前方は表参道交差点。明治神宮設営時に付帯事業として造られた幅36m、直線1kmの参道を、神宮前交差点方面から遠望。当時参道での駐車は自由で、Uターンも可能だった。明治神宮の主祭神は明治天皇と昭憲皇太后で、創建は1920(大正9)年。明治神宮は毎年初詣日本一の参拝者を集めることでも有名。
<白金台にも都電は走った/1960年代>
都電の系統No5は目黒駅前~永代橋間を走っていた路線だが、1967(昭和42)年12月9日に廃止された。車道が狭いために路上に停留所(プラットフォーム)はなく、歩道上で電車の到着を今や遅しと待つ客は、車やバイクを除けながら都電へ一斉に駆け寄った。この停留所は今や有閑マダムの「シロガネーゼ」で知られる白金台の停留所。都電には「乗降者最優先」と後続車両への注意が縦書きされる。都電の前方には三輪車、左端には赤色の郵便自転車が見える。
<年産100万台規模のホンダ鈴鹿製作所/1960年代前半>
ホンダ鈴鹿製作所のラインを流れるスーパーカブC100。鈴鹿はスーパーカブ専用の無窓・空調完備の工場として1960(昭和35)年稼働。国産バイクはスーパーカブをもって、マスプロ生産体勢を確立した。それまでの工場は当時、トタン張りで雨風を避けられる安普請が一般的だったが、「高精度な加工機で精度の高い製品を造るためには管理された生産工場が必須」とのことで同製作所が建てられ、後に鈴鹿はホンダ四輪の生産工場に転用された。
250ccスーパースポーツが台頭した1960年代
<箱根新道を走るホンダCB72/1962年>
有名な温泉地の箱根湯本や強羅を避け、芦ノ湖周辺へのアクセスを改善するため、静岡方面との幹線道路として1962(昭和37)年3月31日に全国2番目の自動車専用道路として開通した箱根新道。新装ホヤホヤの道を登るブリッジ付きアップハンドルを取り付けたドリームCB72。当時2輪車の通行料は50円だった。ホンダの型式は当時、CBの後の70番台前半が250ccクラスを意味したが、車名に排気量表示がされた最初のモデルは1965年発売のCB450である。
<ヤマハ初の本格250スポーツ「YDS1」/1959年>
1959年、日本初の5段変速+タコメーター装備で登場のヤマハスポーツYDS1(250cc)のデザインは、GKダイナミックスの存在感を高めた。ヤマハの主要機種のデザインは現在もGK(Group of Koikeの略)が担うが、その母体が結成されたのは1952(昭和27)年だった。一方のホンダは、CB72以前から造形室のデザイナーが手がけていた。1960年代、ホンダとヤマハファンは明確に分かれ、交差点ではドラッグレースを思わせるスタートがよく見られた。
<YDS1の浅間火山レース仕様/1959年>
YDS1にはロードレース用と、モトクロス用のキットパーツが用意された。通称「浅間タンク」という24L容量の赤色燃料タンクやストッパー付きシート、消音器なしのチャンバーを取り付けたYDS1が町中を走り回った。ノビータイヤ、アップマフラーを含んだスクランブラーキット一式は当時3万653円。第1回全日本モトクロスが大阪・信太山で開かれ、1960年に朝霧高原で開かれた第2回にはYDS1のキット付きモトクロッサーが出場した。
<ホンダ初の250ccスーパースポーツ「CB72」/1960年>
1960年登場のドリームCB72スーパースポーツは、アメリカホンダから急きょスポーツ車が欲しいとの要請で生まれた。エンジンはC72を強化してチューンし、ダイヤモンド型パイプフレームに搭載。国内では「トップで70km/h以下は走れません」のコピーが有名になった。デザインは本田技術研究所の車体課造形室だが、あまりにヤマハYDS1のデザインが鮮烈で、そのイメージにならないように悩んだと当時のデザイナーは話していた。
文●福島新介 写真●八重洲出版 まとめ●モーサイ編集部・阪本
こんな記事も読まれています
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!
愛車を賢く売却して、購入資金にしませんか?
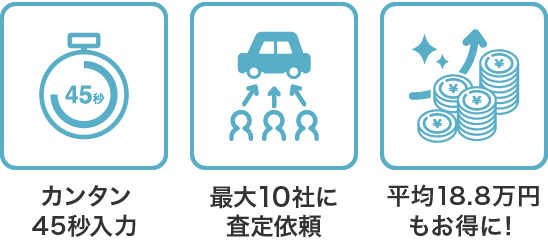
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!
愛車を賢く売却して、購入資金にしませんか?
おすすめのニュース
-
-
日刊自動車新聞0
-
Auto Prove0
-
日刊自動車新聞0
-
-
バイクのニュース5
-
月刊自家用車WEB0
-
-
motorsport.com 日本版0
-
愛車管理はマイカーページで!
登録してお得なクーポンを獲得しよう
おすすめのニュース
-
-
-
-
-
-
THE EV TIMES0
-
-
AUTOSPORT web0
-
AUTOSPORT web0
-
日刊自動車新聞6
-
乗りものニュース5
-
-
-
Auto Messe Web11
-
motorsport.com 日本版0
-
-
AutoBild Japan2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AUTOSPORT web0
-
日刊自動車新聞7
-
-
-
業界ニュースアクセスランキング
-
お金持ちがこぞって買うのも納得! 新型レクサスLMに乗ったらライバルなんて存在しないことがわかった
-
4年で108人死亡 岡山県「人食い用水路」はなぜ誕生したのか? 危険性は近年緩和も、そもそも存在するワケとは
-
日産「新型スポーツSUV」まもなく登場へ! 430馬力超え×「GT-Rの技術」融合!? 6月発売の最強”フラッグシップ” 新型「アリア NISMO」 どんなクルマ?
-
ダンプカーの車体にある「謎の文字と番号」の正体は? 「足立 営 12345」は何を意味しているのか 実は「経済成長」と深い歴史があった!?
-
ホンダ新型「シティ」発表! スポーティな「RS」もある「コンパクト5ドアハッチバック」! 精悍顔な“新モデル”に熱望の声! 馬で予約受付開始
コメントの多い記事
-
無給油で1000kmオーバーを走行できるクルマがゴロゴロ! 国産ハイブリッド&ディーゼルって改めて考えると凄くないか!?
-
ヘッドライトの検査が「ロービームのみ」への変更で「落検車」続出の可能性! 旧車乗りに突きつけられる厳しい現実
-
新型N-BOXより全然安い[レクサスCT]!! プリウスベースも全く別物! おじさんにオススメしたいハッチバック3選
-
日産の「超凄い“フェアレディZ”」実車公開! 専用エアロ装備の“ド迫力仕様”! 4本出しマフラーも超カッコイイ「フェアレディZ IMPUL」登場
-
軽自動車は”特別ルール”で安全性能が低い!? アイデア豊富の[スペーシア]は販売1位の[N-BOX]にどう戦うのか







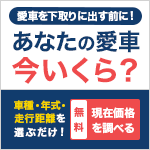
みんなのコメント